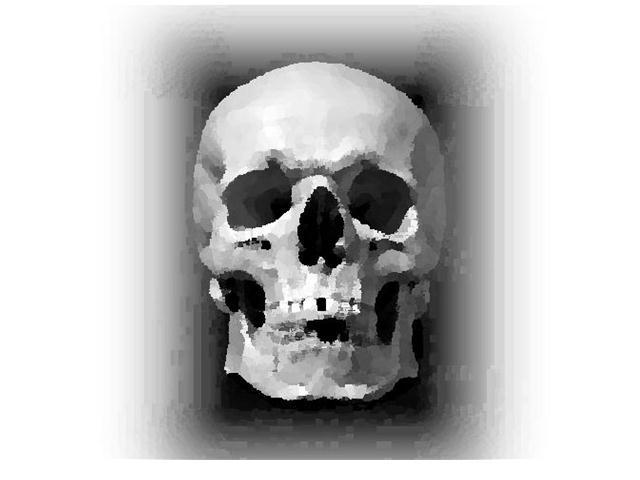環状列石は、何かをモデルにして描いているはずである。この土器には環状が二重になった輪で描かれている。これが、実在する上空から見た絵地図といえないか。大きな円は「夏季」で、小さい方は「冬季」になる。中間の楕円形のような所は「秋」「春」の時期と思われる。次の画像は釈迦堂遺跡の「渦巻き土鈴」となっているが、このモデルは「太陽」であろう。太陽の運行は「朝日で出て来て、日中は地上を照らし、夕日となって沈む。 . . . 本文を読む
『野中堂環状列石、万座環状列石は石を様々な形に組み合わせた配石遺構が二重の環状を形成しているのが特徴です。』この土器には、様々な情報が盛りだくさんに含まれていると感じます。『「日時計状組石」は、各々の環状列石の中心から見て北西側にあり、外帯と内帯の間に位置しています。』と解説されています。「二重の輪 日時計状」が土器面に模様として表現されているかです。土器の地上部分を拡大してみました。この模様の意 . . . 本文を読む
この土器は大湯環状列石を解明する重要な意味内容を含んでいると察します。この土器の模様を読み解きたいものです。初めに「天空」と「地上」の部分を拡大して見ました。「天空」と「地上」の部分に「絵図」が描かれています。これは「環状列石の姿」だと仮想しています。一部分を拡大した「天空」と「地上」の部分です。地上部分には、下の画像のような現風景が記されているものと期待しています。現風景も絵図として描かれている . . . 本文を読む
次の土器は、大湯環状列石の出土品でも特別な要素をもった遺物かと思います。天空に向かって羽ばたいているような体型です。
「土器には多様な器種があるが、中でも口縁に中空の突起が付く深(ふか)鉢(ばち)形土器」と解説もなされています。
色々な要素を含んだ貴重な土器にちがいありません。
それは「現世の地上の世界」と「霊の行く天空の世界」が描かれていることです。
. . . 本文を読む
大湯環状列石には「祭祀用具」の土器類が数多く出土しています。ここで二つの土器を比べて検討してみます。二つの土器が並んだ画像がありました。凸と凹という感じに見えます。土器の模様も意味が全く異なるものと思いました。凸型の土器は、口縁部分と首部分は「天空」に願いが届くように・・・。腹部は「地上」と「地底」に分けられます。※基本形(下記)に合致します。右の凹型の土器を逆さまに加工してみました。「この世」と . . . 本文を読む
大湯環状列石は二つの大きな環状列石があり、祭祀用と思われる遺物が多く出土しています。再度、解明を試みます。ちがう解釈が出てくるのも楽しいものです。球状の土器に見えます。上部の首と思われる部位がありませんし、下の方の画像がありません。、何を模しているのでしょう。この土器の下半分が判るような画像を見つけました。下半分は「無紋」の半球状でした。「地底」だと判断できました。「黄泉の国」ともいえます。土器の . . . 本文を読む
大湯環状列石の土器です。首の長い形がはっきり分る完成品のように見えます。祭祀用の土器ですが、ありがたいことに上下四段階に分けて説明ができそうです。上から「天空」ですが「カムイ」などと具体的な名詞は決めていません。後日考えます。長い首は「天空への道」と思います。球状の部分は上の半分は現実の生活の場で「地上」としました。下半分の無紋の部分を「地底」と名付けました。「黄泉の国」ということでしょうか。地上 . . . 本文を読む
大湯環状列石には名称のように、二つの大きな環状列石があり、祭祀用と思われる遺物も多く出土しています。再度、祭祀用の多い遺跡の解明を試みたいと思います。この土器に「〇」が二つあるようです。これが大湯環状列石の姿と合うように思えました。つまり、実際の姿が土器面に模されているようなのです。土器の底部が無地の面がありますが「地底」と仮に呼ばせてもらいます。一部拡大して見ました。地上の様子ではないかと想像し . . . 本文を読む
「公益財団法人 群馬県埋蔵文化財調査事業団|群馬の遺跡・出土品「埋文ギャラリー」縄文土器と説明があります。「〇状の跡」が固まって土器面についています。下記のような説明文がありました。「道訓前遺跡は⾚城⼭麓の緩やかに南⻄に伸びる台地(標⾼320メートルから330メートル)に⽴地しています。 発掘調査により本遺跡が縄⽂時代中期中葉から後葉にかけての⼤規模な環状集落であることが判明しました。」大規模な環 . . . 本文を読む
「台付深鉢形土器 宮之脇遺跡B地点出土(可児市蔵)」と説明があります。この土器を見て「高坏」と思うところに「穴」が開いています。これは、どのような意味があるのだろうか?この穴は、単なる装飾的なものでなく「生活環境」「地形」となんらか関連するものてあると考えた。穴を「滝つぼ」や「崖」「淵」などが浮かんだ。この土器を「滝」として見立てることにして説明する試みをしてみた。白装束で滝に打たれて修行している . . . 本文を読む