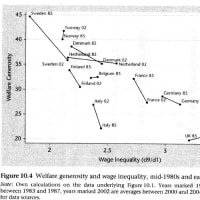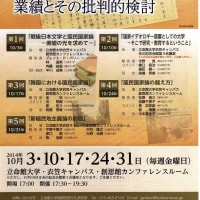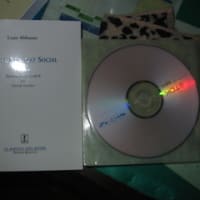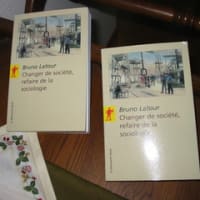今回は社会学の「古典」について(^_^.)。
デュルケムの『社会分業論』は、社会学を学問として確立したはじめての著作、と言うことが出来るでしょう。社会学に興味を持ち始めの人で、何か「古典」を読んでみたいという人、あるいは初期の社会学がいかなる問題関心を持ち、どのように構想されたのかを知るには一番の著作です。
でも、 なにを今更、こんな手あかのついた著作をここで紹介するの?、と思うかもしれませんね。
しかし最近私は、このデュルケムの著作には、非常に新鮮な読みが可能なのではないかと考えています。とりわけ、フランス的共和主義の伝統という文脈のなかでこの著作を読むのであれば、その意義はとりわけ明確になるだろう。実際、フランス的共和主義は、中間集団を否定し、一人一人の自律した個人を前提としている。この伝統の中では、「有機的連帯」という中間集団の形成をポジティブにとらえる議論は、むしろ希有だといえる。
中間集団を認めないフランス的共和主義は、移民を多く受け入れ、さまざまなエスニシティーを抱えるに至っている現在のフランスでは、もはや限界を迎えているように思われる。おそらくこれからは、中間集団としてのコミュニティーの存在を容認しつつ、それを介して社会的連帯を形成するシステムが求められるであろう。
この点では、デュルケムの議論は、まさに現代においてこそ読まれるべきとも言えよう。
この著作のアマゾンにおけるページには、以下のリンクでジャンプ出来ます。
社会分業論〈上〉
社会分業論〈下〉
デュルケムの『社会分業論』は、社会学を学問として確立したはじめての著作、と言うことが出来るでしょう。社会学に興味を持ち始めの人で、何か「古典」を読んでみたいという人、あるいは初期の社会学がいかなる問題関心を持ち、どのように構想されたのかを知るには一番の著作です。
でも、 なにを今更、こんな手あかのついた著作をここで紹介するの?、と思うかもしれませんね。
しかし最近私は、このデュルケムの著作には、非常に新鮮な読みが可能なのではないかと考えています。とりわけ、フランス的共和主義の伝統という文脈のなかでこの著作を読むのであれば、その意義はとりわけ明確になるだろう。実際、フランス的共和主義は、中間集団を否定し、一人一人の自律した個人を前提としている。この伝統の中では、「有機的連帯」という中間集団の形成をポジティブにとらえる議論は、むしろ希有だといえる。
中間集団を認めないフランス的共和主義は、移民を多く受け入れ、さまざまなエスニシティーを抱えるに至っている現在のフランスでは、もはや限界を迎えているように思われる。おそらくこれからは、中間集団としてのコミュニティーの存在を容認しつつ、それを介して社会的連帯を形成するシステムが求められるであろう。
この点では、デュルケムの議論は、まさに現代においてこそ読まれるべきとも言えよう。
この著作のアマゾンにおけるページには、以下のリンクでジャンプ出来ます。
社会分業論〈上〉
社会分業論〈下〉