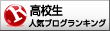高校生のみなさん、(^◇^)ノ お~ぃ~ゲンキか!
みなさん、既に知っていると思うが、第1段階選抜結果が発表されておりますね・・・・
国公立大の出願が7日に締め切られ、一部の大学・学部で第1段階選抜が行われた。「国公立大の第一段階選抜」とは、志願者数が募集人数を大幅に上回った場合、個別試験の実施が困難になるなどの事態を予測し、あらかじめセンター試験の得点を使って受験者を絞る大学・学部が適用する選抜方法である。これが「第1段階選抜」と呼ばれるもので、更に大学・学部はその合格者に対して個別試験(第2段階選抜)を実施するのである。
平成18年度入試で、第1段階選抜の実施予告している大学・学部数は55大学175学部です。予告なので、実際に第1段階選抜が行わない大学もあり、既に≪第1段階選抜状況をHPに掲載している一部大学一覧≫と、≪第1段階選抜を実施しないと発表した大学一覧≫を下記にピックアップしておきますので、必ず覗いて見てください。
≪第1段階選抜状況をHPに掲載している一部大学一覧≫
◆ 東北大学
◆ 千葉大学
◆ 一橋大学
◆ 京都大学
◆ 神戸大学
≪第1段階選抜を実施しないと発表した大学一覧≫
◆ 東京工業大学
◆ お茶の水女子大学
◆ 大阪市立大学


みなさん、既に知っていると思うが、第1段階選抜結果が発表されておりますね・・・・
国公立大の出願が7日に締め切られ、一部の大学・学部で第1段階選抜が行われた。「国公立大の第一段階選抜」とは、志願者数が募集人数を大幅に上回った場合、個別試験の実施が困難になるなどの事態を予測し、あらかじめセンター試験の得点を使って受験者を絞る大学・学部が適用する選抜方法である。これが「第1段階選抜」と呼ばれるもので、更に大学・学部はその合格者に対して個別試験(第2段階選抜)を実施するのである。
平成18年度入試で、第1段階選抜の実施予告している大学・学部数は55大学175学部です。予告なので、実際に第1段階選抜が行わない大学もあり、既に≪第1段階選抜状況をHPに掲載している一部大学一覧≫と、≪第1段階選抜を実施しないと発表した大学一覧≫を下記にピックアップしておきますので、必ず覗いて見てください。
≪第1段階選抜状況をHPに掲載している一部大学一覧≫
◆ 東北大学
◆ 千葉大学
◆ 一橋大学
◆ 京都大学
◆ 神戸大学
≪第1段階選抜を実施しないと発表した大学一覧≫
◆ 東京工業大学
◆ お茶の水女子大学
◆ 大阪市立大学