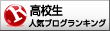高校生のみなさん、(^◇^)ノ お~ぃ~ゲンキか!
みなさん、国公立大学再編・統合に関してあちこちで話題になっていますね。
既に、大阪大学と大阪外国語大学は統合に合意済みで2007年10月に統合予定で、2008年4月学生入学予定をしています。大阪外国語大学は、大阪大学外国語学部として再出発します。
現在までに国公立大学再編・統合に関して、統合を協議・検討中の国公立大学は下記の通りです。
◆ 弘前大学+秋田大学+岩手大学
教育学部の再編・統合を中心に協議中。
◆ 茨城大学+宇都宮大学+群馬大学+埼玉大学
4大学が連携方策について協議中。
◆ 上越教育大学
新潟大学との統合以外にも、富山大学、信州大学との統合も視野に検討中。
◆ 静岡大学+浜松医科大学
統合を協議中。
◆ 豊橋科学技術大学+名古屋大学
名古屋大学と統合を前提に協議。静岡大学・浜松医科大学との統合は見送り。
◆ 愛知教育大学
岐阜大学、豊橋技術科学大学、名古屋大学、三重大学との統合を学内で検討。
◆ 岐阜大学+市立岐阜薬科大学
統合を協議中。
◆ 滋賀大学+滋賀医科大学
滋賀大、滋賀医科大、京都教育大、京都工繊大の4大学で統合を協議中だったが、滋賀大学の学長が、4大学での統合を解消して新たに滋賀大、滋賀医科大の2大学統合を目指し、2005年4月から協議を再開する意向を表明。
◆ 大阪大学+大阪外国語大学
2007年度統合を視野に入れた連携を検討。
◆ 徳島大学+鳴門教育大学+香川大学+高知大学+愛媛大学
連携強化のため四国国立大学協議会設置。5大学での単位互換などを目指す。
◆ 埼玉県立大学
短期大学部を2006年度をめどに廃止し、4年制へ統合・再編する方向で検討中。
◆ 京都府立大学+京都府立医科大学
統合視野に連携検討。
◆ 島根県立大学+島根県立島根女子短大+島根県立看護短期大学
2007年度をめどに、3大学を統合。県立島根女子短大、県立看護短大は「短期大学部」として再編する方向で検討中。
◆ 長崎県立大学+県立長崎シーボルト大学
2005年4月独立行政法人化、2008年度中の再編・統合を検討中。
みなさんがこれから受験を考えている大学がこの中にあるのでしたら、注意深く見ておきましょう・・・・


みなさん、国公立大学再編・統合に関してあちこちで話題になっていますね。
既に、大阪大学と大阪外国語大学は統合に合意済みで2007年10月に統合予定で、2008年4月学生入学予定をしています。大阪外国語大学は、大阪大学外国語学部として再出発します。
現在までに国公立大学再編・統合に関して、統合を協議・検討中の国公立大学は下記の通りです。
◆ 弘前大学+秋田大学+岩手大学
教育学部の再編・統合を中心に協議中。
◆ 茨城大学+宇都宮大学+群馬大学+埼玉大学
4大学が連携方策について協議中。
◆ 上越教育大学
新潟大学との統合以外にも、富山大学、信州大学との統合も視野に検討中。
◆ 静岡大学+浜松医科大学
統合を協議中。
◆ 豊橋科学技術大学+名古屋大学
名古屋大学と統合を前提に協議。静岡大学・浜松医科大学との統合は見送り。
◆ 愛知教育大学
岐阜大学、豊橋技術科学大学、名古屋大学、三重大学との統合を学内で検討。
◆ 岐阜大学+市立岐阜薬科大学
統合を協議中。
◆ 滋賀大学+滋賀医科大学
滋賀大、滋賀医科大、京都教育大、京都工繊大の4大学で統合を協議中だったが、滋賀大学の学長が、4大学での統合を解消して新たに滋賀大、滋賀医科大の2大学統合を目指し、2005年4月から協議を再開する意向を表明。
◆ 大阪大学+大阪外国語大学
2007年度統合を視野に入れた連携を検討。
◆ 徳島大学+鳴門教育大学+香川大学+高知大学+愛媛大学
連携強化のため四国国立大学協議会設置。5大学での単位互換などを目指す。
◆ 埼玉県立大学
短期大学部を2006年度をめどに廃止し、4年制へ統合・再編する方向で検討中。
◆ 京都府立大学+京都府立医科大学
統合視野に連携検討。
◆ 島根県立大学+島根県立島根女子短大+島根県立看護短期大学
2007年度をめどに、3大学を統合。県立島根女子短大、県立看護短大は「短期大学部」として再編する方向で検討中。
◆ 長崎県立大学+県立長崎シーボルト大学
2005年4月独立行政法人化、2008年度中の再編・統合を検討中。
みなさんがこれから受験を考えている大学がこの中にあるのでしたら、注意深く見ておきましょう・・・・