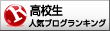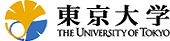高校生のみなさん、(^◇^)ノ お~ぃ~ゲンキか!
みなさん、HageOyaji通信:第422話≪高校生に到達度評価検定案検討開始(中央教育審議会)≫で、文部科学省が高校生対象の到達度検定の実施を検討していることを伝えましたが、この検定は、教科毎にグレードをつけ、大学毎に入学の条件を設けるものとなり、高校在学中に複数回受験可能なものにする方向で議論が進んでいるようです。
この検定制度が実現すれば、将来、到達度評価検定が大学入試センター試験に替わるものとなる可能性も充分にあります。
そうしますと、日本の大学入試制度も何十年ぶりに様変わりすることになりそうです。到達度評価検定についても、大学入試センター試験の今後の動向と睨み、随時詳細を配信していきます。
既に、HageOyaji通信:第423話≪大学センター試験を課すAO入試(北大工学部応用理工系と農学部農業経済学科)≫したように、北海道大学では、AO入試に大学センター試験を課すことで、学力と資質の両方を判定し、より優れた学生を確保できるとの考えから実施します。
これらのことの発端は、みなさんもご承知の通り、「必修科目の未履修問題」からですね。
昨年秋に世界史など必修科目の未履修の問題が全国の高校で相次いで発覚し、文部科学省の調査で、科目の未履修があったのは全国の高校の1割以上が関係していました。
これを受けて文部科学省の諮問機関である中央教育審議会で学習指導要領、高校教育、大学入試のあり方等について議論された中で、伊吹文部科学大臣は、
≪学習指導要領は「必要最低限の学力と教養のレベル」を示したものなので、大学入試に合わせて指導要領を変えることはしないが、現在の高校では、世界史が必修で、日本史と地理はどちらか選択になっているが、センター試験で世界史と日本史が同じ時間にあるのも問題だ。センター試験のあり方も変えなければならない。≫
と、発言されています。
また、同時に国立大学協会は、受験生の地歴離れを救うため、センター試験の科目選択の見直しを
要望し、大学入試センター試験の「地理歴史」からの2科目選択を可能にするように、大学入試センター宛に要望書を提出してきました。
国立大学協会の「大学・大学院政策に関する活動指針」は、
≪国際社会に貢献できる人材を育成するにあたり、「国際理解の推進とわが国の文化と伝統の尊重(現行学習指導要領)」のために世界の歴史と日本の歴史、地理を学ぶことは大変重要だ。 中・高における地理歴史の学習なしに大学教育での人文・社会科学系の教育一般は難しい。≫
そして、「入試制度改革に関する意見書」では、
◆大学教育を受ける前の準備として地歴3科目を履修しておくことがのぞましい。現行のセンター試験の日程の中で地歴の中で複数受験させるのは困難かと思われる。試験のコマ数を増やすことは考えていない。
◆地歴科目と公民科目を混ぜた中から選択できるようにしてもらいたい。
以上の背景から、大学入試センター試験で、現行の「地歴」「公民」を「地歴・公民」1教科に統合する方針を、大学入試センターが固めたことが明らかになってきています。現在の高校一年生が受験する平成22年度から実施する方向で検討されているようです。
もし、この制度が導入されれば、地歴・公民、理科の選択の幅が広がり、「地歴・公民」が1教科になり、現状では不可能な日本史と世界史の2科目を選択することが可能になります。また、理科も同様に物理と地学の2科目を選択することが可能になります。
そうなると、受験生にとっては選択の幅が広がり、受験対策の方法も変わってくるでしょう。
平成22年度以降のセンター試験「社会科」「理科」の選択は:
【現行の大学入試センター試験】
社会科は、
「地理歴史」(世界史A・B、日本史A・B、地理A・B)⇒6科目から1科目を選択
「公民」(現代社会、倫理、政治・経済)⇒3科目から1科目を選択
理科は、
「理科1」(理科総合B、生物I)⇒2科目から1科目を選択
「理科2」(理科総合A、化学I)⇒2科目から1科目を選択
「理科3」(物理I、地学I)⇒2科目から1科目を選択
【平成22年度以降大学入試センター試験】
社会科は、
「地理・歴史・公民」⇒9科目から2科目を選択
(但し、同一科目のA・Bの選択できません)
理科は、
「理科1・2・3」⇒6科目から2科目を選択

の方向で、検討中のようです。
「必修科目の未履修問題」からの一歩も二歩も前進ですね。



みなさん、HageOyaji通信:第422話≪高校生に到達度評価検定案検討開始(中央教育審議会)≫で、文部科学省が高校生対象の到達度検定の実施を検討していることを伝えましたが、この検定は、教科毎にグレードをつけ、大学毎に入学の条件を設けるものとなり、高校在学中に複数回受験可能なものにする方向で議論が進んでいるようです。
この検定制度が実現すれば、将来、到達度評価検定が大学入試センター試験に替わるものとなる可能性も充分にあります。
そうしますと、日本の大学入試制度も何十年ぶりに様変わりすることになりそうです。到達度評価検定についても、大学入試センター試験の今後の動向と睨み、随時詳細を配信していきます。
既に、HageOyaji通信:第423話≪大学センター試験を課すAO入試(北大工学部応用理工系と農学部農業経済学科)≫したように、北海道大学では、AO入試に大学センター試験を課すことで、学力と資質の両方を判定し、より優れた学生を確保できるとの考えから実施します。
これらのことの発端は、みなさんもご承知の通り、「必修科目の未履修問題」からですね。
昨年秋に世界史など必修科目の未履修の問題が全国の高校で相次いで発覚し、文部科学省の調査で、科目の未履修があったのは全国の高校の1割以上が関係していました。
これを受けて文部科学省の諮問機関である中央教育審議会で学習指導要領、高校教育、大学入試のあり方等について議論された中で、伊吹文部科学大臣は、
≪学習指導要領は「必要最低限の学力と教養のレベル」を示したものなので、大学入試に合わせて指導要領を変えることはしないが、現在の高校では、世界史が必修で、日本史と地理はどちらか選択になっているが、センター試験で世界史と日本史が同じ時間にあるのも問題だ。センター試験のあり方も変えなければならない。≫
と、発言されています。
また、同時に国立大学協会は、受験生の地歴離れを救うため、センター試験の科目選択の見直しを
要望し、大学入試センター試験の「地理歴史」からの2科目選択を可能にするように、大学入試センター宛に要望書を提出してきました。
国立大学協会の「大学・大学院政策に関する活動指針」は、
≪国際社会に貢献できる人材を育成するにあたり、「国際理解の推進とわが国の文化と伝統の尊重(現行学習指導要領)」のために世界の歴史と日本の歴史、地理を学ぶことは大変重要だ。 中・高における地理歴史の学習なしに大学教育での人文・社会科学系の教育一般は難しい。≫
そして、「入試制度改革に関する意見書」では、
◆大学教育を受ける前の準備として地歴3科目を履修しておくことがのぞましい。現行のセンター試験の日程の中で地歴の中で複数受験させるのは困難かと思われる。試験のコマ数を増やすことは考えていない。
◆地歴科目と公民科目を混ぜた中から選択できるようにしてもらいたい。
以上の背景から、大学入試センター試験で、現行の「地歴」「公民」を「地歴・公民」1教科に統合する方針を、大学入試センターが固めたことが明らかになってきています。現在の高校一年生が受験する平成22年度から実施する方向で検討されているようです。
もし、この制度が導入されれば、地歴・公民、理科の選択の幅が広がり、「地歴・公民」が1教科になり、現状では不可能な日本史と世界史の2科目を選択することが可能になります。また、理科も同様に物理と地学の2科目を選択することが可能になります。
そうなると、受験生にとっては選択の幅が広がり、受験対策の方法も変わってくるでしょう。
平成22年度以降のセンター試験「社会科」「理科」の選択は:
【現行の大学入試センター試験】
社会科は、
「地理歴史」(世界史A・B、日本史A・B、地理A・B)⇒6科目から1科目を選択
「公民」(現代社会、倫理、政治・経済)⇒3科目から1科目を選択
理科は、
「理科1」(理科総合B、生物I)⇒2科目から1科目を選択
「理科2」(理科総合A、化学I)⇒2科目から1科目を選択
「理科3」(物理I、地学I)⇒2科目から1科目を選択
【平成22年度以降大学入試センター試験】
社会科は、
「地理・歴史・公民」⇒9科目から2科目を選択
(但し、同一科目のA・Bの選択できません)
理科は、
「理科1・2・3」⇒6科目から2科目を選択

の方向で、検討中のようです。
「必修科目の未履修問題」からの一歩も二歩も前進ですね。