年末に風邪引きで寝込んでいて月初もなんとなく不調なのか、夜は毎晩出かける用事があり歩きに行くことを躊躇していたのかもしれません
連休は3連歩で楽しみました
9日、間伏林道から
 いつもの入り口
いつもの入り口

いつもの道
 いつもの海
いつもの海
 いつものきつい坂 あそこまで行くぞ!(はぁ!はぁ!)
いつものきつい坂 あそこまで行くぞ!(はぁ!はぁ!)
 いつもの内輪 でも、ちょっと写真のアングルが違う為か ここどこ?
いつもの内輪 でも、ちょっと写真のアングルが違う為か ここどこ?
 左に行けばいつもの外輪山 外輪山に沿って行くと
左に行けばいつもの外輪山 外輪山に沿って行くと
 通称“幻の湖”勿論今日は幻
通称“幻の湖”勿論今日は幻
 干上がった地面に割れ目がその模様は空撮で見た大地。あの線は道路か?畑の区切りの椿の木?に見えてしまう
干上がった地面に割れ目がその模様は空撮で見た大地。あの線は道路か?畑の区切りの椿の木?に見えてしまう
 矢印があるのですがとこに行くの?私は分かるのですが、初めての人は分からない!メンテナンスをマメにしてもらいたいものです!
矢印があるのですがとこに行くの?私は分かるのですが、初めての人は分からない!メンテナンスをマメにしてもらいたいものです!
10日大島公園ふのうの滝往復
11日旧泉津小学校から石の反橋、笠松から公園往復
 旧道は今歩く人が少ないので荒れています
旧道は今歩く人が少ないので荒れています
 目的地ですが 分かりますか?
目的地ですが 分かりますか?
 “石の反橋”流れて来た溶岩流が壊れたりしてたまたまアーチになったもの
“石の反橋”流れて来た溶岩流が壊れたりしてたまたまアーチになったもの
今は上を渡ることができません。草や木が大分育ってしまいましたしアーチが細くなってきたような気がします。うーん崩れなければよいですが

 この3日間は晴れで風も無く外遊びに最適でした(完全復活なる)(しま)
この3日間は晴れで風も無く外遊びに最適でした(完全復活なる)(しま)
連休は3連歩で楽しみました
9日、間伏林道から
 いつもの入り口
いつもの入り口
いつもの道
 いつもの海
いつもの海 いつものきつい坂 あそこまで行くぞ!(はぁ!はぁ!)
いつものきつい坂 あそこまで行くぞ!(はぁ!はぁ!) いつもの内輪 でも、ちょっと写真のアングルが違う為か ここどこ?
いつもの内輪 でも、ちょっと写真のアングルが違う為か ここどこ? 左に行けばいつもの外輪山 外輪山に沿って行くと
左に行けばいつもの外輪山 外輪山に沿って行くと 通称“幻の湖”勿論今日は幻
通称“幻の湖”勿論今日は幻 干上がった地面に割れ目がその模様は空撮で見た大地。あの線は道路か?畑の区切りの椿の木?に見えてしまう
干上がった地面に割れ目がその模様は空撮で見た大地。あの線は道路か?畑の区切りの椿の木?に見えてしまう 矢印があるのですがとこに行くの?私は分かるのですが、初めての人は分からない!メンテナンスをマメにしてもらいたいものです!
矢印があるのですがとこに行くの?私は分かるのですが、初めての人は分からない!メンテナンスをマメにしてもらいたいものです!10日大島公園ふのうの滝往復
11日旧泉津小学校から石の反橋、笠松から公園往復
 旧道は今歩く人が少ないので荒れています
旧道は今歩く人が少ないので荒れています 目的地ですが 分かりますか?
目的地ですが 分かりますか? “石の反橋”流れて来た溶岩流が壊れたりしてたまたまアーチになったもの
“石の反橋”流れて来た溶岩流が壊れたりしてたまたまアーチになったもの今は上を渡ることができません。草や木が大分育ってしまいましたしアーチが細くなってきたような気がします。うーん崩れなければよいですが

 この3日間は晴れで風も無く外遊びに最適でした(完全復活なる)(しま)
この3日間は晴れで風も無く外遊びに最適でした(完全復活なる)(しま)


































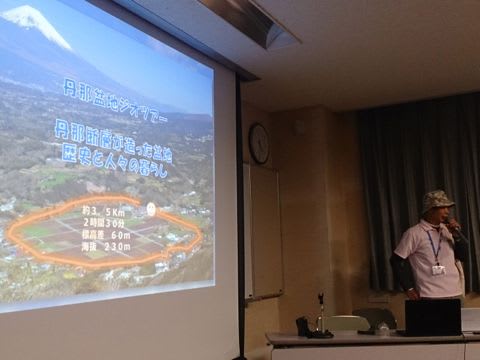










































 家から2キロの地点にある筆島 今日も波立っています
家から2キロの地点にある筆島 今日も波立っています な~に?
な~に? 逃げないで~
逃げないで~ はいこっち向いて!
はいこっち向いて! 実はこんなに小さい子でした
実はこんなに小さい子でした




















