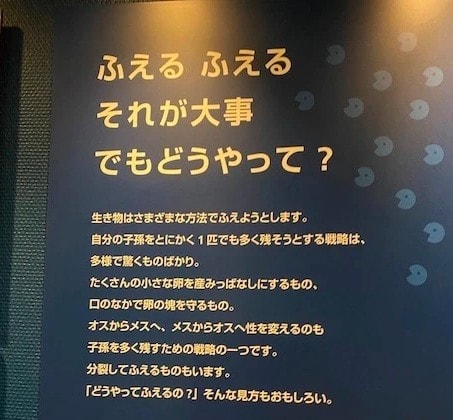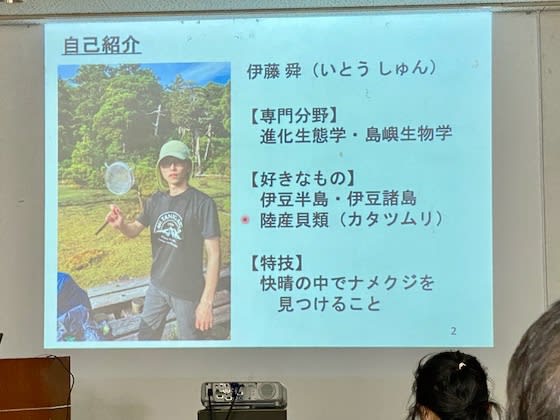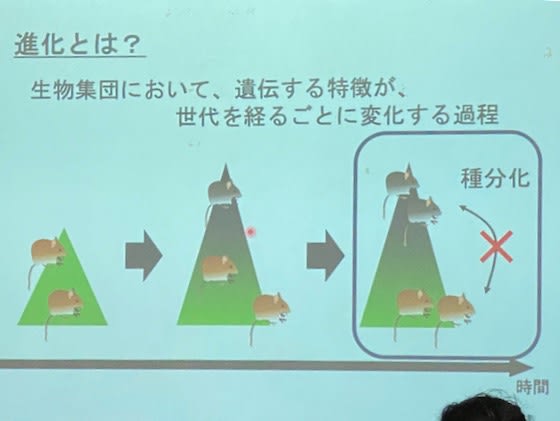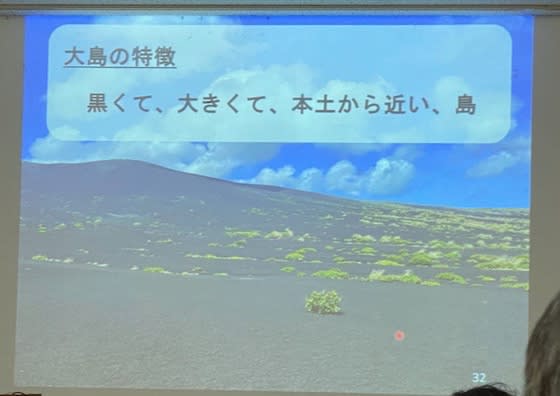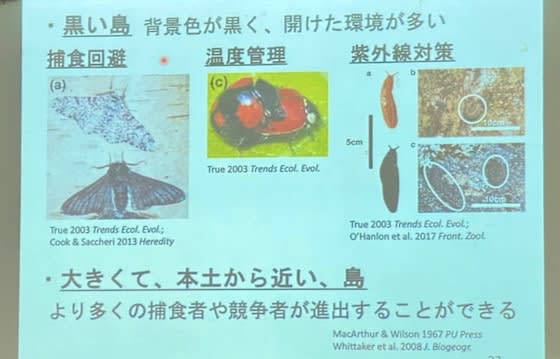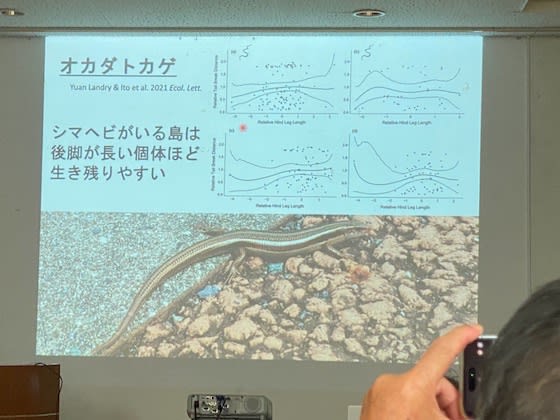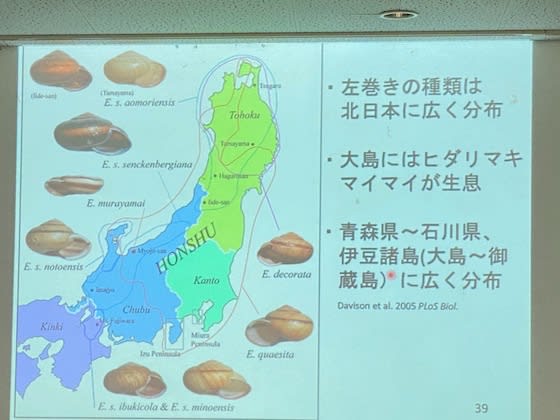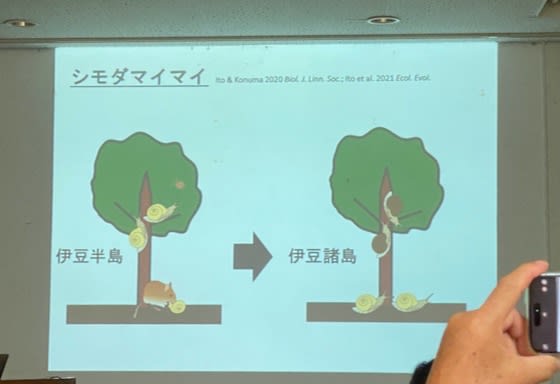被災されたみなさま、関係者のみなさまに心よりお見舞い申し上げます。
今尚続く余震により、不安の中、お過ごしの方が多くあられることに心が痛みます。
みなさまの元に支援の手が届きますよう、
1日も早い復旧、復興となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
時には脅威にもなる自然の前には人間は無力でありながらも、
自然のメカニズムや自ら住んでいる土地に関して「知る」ことは、
主体的に暮らすために、なくてはならないと感じています。
現在、冬休みの帰省中で、夫の実家である宮城県仙台にいます。
ここ、東北の地も度重なる震災の被害にあっている地域です。
杜の都として知られる仙台、
中心地から少し歩けば、川と緑が広がっています。
散歩コースの広瀬川の河岸です。

崖に白い露頭が見えていて、

帰って調べてみると、
「350 万年前の火山活動によってもたらされた広瀬川凝灰岩部層」* とのことで、
「仙台市街を構成する大地は...たび重なる変動を経験しながら
海と陸の時代を繰り返し、現在の姿となった」*
とあり、動く大地にわたしたちは暮らしているのだと、あらためて痛感しました。
*参考文献「仙台の大地の成り立ちを知る」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geosoc/119/Supplement/119_2013.0037/_pdf
広瀬川を挟んで青葉山にある仙台城跡にも向かいました。

約400年前に伊達政宗公によって築かれた仙台城、
建物は廃城令や空襲の火災で失われてしまいましたが、
壮大な石垣は国の史跡指定もされ、
これまでに何度も災害に合いながらも修復されてきました。
昨年の年末に訪れた時は、
2022年3月に発生した地震により石垣が複数箇所で崩落がおきていましたが、
こちらは通れるようになっていました。


今も尚、別箇所で修復しているところがあるようです。
こちらは切石積みという切られた石が積まれています。

しかしこの石垣、ひとつひとつが大きくて、重機のない当時の建設も大変な労力だったことでしょう。

そんなことを考えていたら、石垣石の割り方が展示されていました!

伊達政宗の騎馬像も傾いてしまい、昨年は見れませんでしたが、修復され、戻ってきていました!

仙台のシンボル的存在✨ シルエットがかっこいい!

石垣の復旧にかかる費用は約10億円かかるそうで、
その一部(2000万円)を仙台市がクラウドファンディングで寄付を募っていました。
https://readyfor.jp/projects/ishigakifukkyu
このように、みなの思いがわかりやすい形で集って届けられるクラウドファンディング、
いいですね。
ひとりでは無理なことでもみんなで前を向いて歩んでいきたいです。
困難も支え合って乗り越える社会の一員であることを誇りに思う
2024の始まりでした。
(ユリカ)




















 これ酸素ボンベ これが中々重いすいていた
これ酸素ボンベ これが中々重いすいていた

 こんなのも辛いです
こんなのも辛いです