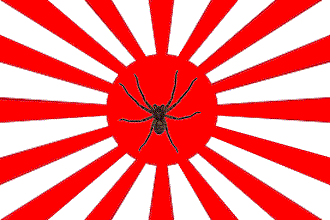菅義偉によって日本学術会議会員の任命が拒否された加藤陽子について知りたくて、図書館に『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(朝日出版社)を予約したが、11年前に出版されたにもかかわらず、人気が高くて、いまだに借りられない。しかたがなく、彼女の指導教授だった伊藤隆の本を読む。
伊藤隆は私の15歳上の昭和史の大家である。しかし、彼の『歴史と私』(中公新書)を読んでも、なぜ、日本がアメリカとの戦争に突っ込んでいったがわからない。わかるのは、彼が民青の駒場のキャップになり、共産党にもはいったが、共産党に疑いを持ち、共産党が大きらいになったということだけである。
〈 共産党にどっぷり浸かっていた私は、学生大会の議長になると反対者の発言を許さないなど強引な進行をしたり、民青本部で『若き戦士』という機関紙作りに励んだりしていました。〉
〈 許せないと思うことがいくつかあって、その年の7月に共産党が従来の武装闘争方針から大転換を行った大会、いわゆる「六全協」のときには仲間と代々木の党本部に押しかけて抗議し、日本共産党を見限りました。〉
〈 本郷に来てからは共産党から離れて、やっと本気で近代史の勉強を始めました。〉
私が大学にはいったときも、駒場の「学生大会」の無茶ぶり、「強引な進行」は変わっていなかったが、民青が主導権を握っていなかった。本郷にいったときの理学部の「学生大会」はもっと普通のもので、ルールに基づいて運営されていた。民青と新左翼とノンポリとがつりあっていた。このなかで、東大闘争といわれるストライキが始まった。
たぶん、共産党の方針転換が定着していたのだろう。「強引さ」は一部の新左翼が引き継いでいたのだろう。したがって、私には伊藤隆の共産党嫌いが理解できない。
『歴史と私』は、権力の中枢にいた人間たちの資料発掘についての自分の功績を語っているだけなので、軍部のなかの争いや、軍部の台頭の理由がわからない。私は、大局的には、第1に、軍部を抑えるものないという大日本帝国憲法の欠陥と、第2に、政府による左翼運動の強圧的弾圧とによって起きたことだと思う。
ここで、左翼とは、人間が人間を支配することを拒否する者たちを私はさす。
つづいて、伊藤隆の『大政翼賛会への道』(講談社学術文庫)を読む。こちらは、軍部や革新右翼の動きに詳しい。伊藤は「革新」という言葉を、体制内ルールを無視しても体制変革を目指す者たちという意味で使っている。「革新」はテロやクーデターに結びつく言葉である。
大日本帝国憲法は、天皇が言い出さなければ、「神聖にして侵すべからず」の天皇制を廃止できないよう規定していた。天皇制を支持する右翼が、体制を「破壊」せよという革新右翼になる理由がわからない。
伊藤隆は、「革新」派が台頭した理由を、ドイツやイタリアの影響で、米英のデモクラシーすなわち資本主義が日本の大衆の困窮を生んだと考えるようになったからだ、と考えているようである。
伊藤は、本著で、近衛新党運動を推進した日本社会主義研究所の暫定綱領を引用している。
〈 我等は日本伝来の天皇制をもって日本国民最適の国家形態と信じ、いっさいの経綸をこの前提のもとに行なわんとす〉
〈 我等は生産手段の私有を基礎とする資本主義の無政府経済性をもって我が国民の生活圧殺するものと認め、できえるだけ急速にこれが撤廃を期す〉
デモクラシーが資本主義だというのはおかしいが、天皇に主権があるという「国体」を問題にしないと、この誤りに落ち込むのだろう。したがって、左翼への弾圧が「革新」右翼の台頭を招いたと言える。
自由平等の「平等」を、人間が人間を支配することの廃止と理解せず、みんなが同じ服を着て同じものを食べると考えたことに、「革新」右翼の誤りがあったと思う。