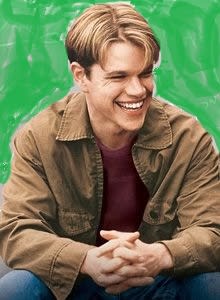2018年のイギリス・フランス映画『ガーンジー島の読書会の秘密』は、イギリスの若い女流作家がノルマンディー沖の小島の読書会を訪れ、愛が芽生え、結婚するという物語である。占領されるという戦争の記憶を扱いながら、美男美女が結ばれるというハッピーエンドの物語である。
映画の原題 “The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society”は、その読書会の名前である。直訳すれば「ガーンジー島の文学とジャガイモの皮のパイの会」となる。 “Guernsey”がその島の名前であるが、私には「ガーンジー」とは聞こえず、「グールンズィ」と聞こえる。発音記号で示せば、[ˈɡɜːrnzi]となる。
グールンズィ島はイギリス王室の属領だが、第2次世界大戦中、ドイツ軍に占領された。読書会の名前は、4人の島民が夜歩いていると、ドイツ軍の兵士にとがめられ、とっさに「グールンズィ島の文学とジャガイモの皮のパイの会から帰宅する途中です」と答えたことからくる。そして、本当に読書会を継続的に開くことになる。
私自身は読書会というものを経験したことがないが、映画では、誰かが本の紹介者になり、何ページかを朗読し、そのあと、メンバーが議論する形をとっていた。
戦後、1946年に、島を訪れた女流作家のジュリエットは、読書会に主催者のエリザベスがいないことに気づき、それを探り始める。読書会のメンバーにとっては、それは、秘めておきたい悲しい記憶であった。エリザベスはドイツ軍に連れられていき、戦争が終わっても戻ってこないのである。いっぽう、ジュリエットが宿泊した宿の女主人は、読書会のメンバーはウソつきで、エリザベスをドイツ軍兵士の子どもをやどした「あばずれ」とののしる。
ジュリエットが島に訪れるきっかけを作った読書会の一人(男)、ドースィ(Dawsey)は、エリザベスとドイツ軍兵士の愛は真剣で、その間に生まれた女の子を自分が育てていると話す。
映画は、ジュリエットとドースィの恋心に焦点を当てているので、なぜ、島の女とドイツ兵士に愛が芽生えたのか私にはわからない。たぶん、その兵士は優しい人なのだろう。その兵士が、兵営を抜け出て、エリザベスと密会していることを密告する島民がいて、島から追放されるが、載せられた船が連合軍の攻撃に会い、船ごと死んでしまう。
一方、エリザベスは、脱走した捕虜少年のために夜間に薬を取りに行くが、ドイツ軍につかまり、エリザベスは大陸の収容所送りになり、少年は射殺される。
ジュリエットはアメリカ人の婚約者にエリザベスの行方を調査してもらう。エリザベスが、収容所で少女を殴っている看守を止めようとして、射殺されたという知らせをもって、婚約者はジュリエットを軍用機で迎えに来る。
とても、複雑なプロットで、時間の制限がある映画では、どうしても、消化不良になる。じつは、読書会のメンバーが本当の家族であったのか、それとも、疑似家族であったのか、私にはわからない。私は、読書会というもののもつ力を信じたいので、疑似家族であって欲しいと思うが、映画では本当の家族であるようにも見える。
この後、イギリスにもどったジュリエットは、島の読書会メンバーと離れることに耐えられず、婚約者と別れ、ドースィに結婚を申し込むという結末で終わる。
第2次世界大戦終結から70年以上もたって、この映画が作られたのは、心の傷の記憶がまだイギリスやフランスの人々に渦巻いているのではないか。
婚約者など不要な登場人物を消し去り、外部からの侵入者のジュリエットが、読書会をとおして島民の戦争の心の傷を暴くことに焦点を絞ると、もっと、深みのある映画になっただろう。島の女が敵の兵士を愛することこそ戦争のもたらす悲劇の中心テーマになると思う。本作は、イギリス映画としては、メロドラマ的すぎる。