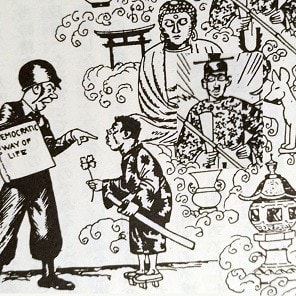けさの朝日新聞に一水会の鈴木邦男の死を悼む中島岳志のインタビュー記事が載っていた。「一水会」とは、美術団体のような名前だが、鈴木邦男が創った右翼団体である。
20年近く前、鈴木邦男は河合塾で大検を目指す高校中退者の講師をしていた。私は、中退した息子をそこに通わせた。息子は彼の暴力的な言動に恐怖を怯え、河合塾に通いたくと訴えていたが、河合塾の講師がそんなことを言って高校中退者を脅すとは私は信じられなかった。私は鈴木邦男という名も聞いたことがなかったからだ。
しかし、完全に引きこもった息子と対話を続けるうちに、本当であると思うようになった。三島由紀夫と森田必勝の自決に共感する鈴木邦男に、私は好感をもてない。自分勝手な理屈で若者に暴力を煽る鈴木邦男を危険な男だと思う。
そういう鈴木邦男を悼む中島岳志も、怪しい男だと思う。その中島岳志を「リベラル保守」の政治学者と紹介する朝日新聞の真田香菜子も、頭がおかしくなっていないか、私は心配である。日米安保反対、格差社会反対であれば、右翼の鈴木邦男が左翼に近づいたと言えるのか、とても、安易である。もともと中島は、国家あるいはその象徴たる天皇のもとの平等を唱えている男である。個人というものがぶっ飛んでいる。
左翼とは、人間に序列をつけることに反対する考え方である。個人を抑圧するあらゆる権力に反対するのが左翼である。エンゲルスが言うように、国家は廃止すべきものと考えるのが左翼である。左翼にいろいろな集団があるのは、国家廃止の道筋に、考え方の違いがあるからである。
ここでは、6年前、『愛国と信仰の構造 全体主義はよみがえるのか』(集英社新書)を読んだときの私の感想(Yahooブログ)を再録し、中島岳志への批判としたい、
☆ ☆ ☆ ☆
愛国と信仰の構造 全体主義はよみがえるのか(2016/9/22(木) )
6ヵ月前に予約した本がようやく図書館から届いた。中島岳志と島薗進との対談、『愛国と信仰の構造 全体主義はよみがえるのか』(集英社新書)である。
待ちくたびれたのもあるが、つまらない本であった。対談が深まらないのである。対談とは、二つの異なる精神が接触し、化学反応を起こすのが面白いのである。
島薗進は1948年生まれ、私の1年下で、東大闘争を体験した世代である。中島岳志は1975年生まれ、東大闘争が終わってから生まれた、すなわち、新左翼を知らない世代である。二つの世代が接触したとき、何かが起きるべきだった。
本の表題に「信仰」があるが、二人とも、政治的で宗教的ではない。中島岳志は、自分だけが知っているかのように、右翼思想を自慢げに語る。それを島薗進がやさしく諭す。中島岳志が訂正するでも反論するでもなく、話が転じていく。
島薗進は、6年前の『国家神道と日本人』(岩波新書)で、明治政府の儒学者によって「国家神道」が作られて行く様を実証的に書いた。これは読みごたえがあった。
儒学は、中国の戦国時代に生まれた、国を統治する技術である。『論語』などは簡潔に書かれているので愛読者が意外と多く、学校での漢文の教材に必ず取り上げられる。儒学は、人間の特質を理解し利用すれば、人民を統治できる、と言っている。具体的には「礼」と「儀」である。
「礼」は、上下の秩序を国家から家庭までの貫き、「忠」や「孝」によって人間の心まで支配することである。明治政府が「礼」を意識的に利用したことは、丸山眞男が繰り返し述べている。
島薗進が見出した視点は「儀」である。明治政府は天皇制を「国家儀礼」とすることで、外来のキリスト教と両立するものかのように装い、一方で天皇を神格化した。天皇制があるということは、戦前の非理性的社会体制が続いていることだ、と島薗進はみなす。「象徴天皇制」になっても天皇が「国家儀礼」の頂点にあることには変わらない。
対談では、島薗進が色々と教えるにもかかわらず、中島岳志は「国民国家」、「一君万民」、「他力本願」をまくしたてる。
私の世代は、戦前の右翼思想を知らないのではなく、支持しないだけである。戦前の右翼思想は、明治政府が「礼」と「儀」による教育を徹底したために生まれた妄想である。
私の世代は、戦後の民主主義教育が文部省の力に抑え込まれ教育界が右傾化していく様を目撃した。中島岳志の世代は完成した右傾化教育の中で育った。当然、愛国主義が復活するだろう。これは不幸なことである。