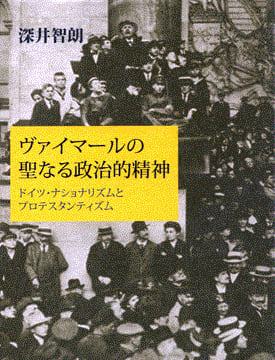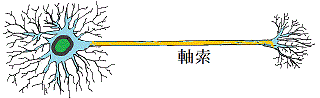私が子供のとき、奴隷は、首に かせがあり、足に 鎖があるもの、と思っていた。子供のとき見た映画『ベン・ハー』では、チャールトン・ヘストンがガレー船に鎖でつながれ、オールでこいでいた。
しかし、大人になって気づいたのは、働くには、首かせや足かせは邪魔なのである。寝るときも邪魔である。だから、奴隷は、普段は、首かせ足かせをしていない。首かせや足かせは、逃亡の恐れがあるときのみに、つけられたようである。
新約聖書を読んでいると、「奴隷」と「しもべ」の区別がつきにくい。もともと、ギリシア語の名詞δοῦλος(ドゥウロス)は「奴隷」を意味するが、日本語聖書では「しもべ」と訳し、動詞δουλεύωは「仕える」と訳している。イエスの時代は、奴隷も、しもべも、自分の意志で主人を選べるか否かを除き、生活の実態は大差がなかったのだろう。
旧約聖書を読んでいると、エジプトの奴隷の生活から脱出して、荒れ野をさまよう40年間に、神がモーセに、イスラエル人か否かで使用奴隷を差別するように指示している。荒れ野をさまよう逃亡奴隷に、使用する奴隷がいたとは考えにくい。モーセの五書は後の時代に祭司によって書かれたからだろう。
さらに、昔にさかのぼると、古代メソポタミアの社会では、借金が返せないと奴隷にされ、誰かが所有者にお金を払うと奴隷から解放された。穀物のタネを借り受け、収穫のとき、返すという制度であったから、天候不順がつづくと、借金が返せなくなる。だから、誰でも奴隷になる可能性があったわけである。
岩田靖夫の『ギリシア哲学入門』(ちくま新書)によると、古代ギリシアでは、プラトンが「自己支配力、自己統制力の欠如した人間」を奴隷とみなしていた。奴隷の反対は「市民」、「自由人」となる。アリストテレスは「判決と支配に関与する」者を「市民」と考えていた。古代メソポタミアでも古代ギリシアでも、「市民」には兵役の義務があったが、アリストテレスが「市民」の条件に「防衛に関与」をあげていないのが興味深い。軍人を職業とし、「市民」か否かと無関係のものとしたのだろう。
振り返って、現代の日本人を考えるとき、彼らは自由意志を持っているのだろうか。政治に参加しているのだろうか。彼らは「自由人」なのか、「しもべ」なのか、「奴隷なの」か。首かせ、足かせがなくとも、奴隷だと思っていなくとも、自由意志をもたず、政治に参加せず、自己決定をしなければ、現代の「奴隷」にすぎない。