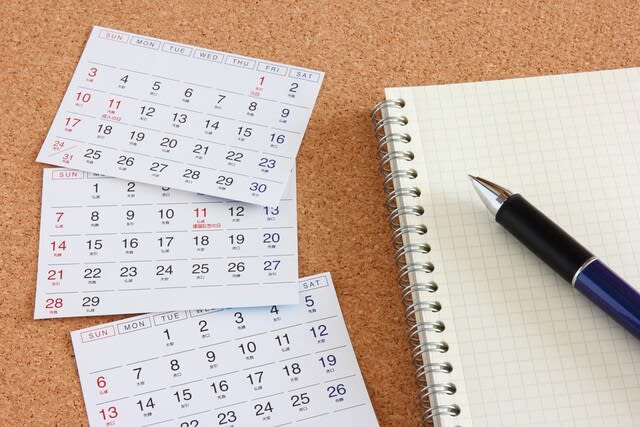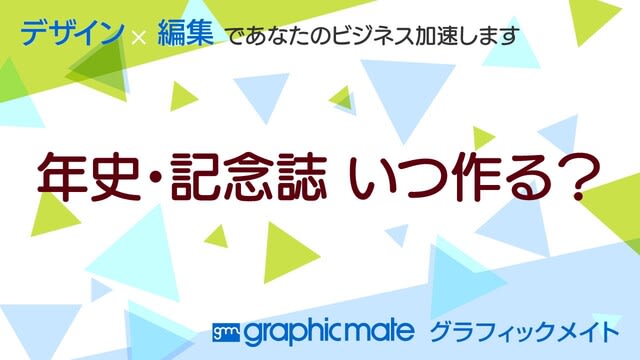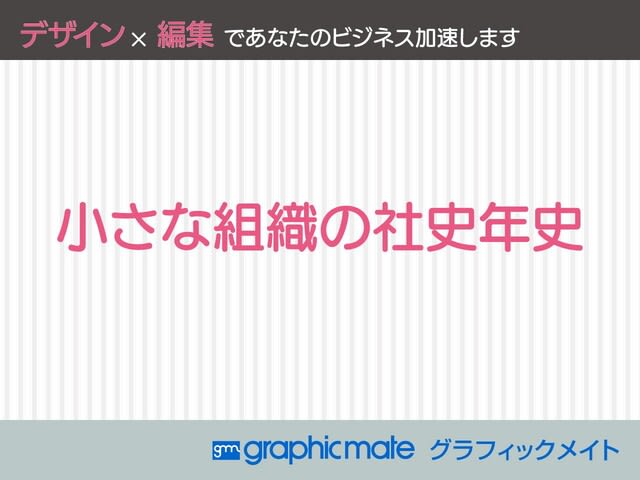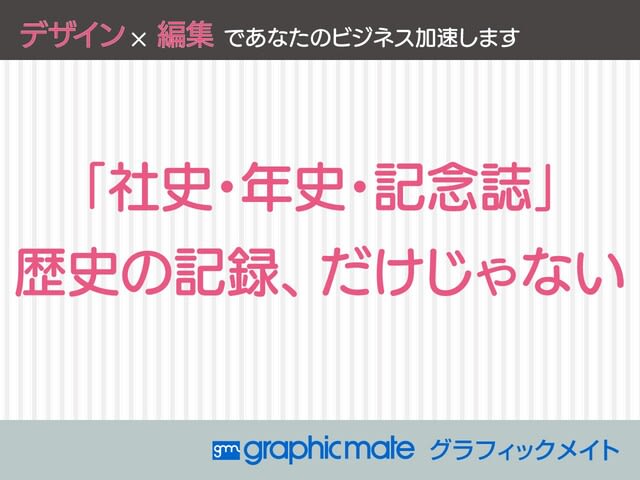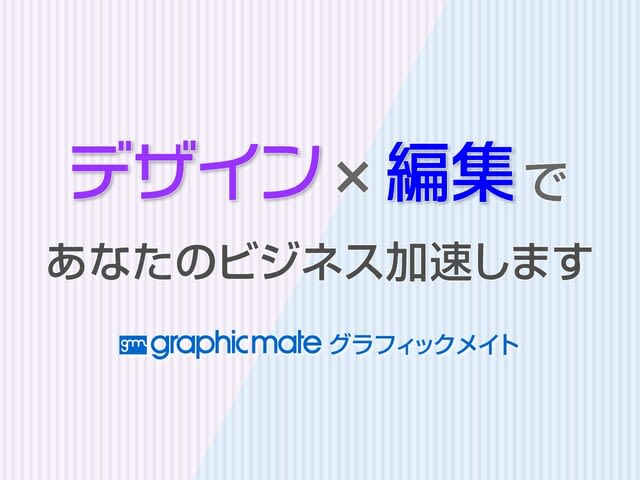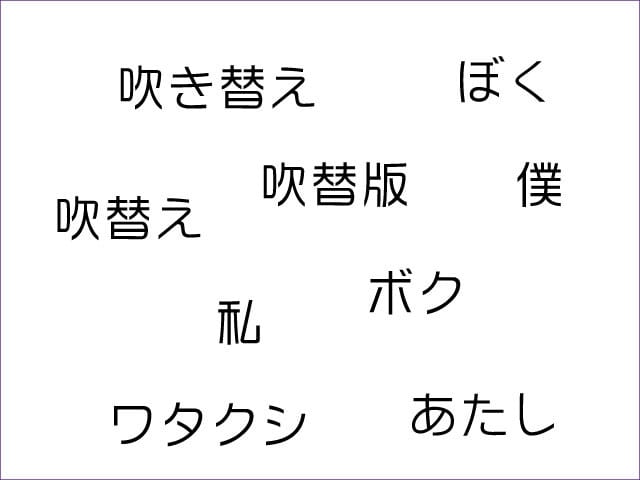東京港区の編集もできるデザイン会社 グラフィックメイトの大里早苗です。
グラフィックメイトは年史、記念誌の制作を手がけて54年。さまざまなタイプの年史、記念誌を制作してきました。年史・記念誌の制作でまず考えなければならないのが「期間」と「予算」です。
期間を決める条件には、次のようなものがあります。
とは言え一般的に大きく影響するのが、年史を配布する記念式典などの日程が決まっている場合です。動かせない締切に向かって、上記の条件をクリアしていく必要があります。
締切がまだ決まっていなくても、できるだけ早い始動を。締切が決まってしまっているなら、一刻も早い始動が必要です。
次に予算です。予算によって、制作できる社史・年史の仕様、部数が決まってきます。
制作工程は次のようなものがありますが、そのうちどこまでを自分たちで行うのか、どこまでを依頼するのかによって費用は大きく変わってきます。
ページ数や、どんな仕上がりの型にするか。判型と言われるサイズの選択や、どのような用紙を使用するかという点も予算に影響してきます。
いくつもの要素が複雑に絡みあっていますので、編集・デザイン会社や印刷会社に見積り依頼をされることをお勧めします。
♢ー♢ー♢ー♢ー♢ー♢ー♢ー♢ー♢ー♢ー♢
グラフィックメイトでは社史・年史・記念誌制作についてのご相談を受け付けています。
オンライン相談は初回無料(1時間程度)/メール相談無料。
まずはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
●こんなこともご相談にのります。
社史年史ってそもそもどうやって進めれば良いかわからない
○周年までに制作したいけれど、間に合う?
社員みんなで作る方法はある?
社員はあまり関われないけどどこまでやってもらえる?
社史年史の有効な使い方は?
他社さんの見積額や進行について適切か知りたい
最後までお読みいただきありがとうございました。いいねやフォローをしていただけると嬉しいです。
【関連記事】
グラフィックメイトブログの中の 年史制作 に関する記事一覧
グラフィックメイトブログの中の 記念誌 に関する記事一覧

good life ☆ good design ☆ graphicmate
https://www.gmate.jp/ Tel 03-3401-7310
グラフィックメイトは年史、記念誌の制作を手がけて54年。さまざまなタイプの年史、記念誌を制作してきました。年史・記念誌の制作でまず考えなければならないのが「期間」と「予算」です。
期間を決める条件には、次のようなものがあります。
・創業からの年数は?
・初めての年史制作か、2回目以降か?
・何年分をまとめるのか?
・総ページ数は?
・資料は整理されているか?
・初めての年史制作か、2回目以降か?
・何年分をまとめるのか?
・総ページ数は?
・資料は整理されているか?
とは言え一般的に大きく影響するのが、年史を配布する記念式典などの日程が決まっている場合です。動かせない締切に向かって、上記の条件をクリアしていく必要があります。
締切がまだ決まっていなくても、できるだけ早い始動を。締切が決まってしまっているなら、一刻も早い始動が必要です。
次に予算です。予算によって、制作できる社史・年史の仕様、部数が決まってきます。
制作工程は次のようなものがありますが、そのうちどこまでを自分たちで行うのか、どこまでを依頼するのかによって費用は大きく変わってきます。
編集、取材、原稿作成、撮影、表・グラフ・年表の作成、
誌面のデザイン・レイアウト、校正、進行管理、印刷、製本
誌面のデザイン・レイアウト、校正、進行管理、印刷、製本
ページ数や、どんな仕上がりの型にするか。判型と言われるサイズの選択や、どのような用紙を使用するかという点も予算に影響してきます。
いくつもの要素が複雑に絡みあっていますので、編集・デザイン会社や印刷会社に見積り依頼をされることをお勧めします。
♢ー♢ー♢ー♢ー♢ー♢ー♢ー♢ー♢ー♢ー♢
グラフィックメイトでは社史・年史・記念誌制作についてのご相談を受け付けています。
オンライン相談は初回無料(1時間程度)/メール相談無料。
まずはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
●こんなこともご相談にのります。
社史年史ってそもそもどうやって進めれば良いかわからない
○周年までに制作したいけれど、間に合う?
社員みんなで作る方法はある?
社員はあまり関われないけどどこまでやってもらえる?
社史年史の有効な使い方は?
他社さんの見積額や進行について適切か知りたい
最後までお読みいただきありがとうございました。いいねやフォローをしていただけると嬉しいです。
【関連記事】
グラフィックメイトブログの中の 年史制作 に関する記事一覧
グラフィックメイトブログの中の 記念誌 に関する記事一覧

good life ☆ good design ☆ graphicmate
https://www.gmate.jp/ Tel 03-3401-7310