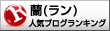あれから 6年。
普通の剣龍は一般的な縞物が覆輪に変わるように伯青龍が深覆輪になったものですが
美雪剣龍は三光中斑に変化したものです。
御城覆輪のような剣龍と聞かされても見た目はどこが
 といったところで色めき立つ人はたぶん滅多にいませんが
といったところで色めき立つ人はたぶん滅多にいませんがそのような感じの変化種です。

一昨年の猛暑でだいぶ下葉を落としがっくりと肩まで落としていたのですが

上の木はさすが古木ということで持ち堪えていました。


忘れた頃に仔が出たものの今回は派手柄でした。




こちらは下葉を落とした口の方。



しかし下葉を毟ったのと同じ効果かずいぶん仔が出てくれました。

明治15年の銘鑑に剣龍の前身である美雪覆輪の名を見かけますが
世に出てからこんな株になったのは初めてかもしれません。


さすが三光中斑芸の面目躍如といったところです。


こちらは小さく出来た木を寄せ植えしてみました。


よく増えますし

ここからでも作上がりする安心感もあり
愛らしさに溜息がこぼれます。

本来、剣龍という品種は名刀のような近寄り難い秘めた魅力を持っていますが
実際すぐ枯れるという特質が近寄り難くさせています。

それが姿はそのままにブレークスルーといえるほど中身が変化していて
それなりに丈夫でそれなりに増えるとなれば価値観はコペ転しますので
これは楽しまない手はないとしたものです。




あれから10か月。
某鉢作家さんから預かりの木です。
普通の豆葉な姿をしているのに花も咲かず仔も吹かず
長い間淡々と過ごしているのは不思議な気がします。
何か黄金虫的な性質があるのかもしれませんね。
とはいっても昨年以降新根が出揃ってくれて元気が出てきましたので
そろそろ何か動きがあっても良さそうです。


と思ったら撮影中、サクラさんが邪魔しに来ました。
こっちの動きじゃないっちゅうに。




あれから 10か月。
某鉢作家さんからの預かり品です。
人のだから枯れても惜しくないのでお気楽に・・・とはいかず

好待遇で育てています。

結果、新たに3本も仔が出てきてくれました。



前からの大仔は相変わらず派手なままですが


新たな仔は何となくいけそうな気がしています。


花芽予定位置からまで仔が出ています。
この元気さは根が良く出来たからなのでしょう。
大株立ちにして返却したいものです。



あれから 半年。
大株を目指せるわけもなくやっぱり株分けしちゃいますよね~。


でも、付けてある仔に勢いは付いてきましたし

刺激になったのか新たな仔も誕生しました。




そして分けた方の仔はというと


新たにアタリが二つ動き出しました。

秋には3本立ちになっていることでしょう。
うむうむ、この品種は割るほどにそれが刺激となって増えていくようですね。




あれから 1年。
葉繰りは年2枚でした。
一昨年は途中の葉が枯れ落ちて寂しかったのですがそれも目立たなくなっています。

深覆輪の柄を見ると弱そうに見えますが毎年根がたくさん出て元気いっぱいです。



下の大仔からは早くも仔が2本。
でも、若木の間はこんなものでしょう。
古木になれば親木も仔も柄は安定するようです。

一番上の仔も派手に出てだんだん紺が乗るという
よく見る解説文に合致しています。



こちらの木は若木の割にはユウレイ仔を生まずなかなかの健闘ぶりです。

元親は昔ユウレイ仔をちぎっては捨てちぎっては捨てしていましたから
それを思えばこちらはかなり優秀なのかもしれません。







あれから 3年と9か月。
名付けのセンスが皆無でそのまんまの青光墨黄縞と呼んでいましたが
蘭国さんが素敵な名前を考えてくださいました。

黄煌墨(きこうぼく・kikouboku)。
語呂はそのままで黄縞が煌めき墨を流すといった感じです。






そういえば今年は全国大会でひな壇に上がりましたので新登録の資格は十分。
登録待ちの縞や覆輪は沢山あるものの決め手に欠けるものがほとんどの中
これはベテラン以上なら慣れ親しんだ青光墨が台になっています。
黄縞に変わっただけですからどなたが見ても品種の判別は容易でしょう。
もし登録できるとしたら従来品種からの色変わりは白翁以来かも。
早速、3鉢揃えなきゃと棚を眺めましたが良柄の木が残り少ないことに気が付きました。




あとはこんな半柄くらいしかありませんでした。
展示した最上柄の木は交換会でサヨナラしましたし何をやってるのか。

新登録はしばらくお預けかも。

羆E
2025年05月18日 | 羆



今月初め、ご縁があって入手しました。

柄の冴え、紺覆輪の具合がちょうど良く
木姿も締まって好ましく
更に下から上まで花芽跡が見当たらず超楽しみ。

つい、肥料を効かせたらポンポン仔が出そうとか考えてしまいますが
早速、継ぎ根が肥料焼けっぽくなっていますので
失敗の轍を踏まないよう慎重に行きたいと思っています。

早々儲かる品種でもないのに手放す人は滅多にいませんので
機会があればと思っていましたがようやく購買意欲は落ち着いた感じです。

羆D
2025年05月17日 | 羆



あれから 半年。
やや小ぶりな木ですが春先から葉半枚近くは成長していますから意外と勢いはありそう。

天葉もその下の派手気味の葉から一転、
きっちりと紺覆輪が回っていますからまずは一安心です。

花芽跡が全く見当たりませんので
木勢さえ付けば楽しいことが起こりそう。

羆C
2025年05月16日 | 羆




あれから 半年。
何やら紺覆輪が崩れ気味で進展が気になります。


それはともかく、下から仔が動き出しました。



まだ肉眼ではわからないものの画像では背筋が白く見えます。
これは当たりを引いたかも~

羆B
2025年05月15日 | 羆



あれから 半年。
もう少し締まった姿の方が良いのでしょうが
これはこれで伸び伸びと育っていますし
堂々とした姿はありなのかもしれません。
それにしても空き家が一つ二つあったはずですがなかなか反応してくれません。
今年は昨年落とした下葉3枚の挽回と仔出しが目標でしょう。

ところで富貴蘭の芸は万に一つとか10万に一つの確率で世に出る貴重さですが
栽培の歴史が数百年と長い富貴蘭ですから
そんな確率の芸でも品種的には割とざらにあったりします。
しかし羆の場合その芸は万に一つが3回か4回ぐらい重ね掛けされているように思えるのです。
そうなると出現率は兆か京に一つという感じで世に出ることはあり得ないのですが
今から138年前、明治20年に1回だけ出てくれたんですね。
そして運良くその芸の貴重さを理解し栽培上手な方に見いだされたおかげで
徐々に増やされ今に伝わったわけです。
とはいえ昭和52年発行の誠文堂新光社刊、古典園芸植物という本で
解説の工藤哲生氏によると、当時本芸品は5鉢ぐらいとありますから
結構ぎりぎりだったのかもしれません。
それから50年で10倍近くまで増えたということになりますが
この芸の魅力が例えば海外にばれてしまえば
あっという間に日本から姿を消してしまいそうではあります。
実生ばやりの今を含めてここ数百年で羆と同等以上の芸は一度も出ていませんから
多分これからも羆の魅力を凌駕する木が出ることはないでしょう。
なるべく国内で大切に保存していきたいものです。
羆A
2025年05月14日 | 羆



あれから 半年。
成長期を迎え羆も艶めいてきました。

昨年、蘭舎の屋根のポリカを交換したのですが
日差しの加減がちょうど良かったらしくて
紺地濃く柄との対比がすんばらしく出来ています。





特に仔の柄が綺麗。

これでも1度痛めてから復活したため葉数の割に根は沢山あり
今年は生育に勢いが付いてくれそう。
羆一枠10鉢育てよう計画に一役買ってくれそうです。

超ご無沙汰でした。
全国大会も終わり、帰ってきて水遣りをしてちょっとのんびりしています。
こちらは寒い4月というか昨日まで寒かったのですが
今日からようやく初夏らしい気候が続きそうです。

全国大会も終わり、帰ってきて水遣りをしてちょっとのんびりしています。
こちらは寒い4月というか昨日まで寒かったのですが
今日からようやく初夏らしい気候が続きそうです。





さて、建国殿はあれから 半年。
親木は昨年の戸外栽培のせいか葉癖が付いてしまいましたが



仔の方は極めて順調のようです。



まだ柄までは不明だったアタリはどちらもしっかりとした中透け芸です。

さすがはいまだに10割を維持するだけのことはあります。


そんな欲目で見ればこちらの仔も脈はありそう。
しばらく古木の素立ち状態が続いたものの
ここに来て大爆発しそうな気がします。