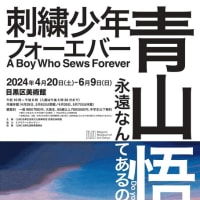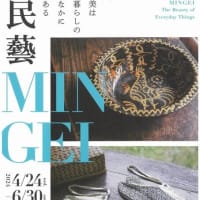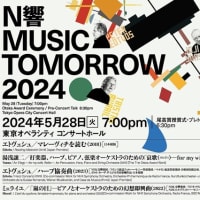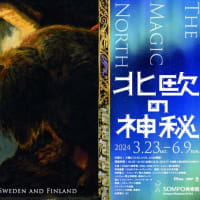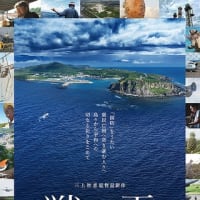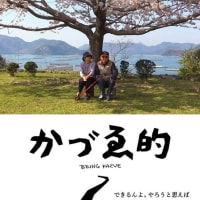宮本輝の「川三部作」の第2部「螢川」は、時は1962年(昭和37年)、所は富山の常願寺川の支流「いたち川」の河畔、主人公は中学2年生(作中で中学3年生になる。年齢は14~15歳)の水島竜夫。第1部の「泥の河」とは別の話だが、時と年齢は「泥の河」から7年たったことを示す。結果、「泥の河」は小学2年生の目で見た世界だが、「螢川」は大人の世界を垣間見た中学2~3年生の世界になる。
両者のちがいは作品の構成に表れる。「泥の河」では時間が直線的に進む。作中の時間はつねに現在だ。一方、「螢川」では頻繁に過去が回想される。現在は過去の積み重ねのうえにある。言い換えるなら、「螢川」では時間は現在と過去のあいだをジグザグに進む。両者のその構成のちがいは小学2年生と中学2~3年生の時間感覚のちがいを反映するのだろう。
過去の回想場面では主に竜夫の父と母との出会いと結婚が語られる。一言でいうと、二人ともわけありだ。それでも結婚に踏みきり、竜夫を生む。二人はそのことで負い目を負う。竜夫がそのいきさつを知っているわけではないが、竜夫を取り巻く世界として二人の過去が語られる。それが作品に奥行きを生む。
竜夫は同級生の英子に恋をする。「泥の河」でも信雄は喜一の姉に、いや、それ以上に喜一の母に惹かれる。だが、小学2年生の信雄はそれを意識しない。一方、竜夫は明確に意識する。性的な関心もある。中学3年生なので当然だろうが、竜夫よりも英子のほうが心身ともに成熟している。それも重要な要素として描かれる。
一種の象徴的な存在として(それがなにの象徴かは、読者の解釈にゆだねられる)、「泥の河」に登場する巨大な鯉と同様に、「螢川」では螢の大群が登場する。竜夫と英子をふくめた4人で螢の大群を見に行く(その場面がこの作品のクライマックスだ)。「何万何十万もの螢火が、川のふちで静かにうねっていた。そしてそれは、四人がそれぞれの心に描いていた華麗なおとぎ絵ではなかったのである。/螢の大群は、滝壺の底に寂寞と舞う微生物の屍のように、はかりしれない沈黙と死臭を孕んで光の澱と化し、(以下略)」と描写される。
これは異様な描写だ。メルヘンだと思って螢の大群を見に行ったら、それはメルヘンではなく、「沈黙と死臭」を孕む「光の澱」だったという不気味さは、子どもから大人への通過儀礼のようなものだろう。一方、「泥の河」の巨大な鯉は、人生の脅威の暗示だったかもしれないが、少なくとも信雄の目には、自然の驚異を超えない。
螢の大群は「泥の河」の巨大な鯉よりも、むしろ喜一の存在に近いかもしれない。喜一は見知らぬ少年として信雄の前に現れ、二人は親しくなるが、やがて信雄は喜一の異常な面に気づく。その経過は「螢川」の螢の大群の先駆のようだ。
両者のちがいは作品の構成に表れる。「泥の河」では時間が直線的に進む。作中の時間はつねに現在だ。一方、「螢川」では頻繁に過去が回想される。現在は過去の積み重ねのうえにある。言い換えるなら、「螢川」では時間は現在と過去のあいだをジグザグに進む。両者のその構成のちがいは小学2年生と中学2~3年生の時間感覚のちがいを反映するのだろう。
過去の回想場面では主に竜夫の父と母との出会いと結婚が語られる。一言でいうと、二人ともわけありだ。それでも結婚に踏みきり、竜夫を生む。二人はそのことで負い目を負う。竜夫がそのいきさつを知っているわけではないが、竜夫を取り巻く世界として二人の過去が語られる。それが作品に奥行きを生む。
竜夫は同級生の英子に恋をする。「泥の河」でも信雄は喜一の姉に、いや、それ以上に喜一の母に惹かれる。だが、小学2年生の信雄はそれを意識しない。一方、竜夫は明確に意識する。性的な関心もある。中学3年生なので当然だろうが、竜夫よりも英子のほうが心身ともに成熟している。それも重要な要素として描かれる。
一種の象徴的な存在として(それがなにの象徴かは、読者の解釈にゆだねられる)、「泥の河」に登場する巨大な鯉と同様に、「螢川」では螢の大群が登場する。竜夫と英子をふくめた4人で螢の大群を見に行く(その場面がこの作品のクライマックスだ)。「何万何十万もの螢火が、川のふちで静かにうねっていた。そしてそれは、四人がそれぞれの心に描いていた華麗なおとぎ絵ではなかったのである。/螢の大群は、滝壺の底に寂寞と舞う微生物の屍のように、はかりしれない沈黙と死臭を孕んで光の澱と化し、(以下略)」と描写される。
これは異様な描写だ。メルヘンだと思って螢の大群を見に行ったら、それはメルヘンではなく、「沈黙と死臭」を孕む「光の澱」だったという不気味さは、子どもから大人への通過儀礼のようなものだろう。一方、「泥の河」の巨大な鯉は、人生の脅威の暗示だったかもしれないが、少なくとも信雄の目には、自然の驚異を超えない。
螢の大群は「泥の河」の巨大な鯉よりも、むしろ喜一の存在に近いかもしれない。喜一は見知らぬ少年として信雄の前に現れ、二人は親しくなるが、やがて信雄は喜一の異常な面に気づく。その経過は「螢川」の螢の大群の先駆のようだ。