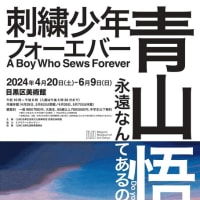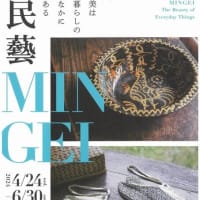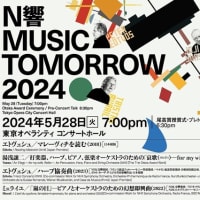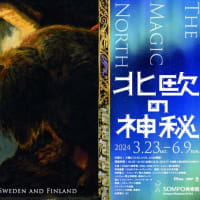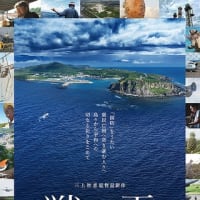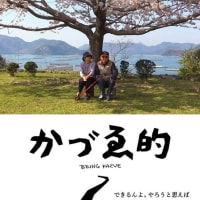東京都美術館で「デ・キリコ展」が開かれている。ジョルジョ・デ・キリコ(1888‐1978)の生涯にわたる作風の変遷をたどる展覧会だ。
デ・キリコの作品は「形而上絵画」といわれる。形而上絵画が生まれたのは1910年代だ。時あたかも第一次世界大戦の真最中。形而上絵画は戦争が生んだ不安の表現のひとつだったろう。だが、デ・キリコの難しい点は、そのような作風が第一次世界大戦の終結後も、折に触れて繰り返されたことだ。後年生まれたそれらの作品(新形而上絵画といわれる)をどう捉えるかは、人それぞれだ。
本展には「大きな塔」(1915?)という作品が展示されている(残念ながら本展のHPには画像が載っていない)。81.5×36㎝の縦長の作品だ。画面いっぱいに5層の塔が描かれる。塔は暗赤色だ。各層ごとに何本ものベージュ色の円柱が並ぶ。空は不気味な暗緑色だ。画面左側に建物の一部が覗く。人の気配はない。
同じ塔を描いた「塔」(1974)という作品が展示されている。デ・キリコの最晩年の作品だ。「塔」は「大きな塔」とほぼ同じサイズだ。だが「塔」の場合は4層で、各層は下から順に赤、青、赤、青とカラフルに彩られている。空は明るい。左側の建物は消えている。全体的にあっけらかんとした作品だ。思わず拍子抜けする。この作品を肯定的に捉えるのか、それとも否定的に捉えるのか。
本展に展示されている1910年代のデ・キリコの作品の中には、傑作と思われる作品がある。たとえば不穏な雰囲気を漂わせる「預言者」(1914‐15)とか、危ういバランスの上に成り立つ「福音書的な静物Ⅰ」(1916)とかだ(本展のHP(↓)に画像が載っている)。それらの作品と後年の作品とは何がちがうのか。
突拍子もない比較だが、デ・キリコの生涯は作曲家のストラヴィンスキー(1882‐1971)の生涯とほぼ重なる。ストラヴィンスキーは第一次世界大戦(そしてロシア革命)の前夜に「火の鳥」、「ペトルーシュカ」、「春の祭典」の三大バレエを書いた。1920年代に入ると作風をガラッと変えた(新古典主義といわれる)。だが第二次世界大戦後になって、「火の鳥」と「ペトルーシュカ」を透明感のあるオーケストレーションに編曲した。ストラヴィンスキーの場合とデ・キリコの場合とは本質的に異なるのか。それとも共通点があるのか。
デ・キリコが最晩年に描いた「オデュッセウスの帰還」(1968)や「燃えつきた太陽のある形而上的室内」(1971)は、子どものいたずらの絵のように見える(画像は本展のHP↓)。画像で見るとピンとこないが、実物を見ると、なぜかホッとする。
(2024.5.31.東京都美術館)
(※)本展のHP
デ・キリコの作品は「形而上絵画」といわれる。形而上絵画が生まれたのは1910年代だ。時あたかも第一次世界大戦の真最中。形而上絵画は戦争が生んだ不安の表現のひとつだったろう。だが、デ・キリコの難しい点は、そのような作風が第一次世界大戦の終結後も、折に触れて繰り返されたことだ。後年生まれたそれらの作品(新形而上絵画といわれる)をどう捉えるかは、人それぞれだ。
本展には「大きな塔」(1915?)という作品が展示されている(残念ながら本展のHPには画像が載っていない)。81.5×36㎝の縦長の作品だ。画面いっぱいに5層の塔が描かれる。塔は暗赤色だ。各層ごとに何本ものベージュ色の円柱が並ぶ。空は不気味な暗緑色だ。画面左側に建物の一部が覗く。人の気配はない。
同じ塔を描いた「塔」(1974)という作品が展示されている。デ・キリコの最晩年の作品だ。「塔」は「大きな塔」とほぼ同じサイズだ。だが「塔」の場合は4層で、各層は下から順に赤、青、赤、青とカラフルに彩られている。空は明るい。左側の建物は消えている。全体的にあっけらかんとした作品だ。思わず拍子抜けする。この作品を肯定的に捉えるのか、それとも否定的に捉えるのか。
本展に展示されている1910年代のデ・キリコの作品の中には、傑作と思われる作品がある。たとえば不穏な雰囲気を漂わせる「預言者」(1914‐15)とか、危ういバランスの上に成り立つ「福音書的な静物Ⅰ」(1916)とかだ(本展のHP(↓)に画像が載っている)。それらの作品と後年の作品とは何がちがうのか。
突拍子もない比較だが、デ・キリコの生涯は作曲家のストラヴィンスキー(1882‐1971)の生涯とほぼ重なる。ストラヴィンスキーは第一次世界大戦(そしてロシア革命)の前夜に「火の鳥」、「ペトルーシュカ」、「春の祭典」の三大バレエを書いた。1920年代に入ると作風をガラッと変えた(新古典主義といわれる)。だが第二次世界大戦後になって、「火の鳥」と「ペトルーシュカ」を透明感のあるオーケストレーションに編曲した。ストラヴィンスキーの場合とデ・キリコの場合とは本質的に異なるのか。それとも共通点があるのか。
デ・キリコが最晩年に描いた「オデュッセウスの帰還」(1968)や「燃えつきた太陽のある形而上的室内」(1971)は、子どものいたずらの絵のように見える(画像は本展のHP↓)。画像で見るとピンとこないが、実物を見ると、なぜかホッとする。
(2024.5.31.東京都美術館)
(※)本展のHP