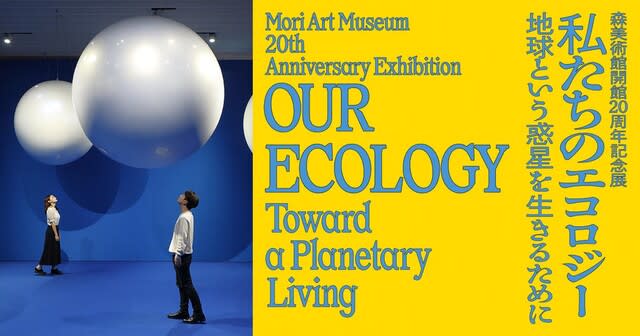原田慶太楼指揮東響の定期演奏会。1曲目は藤倉大の「Wavering World」。シアトル交響楽団からの依頼で「シベリウスの交響曲第7番と共演できる作品」(藤倉大自身のプログラムノート)として作曲された。透明感のある弦楽器の音が飛び交う曲だ。その音は銀色に輝くように感じられる。藤倉大の鮮度のよい音の典型だ。弦楽器の音が交錯する中で木管楽器がうごめき、金管楽器が咆哮する。シベリウス的だ。
途中からティンパニの強打が始まる。それがずっと続く。ほとんどソロ楽器のようだ。本作品は天地創造のイメージから発しているらしいが(上記のプログアムノートより。ただし天地創造はキリスト教の創世記からではなく、フィンランド神話、日本神話などからインスピレーションを得た藤倉大独自のもの)、ティンパニ・ソロは天地創造の登場人物を表すというよりは、音楽的な必然性から生まれたと解したい。だがわたしにはそれがいまひとつ掴めなかった。
だが(再度「だが」と言うが)2曲目のシベリウスの交響曲第7番になると、冒頭のティンパニの一撃が「Wavering World」のティンパニ・ソロにつながり、以降、曲全体にわたり、わたしはティンパニの動きに耳を傾けることになった。それは小さな体験かもしれないが、驚くべき体験でもあった。
シベリウスの交響曲第7番の演奏は、目が覚めるようにダイナミックで、色彩感にあふれていた。わたしは渡邉暁雄さんの指揮でこの曲が刷り込まれているが、しっとりして、あまり山谷がない渡邉暁雄さんの演奏とは真逆の演奏だ。シベリウスの奥の院的な作品ではなく、旺盛な意欲があふれる作品に聴こえた。たしかに第7番はシベリウスの最後の交響曲になったが、シベリウスは第8番を作曲しようと四苦八苦していた。第7番でやめる気はさらさらなかった。
以上の「Wavering World」からシベリウスの第7番への流れは、たいへん説得力があった。言い換えれば、「Wavering World」のおかげでシベリウスの第7番を新鮮に聴くことができた。原田慶太楼の弾むようなリズム感と躍動感も大きな役割を果たした。
3曲目はラフマニノフのピアノ協奏曲第2番。ピアノ独奏はオルガ・カーン。第1楽章はピアノとオーケストラの呼吸が合わなかった。第3楽章はテンポを大きく動かして、それは面白かったが、ピアノがバリバリ弾くところで音が濁った。アンコールにプロコフィエフの「4つの練習曲」から第4番が演奏された。大向こう受けする演奏だったが、雑だった。最後にオーケストラも入りラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の最後の部分がもう一度演奏された。オーケストラはこのときの方がのびのびしていた。
(2024.3.30.サントリーホール)
途中からティンパニの強打が始まる。それがずっと続く。ほとんどソロ楽器のようだ。本作品は天地創造のイメージから発しているらしいが(上記のプログアムノートより。ただし天地創造はキリスト教の創世記からではなく、フィンランド神話、日本神話などからインスピレーションを得た藤倉大独自のもの)、ティンパニ・ソロは天地創造の登場人物を表すというよりは、音楽的な必然性から生まれたと解したい。だがわたしにはそれがいまひとつ掴めなかった。
だが(再度「だが」と言うが)2曲目のシベリウスの交響曲第7番になると、冒頭のティンパニの一撃が「Wavering World」のティンパニ・ソロにつながり、以降、曲全体にわたり、わたしはティンパニの動きに耳を傾けることになった。それは小さな体験かもしれないが、驚くべき体験でもあった。
シベリウスの交響曲第7番の演奏は、目が覚めるようにダイナミックで、色彩感にあふれていた。わたしは渡邉暁雄さんの指揮でこの曲が刷り込まれているが、しっとりして、あまり山谷がない渡邉暁雄さんの演奏とは真逆の演奏だ。シベリウスの奥の院的な作品ではなく、旺盛な意欲があふれる作品に聴こえた。たしかに第7番はシベリウスの最後の交響曲になったが、シベリウスは第8番を作曲しようと四苦八苦していた。第7番でやめる気はさらさらなかった。
以上の「Wavering World」からシベリウスの第7番への流れは、たいへん説得力があった。言い換えれば、「Wavering World」のおかげでシベリウスの第7番を新鮮に聴くことができた。原田慶太楼の弾むようなリズム感と躍動感も大きな役割を果たした。
3曲目はラフマニノフのピアノ協奏曲第2番。ピアノ独奏はオルガ・カーン。第1楽章はピアノとオーケストラの呼吸が合わなかった。第3楽章はテンポを大きく動かして、それは面白かったが、ピアノがバリバリ弾くところで音が濁った。アンコールにプロコフィエフの「4つの練習曲」から第4番が演奏された。大向こう受けする演奏だったが、雑だった。最後にオーケストラも入りラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の最後の部分がもう一度演奏された。オーケストラはこのときの方がのびのびしていた。
(2024.3.30.サントリーホール)