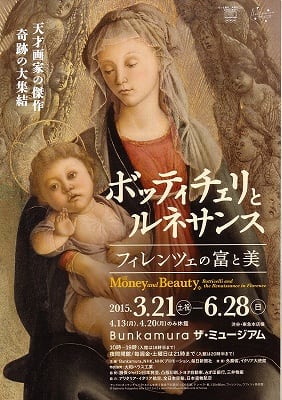4月26日(日)と29日(祝)の2日間、自分のルーツを探して生まれ故郷の周辺を歩いてきました。
生まれ故郷は東京都大田区の多摩川の河口付近。町工場が密集していました。わたしの父は旋盤工でした。先日、高校のときのブラスバンド仲間と飲んでいたら、「お前の家のあたりは臭かった」と言われました。町工場の廃液や油の匂いがしたのでしょう。でも、そんな環境に育ったわたしには、それが当たり前でした。
母は新潟県から嫁いできました。わたしは時々田舎に連れて行ってもらったので、母方の祖父と祖母はよく知っていました。でも、父方の祖父と祖母は、わたしが生まれる前に亡くなっていたので、まったく知らずにいました。写真もありませんでした。今思うと情けない話ですが、名前さえ不確かでした。
それには家庭の事情がありました。でも、それを書いても仕方がないでしょう。ともかく父方のことをあれこれ聴く雰囲気ではなく、父方の祖父や祖母のことは知らずに育ちました。父はもう10年以上前に亡くなっていますので、聴く機会を失いました。
ところが、先日、妻が父の戸籍をもとに祖父の戸籍を取ってみました。そうしたら、いろんなことが分かりました。祖父の生没年月日、住所地、祖母の生没年月日、旧姓、実家、さらに祖父の兄弟姉妹、父の兄弟姉妹、長兄(父は三男です)の子どもたち等々。
なにも知らなかった自分のルーツが、いきなり目の前に広げられたような気がしました。とくにショックだったことは、祖母の実家があった場所が、わたしの生家から歩いてすぐの所だったことです。小さい頃に自転車でよく通った場所です。そんなところに(当時はすでになかったのかもしれませんが)祖母の実家があったとは――。
わたしは、今は目黒区に住んでいます。生まれ故郷に帰ることは稀です。でも、祖父の住所地と祖母の実家があった場所を訪れてみたい――という気持ちが湧いてきました。そこで、冒頭に記したように、生まれ故郷に行ってみました。
祖父の住所地には民家が建て込んでいました。貧しかった当時の風景が目に浮かぶようでした。祖母の実家のあたりは倉庫やスーパーが建ち並ぶ殺風景な一角になっていました。生活臭が感じられませんでした。
父方の祖父と祖母はどんな人だったのか。戸籍を見ると苦労したようですが、どんな人生を送ったのか。会えなかったことが、今では寂しく感じられます。
生まれ故郷は東京都大田区の多摩川の河口付近。町工場が密集していました。わたしの父は旋盤工でした。先日、高校のときのブラスバンド仲間と飲んでいたら、「お前の家のあたりは臭かった」と言われました。町工場の廃液や油の匂いがしたのでしょう。でも、そんな環境に育ったわたしには、それが当たり前でした。
母は新潟県から嫁いできました。わたしは時々田舎に連れて行ってもらったので、母方の祖父と祖母はよく知っていました。でも、父方の祖父と祖母は、わたしが生まれる前に亡くなっていたので、まったく知らずにいました。写真もありませんでした。今思うと情けない話ですが、名前さえ不確かでした。
それには家庭の事情がありました。でも、それを書いても仕方がないでしょう。ともかく父方のことをあれこれ聴く雰囲気ではなく、父方の祖父や祖母のことは知らずに育ちました。父はもう10年以上前に亡くなっていますので、聴く機会を失いました。
ところが、先日、妻が父の戸籍をもとに祖父の戸籍を取ってみました。そうしたら、いろんなことが分かりました。祖父の生没年月日、住所地、祖母の生没年月日、旧姓、実家、さらに祖父の兄弟姉妹、父の兄弟姉妹、長兄(父は三男です)の子どもたち等々。
なにも知らなかった自分のルーツが、いきなり目の前に広げられたような気がしました。とくにショックだったことは、祖母の実家があった場所が、わたしの生家から歩いてすぐの所だったことです。小さい頃に自転車でよく通った場所です。そんなところに(当時はすでになかったのかもしれませんが)祖母の実家があったとは――。
わたしは、今は目黒区に住んでいます。生まれ故郷に帰ることは稀です。でも、祖父の住所地と祖母の実家があった場所を訪れてみたい――という気持ちが湧いてきました。そこで、冒頭に記したように、生まれ故郷に行ってみました。
祖父の住所地には民家が建て込んでいました。貧しかった当時の風景が目に浮かぶようでした。祖母の実家のあたりは倉庫やスーパーが建ち並ぶ殺風景な一角になっていました。生活臭が感じられませんでした。
父方の祖父と祖母はどんな人だったのか。戸籍を見ると苦労したようですが、どんな人生を送ったのか。会えなかったことが、今では寂しく感じられます。