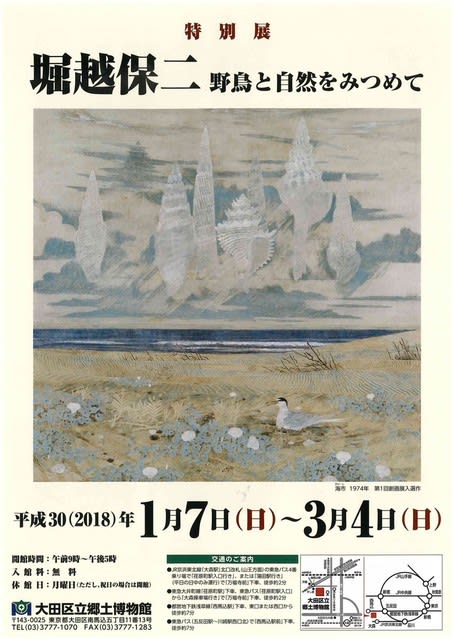週末に乳頭温泉に行った。秋田新幹線の田沢湖駅で降りると、雪が降っていた。乳頭温泉に行く前に、バスで田沢湖を一周した。上掲の写真は湖畔に建つ「たつこ像」。写真だと小さく見えるが、高さは2.3メートルあるので、実際はかなり大きい。わたしの好きな彫刻家、舟越保武(1912‐2002)の作品で、前から一度見たいと思っていたもの。
その日は乳頭温泉に泊まり、翌日は盛岡に移動した。盛岡は仕事で何度か来たことがあるが、プライベートでは初めて。岩手県立美術館が今回の目的だ。初めて訪れる同館では、岩手県ゆかりの美術家、萬鐵五郎(1885‐1927)、松本竣介(1912‐1948)そして舟越保武の作品が常設展示されていた。
わたしの好きな画家の一人、松本竣介と、上述の舟越保武とは、それぞれの展覧会に出かけたこともあり、今回はその折に見かけた作品が多くて、思いがけない再会になった。
今回の発見は、松本竣介と舟越保武が県立盛岡中学(現・盛岡一高)の同期生だったこと。二人はともに1925年(大正14年)に同校に入学した。二人は在学中はとくに親しかったわけではないが、上京してからは親しく付き合い、それは松本竣介が亡くなるまで続いた(同館の解説パネルによる)。
そのような二人の結びつきに、わたしは驚いた。一見したところ、二人の作風には影響関係があまり感じられないが、太平洋戦争をはさんだ困難な時期に、二人が大いに語り合った姿が想像され、わたしは熱いものを感じた。
その夜は盛岡市内に一泊し、翌日は午前中、市内を散策した。盛岡は石川啄木(1886‐1912)と宮澤賢治(1896‐1933)のゆかりの地。啄木は1898年に盛岡中学に入学し(学制変更に伴い校名が何度か変わっているが、ここでは“盛岡中学”で統一する)、賢治は1909年に同校に入学した。二人は約10年を隔てた先輩後輩の関係になり、その先では松本竣介と舟越保武がつながっている。
わたしは20代の頃、啄木の短歌と賢治の童話をずいぶん読んだが、30代に入った頃からは仕事が忙しくなり、文学から離れた。今回、市内の「啄木・賢治青春館」を訪れたときには、昔の記憶が蘇った。
同館に向かう途中で「賢治の井戸」を見つけた。賢治が弟と下宿していたときに使っていた共同井戸。今は駐車場になっている片隅にそれが保存されていた。手持ちのガイドブックには載っていない賢治の痕跡だった。
その日は乳頭温泉に泊まり、翌日は盛岡に移動した。盛岡は仕事で何度か来たことがあるが、プライベートでは初めて。岩手県立美術館が今回の目的だ。初めて訪れる同館では、岩手県ゆかりの美術家、萬鐵五郎(1885‐1927)、松本竣介(1912‐1948)そして舟越保武の作品が常設展示されていた。
わたしの好きな画家の一人、松本竣介と、上述の舟越保武とは、それぞれの展覧会に出かけたこともあり、今回はその折に見かけた作品が多くて、思いがけない再会になった。
今回の発見は、松本竣介と舟越保武が県立盛岡中学(現・盛岡一高)の同期生だったこと。二人はともに1925年(大正14年)に同校に入学した。二人は在学中はとくに親しかったわけではないが、上京してからは親しく付き合い、それは松本竣介が亡くなるまで続いた(同館の解説パネルによる)。
そのような二人の結びつきに、わたしは驚いた。一見したところ、二人の作風には影響関係があまり感じられないが、太平洋戦争をはさんだ困難な時期に、二人が大いに語り合った姿が想像され、わたしは熱いものを感じた。
その夜は盛岡市内に一泊し、翌日は午前中、市内を散策した。盛岡は石川啄木(1886‐1912)と宮澤賢治(1896‐1933)のゆかりの地。啄木は1898年に盛岡中学に入学し(学制変更に伴い校名が何度か変わっているが、ここでは“盛岡中学”で統一する)、賢治は1909年に同校に入学した。二人は約10年を隔てた先輩後輩の関係になり、その先では松本竣介と舟越保武がつながっている。
わたしは20代の頃、啄木の短歌と賢治の童話をずいぶん読んだが、30代に入った頃からは仕事が忙しくなり、文学から離れた。今回、市内の「啄木・賢治青春館」を訪れたときには、昔の記憶が蘇った。
同館に向かう途中で「賢治の井戸」を見つけた。賢治が弟と下宿していたときに使っていた共同井戸。今は駐車場になっている片隅にそれが保存されていた。手持ちのガイドブックには載っていない賢治の痕跡だった。