私がまだ、小学校に上がる前のころ、我が家では蚕を飼っていました。
5mmほどの小さな幼虫から、繭を作ってサナギになるまで、家の中は蚕棚で一杯でした。

山の畑には桑を植え、蚕の餌にするため毎日、枝を切り取っては持って帰っていました。
幼虫のころは柔らかい葉だけ与えますが、だんだんに成長してくると枝ごと与えます。
蚕も数が多いと食欲もすごく、家の中は桑の葉を囓るざわざわという音に包まれていました。

蚕が成長し、繭を作る準備ができると身体が透き通ってきます。そうすると一匹ずつ、紙でできた四角い枠の中に入れます。
上下面にも蓋をしておくと蚕は、その中で糸を吐き、繭を作ります。
しっかりとした繭ができ、中で蚕がサナギになったころに一つずつ取り出し、繭を紙に固定するためのまわりの余分な糸を機械を使って取り除くと、真っ白い繭が現れます。

ここから更に、糸にほぐす作業をするところもあったようですが、我が家では繭の状態で出荷していました。
昼でも夜でも、ざわざわという音は記憶から消えることはありません。
この桑の実、その当時の株が残っていたのか定かではありませんが、子どものころの思い出に誘ってくれました。
[Photo : Nikon D700 / TAMRON SP 180mm Macro]


** にほんブログ村 **
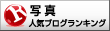


5mmほどの小さな幼虫から、繭を作ってサナギになるまで、家の中は蚕棚で一杯でした。

山の畑には桑を植え、蚕の餌にするため毎日、枝を切り取っては持って帰っていました。
幼虫のころは柔らかい葉だけ与えますが、だんだんに成長してくると枝ごと与えます。
蚕も数が多いと食欲もすごく、家の中は桑の葉を囓るざわざわという音に包まれていました。

蚕が成長し、繭を作る準備ができると身体が透き通ってきます。そうすると一匹ずつ、紙でできた四角い枠の中に入れます。
上下面にも蓋をしておくと蚕は、その中で糸を吐き、繭を作ります。
しっかりとした繭ができ、中で蚕がサナギになったころに一つずつ取り出し、繭を紙に固定するためのまわりの余分な糸を機械を使って取り除くと、真っ白い繭が現れます。

ここから更に、糸にほぐす作業をするところもあったようですが、我が家では繭の状態で出荷していました。
昼でも夜でも、ざわざわという音は記憶から消えることはありません。
この桑の実、その当時の株が残っていたのか定かではありませんが、子どものころの思い出に誘ってくれました。
** にほんブログ村 **










