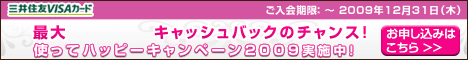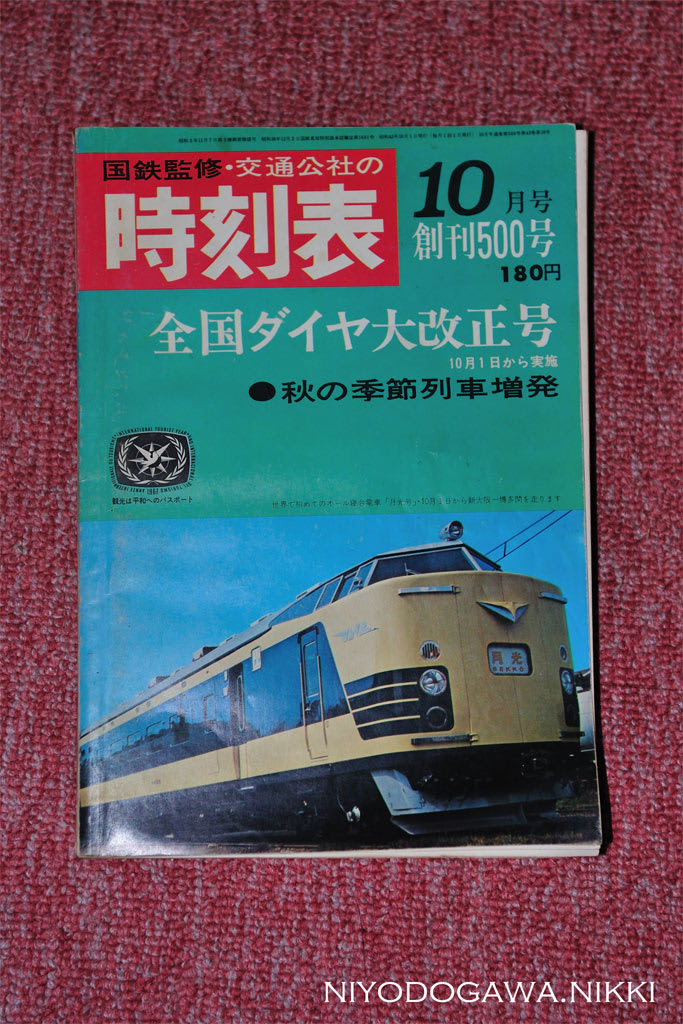今日のTBS「THE世界遺産」はハンガリーのホローケー村でした。
メインタイトルは”人口36人・ホローケーの古い村落”だった(?)と思うのですが、その人口の少なさに驚きました。

私は、2003年12月にここを訪れました。所属する団体の旅行でハンガリーを訪ねましたが、現地のコーディネーターの計らいでその帰路にここに立ち寄りました。

取材にも出ていたお婆さんたちが民族衣装を着て歓迎してくれ、美味しい地元料理もご馳走になりました。また、同行していた若い娘さんがモデルとなって、民族衣装を着せてくれたりと、大歓迎を受けました。

その当時からも寂れた印象はあったのですが、ハンガリーの田舎の村としての古くからの街並みや伝統を守り、それをしっかりと観光資源として活かしていると思いました。

しかし、今は人口が36人となり、それも高齢者がほとんどとのこと。大きな町からは相当に離れていたと記憶していますが、観光だけでは若者が暮らしていくことは難しいことでしょう。

番組での最後に、世界遺産として登録されても、住む人がいなくなっては単なる博物館になってしまう、そんな心配も現実のようです。
[Photo : Minolta α7]



にほんブログ村
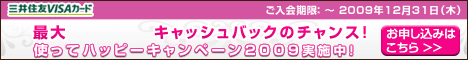

メインタイトルは”人口36人・ホローケーの古い村落”だった(?)と思うのですが、その人口の少なさに驚きました。

私は、2003年12月にここを訪れました。所属する団体の旅行でハンガリーを訪ねましたが、現地のコーディネーターの計らいでその帰路にここに立ち寄りました。

取材にも出ていたお婆さんたちが民族衣装を着て歓迎してくれ、美味しい地元料理もご馳走になりました。また、同行していた若い娘さんがモデルとなって、民族衣装を着せてくれたりと、大歓迎を受けました。

その当時からも寂れた印象はあったのですが、ハンガリーの田舎の村としての古くからの街並みや伝統を守り、それをしっかりと観光資源として活かしていると思いました。

しかし、今は人口が36人となり、それも高齢者がほとんどとのこと。大きな町からは相当に離れていたと記憶していますが、観光だけでは若者が暮らしていくことは難しいことでしょう。

番組での最後に、世界遺産として登録されても、住む人がいなくなっては単なる博物館になってしまう、そんな心配も現実のようです。


にほんブログ村