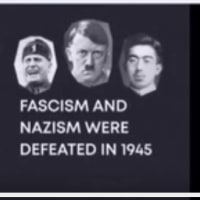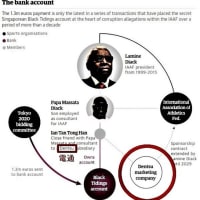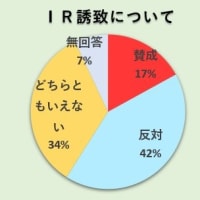防衛省は情報公開法に基づき、航空自衛隊がイラクで行っていた空輸活動を記録した「週間空輸実績」を請求者に開示した。自公政権当時の防衛省は、イラク派兵差止訴訟団などの開示請求に対して活動実態が分からない黒塗りの文書しか開示していなかった。「空自は人道復興支援を行っている」と言い張るためであった。しかし実態は、名古屋高裁が昨年4月、「他国による武力行使と一体化し、憲法9条などに違反する」という判断で示したとおり、復興支援を担う国連職員に比べ、武力行使を伴う兵士の空輸数が圧倒的に多いことがあらためて確認された。これは米軍などへの「後方支援」そのものである。
ブッシュ米大統領は、在任8年間を振り返って、「最大の痛恨事は、イラクに関する情報の誤りだった」、「私も戦争への心構えができていなかった」と反省の弁を述べた。
英国でもイラク参戦をめぐる問題点について包括的調査を行う独立調査委員会が設置され、参戦に至った経緯や軍事攻撃の合法性などについて検証中である。
ところが日本は開戦当時、小泉首相がいち早くブッシュ大統領への支持を表明し、奇妙なヘリクツをこね回して、強引に自衛隊をイラクに派兵した。後を継いだ安倍、福田、麻生の各政権もイラク戦争をめぐる世界の大きな変化に目を瞑った無責任な態度に終始したままである。民主新政権は米英でさえ揺らいでいる「戦争の大義」をどうみているのか、自衛隊派兵は何だったのか、見解をまだ示していない。自公政権によるイラク戦争支持とイラク派兵を徹底検証することがいま、求められている。
イラク派兵違憲4・17名古屋高裁判決は、空自が武装した米軍を中心とした多国籍軍をバグダット空港へ輸送する行為は、政府の憲法解釈とイラク特措法を前提にしても憲法9条1項に違反すると判じた。この裁判で、政府・法務省側は原告団の請求に対し、とりわけ航空自衛隊の空輸活動について徹底的に情報開示を拒否した。そのため原告側は、証人なり証拠を苦労して用意して、イラク派兵違憲確認の主張を展開した。名古屋高裁はそれらにもとづき精密な検討を行い、事実認定したのだった。
公開情報によると、2006年7月から08年12月までの124週間で空輸した2万6千人余の67%に当たる1万7650人は米兵で、実態は米軍の後方支援だったことは明らかだ。イラク特措法の実施要項は武器・弾薬の輸送を禁止していたのに、米兵が人数を上回る小銃・拳銃を持ち込んだ例もあり、武器輸送の抜け道になった可能性もある(「東京新聞」2009年10月7日)。
復興支援とは無縁の、対イラク軍事作戦の一端を担っていた実態が明白となったのだ。

開示された「週間空輸実績」(左)と黒塗りされた過去の開示文書「しんぶん赤旗」2009年10月7日(水)より
これまで防衛省は非開示の理由として「任務に支障が出る」「関係国などの信頼を損ねる」の二点を挙げてきた。今回は、関係国の了解も得られたとして開示に踏み切ったが、本当に関係国が開示に異を唱えていたのかも疑われる。自公政権時代、繰り返し請求しても非開示だったものが、今回全面開示された。政権交代の効果といってよいだろう。
9・11テロ後のアフガニスタン攻撃、イラク戦争を通じて、日本はインド洋での洋上補給、陸自のイラク派遣、空自の輸送支援と、米国の要求に応じる形で海外に自衛隊を派兵してきた。政権交代で実現した今回の情報開示は、年を追って拡大してきた自衛隊派兵の実態について疑問を投げかけた。
「イラク戦争への支援は正しかった」との一点張りで米国追従を続けてきた前政権のウソをそのままにして置いていいのか。今こそ、イラク戦争の正当性も含め、一連の活動を総括すべきときだ。新政権は今回の開示を、徹底した検証作業の第一歩とするべきだ。
ブッシュ米大統領は、在任8年間を振り返って、「最大の痛恨事は、イラクに関する情報の誤りだった」、「私も戦争への心構えができていなかった」と反省の弁を述べた。
英国でもイラク参戦をめぐる問題点について包括的調査を行う独立調査委員会が設置され、参戦に至った経緯や軍事攻撃の合法性などについて検証中である。
ところが日本は開戦当時、小泉首相がいち早くブッシュ大統領への支持を表明し、奇妙なヘリクツをこね回して、強引に自衛隊をイラクに派兵した。後を継いだ安倍、福田、麻生の各政権もイラク戦争をめぐる世界の大きな変化に目を瞑った無責任な態度に終始したままである。民主新政権は米英でさえ揺らいでいる「戦争の大義」をどうみているのか、自衛隊派兵は何だったのか、見解をまだ示していない。自公政権によるイラク戦争支持とイラク派兵を徹底検証することがいま、求められている。
イラク派兵違憲4・17名古屋高裁判決は、空自が武装した米軍を中心とした多国籍軍をバグダット空港へ輸送する行為は、政府の憲法解釈とイラク特措法を前提にしても憲法9条1項に違反すると判じた。この裁判で、政府・法務省側は原告団の請求に対し、とりわけ航空自衛隊の空輸活動について徹底的に情報開示を拒否した。そのため原告側は、証人なり証拠を苦労して用意して、イラク派兵違憲確認の主張を展開した。名古屋高裁はそれらにもとづき精密な検討を行い、事実認定したのだった。
公開情報によると、2006年7月から08年12月までの124週間で空輸した2万6千人余の67%に当たる1万7650人は米兵で、実態は米軍の後方支援だったことは明らかだ。イラク特措法の実施要項は武器・弾薬の輸送を禁止していたのに、米兵が人数を上回る小銃・拳銃を持ち込んだ例もあり、武器輸送の抜け道になった可能性もある(「東京新聞」2009年10月7日)。
復興支援とは無縁の、対イラク軍事作戦の一端を担っていた実態が明白となったのだ。

開示された「週間空輸実績」(左)と黒塗りされた過去の開示文書「しんぶん赤旗」2009年10月7日(水)より
これまで防衛省は非開示の理由として「任務に支障が出る」「関係国などの信頼を損ねる」の二点を挙げてきた。今回は、関係国の了解も得られたとして開示に踏み切ったが、本当に関係国が開示に異を唱えていたのかも疑われる。自公政権時代、繰り返し請求しても非開示だったものが、今回全面開示された。政権交代の効果といってよいだろう。
9・11テロ後のアフガニスタン攻撃、イラク戦争を通じて、日本はインド洋での洋上補給、陸自のイラク派遣、空自の輸送支援と、米国の要求に応じる形で海外に自衛隊を派兵してきた。政権交代で実現した今回の情報開示は、年を追って拡大してきた自衛隊派兵の実態について疑問を投げかけた。
「イラク戦争への支援は正しかった」との一点張りで米国追従を続けてきた前政権のウソをそのままにして置いていいのか。今こそ、イラク戦争の正当性も含め、一連の活動を総括すべきときだ。新政権は今回の開示を、徹底した検証作業の第一歩とするべきだ。