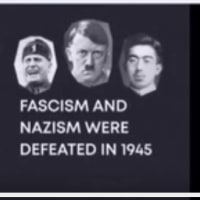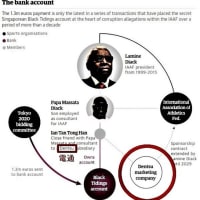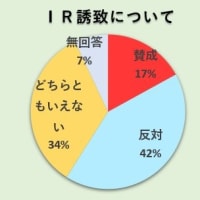<地方分権>のお題目のもと、国から地方自治体への6権限の移譲を巡って、長妻昭厚生労働相と原口一博総務相は、今月中の合意を目指すという。長妻厚労相と原口総務相は、保育所、特別養護老人ホームの設置基準のほか、保育所の利用者の要件、都道府県の職業能力開発校の管理運営の外部委託、障害福祉サービス事業の基準など6つの権限を自治体に移譲する方向で調整に入った。福祉サービスの公共的責任を放棄し、規制緩和と商品化を目指すもので、小泉・竹中新自由主義「構造改革」の流れの一環である。私たちは、自公政権の「構造改革」路線を批判して政権交代を実現したと思っているが、それは錯覚である。民主党のマニフェストには、確かに反「構造改革」的政策も多々含まれているが、所詮非整合的・非一貫的なパッチワークであって、この党の執行部の本流は、小泉・竹中「構造改革」を引き継ぐ「構造改革」派なのだ。
政府の地方分権改革推進委員会は、第3次勧告(7日)で、保育所や特別養護老人ホームなどの設置・運営の最低基準を含む約900項目について、国の基準を廃止、または地方自治体の条例に任せるよう求めた。鳩山由紀夫首相は「スピードをもって実行に移したい」と答えた。
以下福祉の規制緩和と商品化の流れを、保育改革に見てみよう。
「保育所をつくりやすくする」という口実で、認可保育所の職員配置や施設面積などを定めた最低基準(認可基準)の撤廃(規制緩和)が目論まれている。商品化に道を開くために、粗製乱造可能なように、認可基準を撤廃しようというのだ。
「待機児童が多いのに、国基準に縛られて地方の実情に合わせた保育所整備がすすまない」というのが「地方分権」派側の言い分である。しかし、こんなものは「分権」でもなんでもない。保育所に財政資金をかけず、自らの福祉措置の責任を放棄し、営利企業に市場を開放するためには、粗製乱造可能でなければならないし、親の支払い能力に応じた多様なサービス提供のためにも最低基準(認可基準)の撤廃(規制緩和)が必要なのだ。
現在も、東京都などでは独自の「認証」基準を設け、認可保育所増設より認証保育所整備をすすめている。認証保育所とは最低基準を下回る認可外施設のことだ。地方の認可保育所と営利企業の経営する東京都の認証保育所の両方で働いた経験のある保育士は次のように証言している。「実際は認可外施設でも、『都の認証』と聞けば、親は安心感を持ちます。でも、保育の質からみて、公立認可園が10とすれば、私の見た認証園は2か3ぐらい。自分の子どもを預けたいとは思わない」(「しんぶん赤旗」2009年10月26日)。
2001年に無認可保育施設「ちびっこ園池袋西」で乳児が窒息死する事件が起きた。この事件は、利益優先で子どもを預かり、一つのベビーベッドに2人の赤ちゃんを寝かせていたために起きた死亡事件であった。大きな社会問題となり、同年、児童福祉法が改正され、最低基準に準ずる「認可外保育施設指導監督基準」が設けられた。認可保育所の最低基準が取り払われれば、認可外の監督基準も有名無実化するだろう。
地方分権で自由になった自治体が狙っているのは、もちろん公立の認可保育所の増設ではなく、基準を引き下げて営利企業などの参入を図ることである。より低い基準に流れるのは必至で、保育の質の劣化は、子どもの安全を脅かすことに直結する。
もうけ本位の営利企業の参入は、すでに東京都の認証保育所で「階段が急で、転落事故が発生」「食器が100円均一の塩ビ製で熱湯消毒できない」(荒川区・じゃんぐる保育園)、「職員が足りず異年齢児を合同保育しているときに、0歳児が、大きいクラスのおもちゃを誤飲」(世田谷区・小田急ムック成城園)、「経営難から突然、閉鎖」(首都圏で展開していたハッピースマイル)などの事態を引き起こしている(「しんぶん赤旗」同上)。
保育の商品化とは、保育サービス提供者と利用者を市場型契約関係に立たせるということである。現に保育制度改悪の詳細設計を議論している保育第一専門委員会(大日向雅美委員長)では、現在市町村が行っている保育料徴収を保育所が行うことを検討している。現在、市町村が保育所に出している運営費は、市町村が利用者個人に給付することを基本とし、保育所が代理受領する仕組みにするという。利用者直接補助=バウチャー制導入によって保育所と利用者を市場契約関係に立たせる新自由主義的保育制度である。
新自由主義的保育制度のもとでは、現場の保育労働の専門性も保障されない。粗製乱造の保育所では、保育労働が本来もっている「コミュニケーションを媒介・方法にして子どもの発達を保障する」専門性(二宮厚美神戸大教授)は失われ、量だけが問題となる単純労働化されてしまう。こうして、保育サービスの劣化と保育労働の劣化が進む。大人の都合で、健やかに豊かに育つべき子どもたちが迷惑を受けることになるのだ。
政府の地方分権改革推進委員会は、第3次勧告(7日)で、保育所や特別養護老人ホームなどの設置・運営の最低基準を含む約900項目について、国の基準を廃止、または地方自治体の条例に任せるよう求めた。鳩山由紀夫首相は「スピードをもって実行に移したい」と答えた。
以下福祉の規制緩和と商品化の流れを、保育改革に見てみよう。
「保育所をつくりやすくする」という口実で、認可保育所の職員配置や施設面積などを定めた最低基準(認可基準)の撤廃(規制緩和)が目論まれている。商品化に道を開くために、粗製乱造可能なように、認可基準を撤廃しようというのだ。
「待機児童が多いのに、国基準に縛られて地方の実情に合わせた保育所整備がすすまない」というのが「地方分権」派側の言い分である。しかし、こんなものは「分権」でもなんでもない。保育所に財政資金をかけず、自らの福祉措置の責任を放棄し、営利企業に市場を開放するためには、粗製乱造可能でなければならないし、親の支払い能力に応じた多様なサービス提供のためにも最低基準(認可基準)の撤廃(規制緩和)が必要なのだ。
現在も、東京都などでは独自の「認証」基準を設け、認可保育所増設より認証保育所整備をすすめている。認証保育所とは最低基準を下回る認可外施設のことだ。地方の認可保育所と営利企業の経営する東京都の認証保育所の両方で働いた経験のある保育士は次のように証言している。「実際は認可外施設でも、『都の認証』と聞けば、親は安心感を持ちます。でも、保育の質からみて、公立認可園が10とすれば、私の見た認証園は2か3ぐらい。自分の子どもを預けたいとは思わない」(「しんぶん赤旗」2009年10月26日)。
2001年に無認可保育施設「ちびっこ園池袋西」で乳児が窒息死する事件が起きた。この事件は、利益優先で子どもを預かり、一つのベビーベッドに2人の赤ちゃんを寝かせていたために起きた死亡事件であった。大きな社会問題となり、同年、児童福祉法が改正され、最低基準に準ずる「認可外保育施設指導監督基準」が設けられた。認可保育所の最低基準が取り払われれば、認可外の監督基準も有名無実化するだろう。
地方分権で自由になった自治体が狙っているのは、もちろん公立の認可保育所の増設ではなく、基準を引き下げて営利企業などの参入を図ることである。より低い基準に流れるのは必至で、保育の質の劣化は、子どもの安全を脅かすことに直結する。
もうけ本位の営利企業の参入は、すでに東京都の認証保育所で「階段が急で、転落事故が発生」「食器が100円均一の塩ビ製で熱湯消毒できない」(荒川区・じゃんぐる保育園)、「職員が足りず異年齢児を合同保育しているときに、0歳児が、大きいクラスのおもちゃを誤飲」(世田谷区・小田急ムック成城園)、「経営難から突然、閉鎖」(首都圏で展開していたハッピースマイル)などの事態を引き起こしている(「しんぶん赤旗」同上)。
保育の商品化とは、保育サービス提供者と利用者を市場型契約関係に立たせるということである。現に保育制度改悪の詳細設計を議論している保育第一専門委員会(大日向雅美委員長)では、現在市町村が行っている保育料徴収を保育所が行うことを検討している。現在、市町村が保育所に出している運営費は、市町村が利用者個人に給付することを基本とし、保育所が代理受領する仕組みにするという。利用者直接補助=バウチャー制導入によって保育所と利用者を市場契約関係に立たせる新自由主義的保育制度である。
新自由主義的保育制度のもとでは、現場の保育労働の専門性も保障されない。粗製乱造の保育所では、保育労働が本来もっている「コミュニケーションを媒介・方法にして子どもの発達を保障する」専門性(二宮厚美神戸大教授)は失われ、量だけが問題となる単純労働化されてしまう。こうして、保育サービスの劣化と保育労働の劣化が進む。大人の都合で、健やかに豊かに育つべき子どもたちが迷惑を受けることになるのだ。