The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
“ISOを活かす―40. 日常点検によって、計測器の校正はずれを早期に発見する”
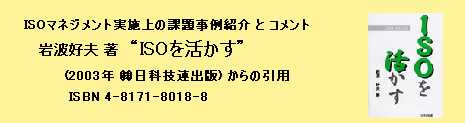
今回は 計測器管理が テーマです。
【組織の問題点】
工作機械メーカーA社では、計測器は12ヶ月ごとに外部校正機関で校正することになっています。ところが、この7月の内部監査でノギスの1つが、昨年3月の校正以来12ヶ月以上経っていることが判明。そこで、そのノギスをすぐに外部校正機関で校正したところ、校正はずれであることが判明し、修理していました。
A社では、昨年の内部監査でも同様の問題があったとのこと。
計測器ノギスに関するA社の管理体制は適切に機能しておらず、どのように対処するべきかという課題です。
【磯野及泉のコメント】
著者・岩波氏は、二つの問題があると言っています。すなわち、先ず 再発防止策を検討せずに 直ちに 外部への校正を依頼するという是正(ISO9001的には修正)作業に入ったこと。第二に 校正はずれのノギスで測定した製品の妥当性を検証せずにいること、です。ISO9001の適用の考え方は 著者・岩波氏の指摘の通りだと思います。
ですが、問題が発覚した時、まずすみやかに是正することは 問題だとは言えず、再発防止策を含めた是正処置を実施しなかったことが、問題なのだと思います。この本では その辺りが 多少 誤解を招く表現になっているように思います。
確実な 是正処置(再発防止策)が実施されていないため、“昨年の内部監査でも同様の問題が発見されている” わけです。一体 内部監査で発見された 不適合はどのように処置されていたのでしょう。
A社の 是正処置のプロセスに根本的な問題がありそうです。
それから、工作機械メーカーA社では どうも 全体にコストや手間の意識が薄いというのが第一印象です。
A社では ノギスの校正に外部機関に依頼している由。ノギス程度の測定精度を要求されているものに コストをかけすぎのような気がします。トレーサブルな基準ゲージを用意して 基準から外れた測定値が出ないかどうか監視し、もしはずれた場合は、廃棄し、新品を購入することで 対処可能なような気がしますし、この方が手間もコストもかからないように思います。それから 基準ゲージを 親基準として 社内の測定器の基準とすれば さらに管理コストは下がるでしょう。
“ノギスの修理” とは一体どのようなことをするのでしょう。あのような簡単な構造の道具は修理可能なのでしょうか。修理後の校正は 可能なのでしょうか。むしろメーカー保証のある新品の方が 安心ではないでしょうか。
そして、基準ゲージこそ外部機関に依頼して点検するべきでしょう。
あるいは、著者・岩波氏の紹介事例は 実は計測器がノギスのような簡易なものではなく、もっと複雑で高精度が要求されるものであったが、ここで 分かり易くするため 計測器を “ノギス” と したのかも知れません。もし、そうであれば 私の提案は成立しません。
測定器の精度管理は システムとして管理するべきです。つまり、測定者の“くせ”による誤差も含めて、測定システム全体の測定誤差の分析をするべきで、ISO/TS16949では GRR(Gage Repeatability and Reproducibility)という統計的管理の手法を推奨しています。これも 考慮するべきでしょう。
また 計測や検査などの頻度や管理コストは オンライン品質工学で考案されている公式で検討してみても良いでしょう。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « “幼児化する日... | 日本人の意識停滞 » |
| コメント(10/1 コメント投稿終了予定) |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |




