The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
“ISOを活かす―37. 特殊工程とするかどうかは、製品の品質保証方法によって決まる”
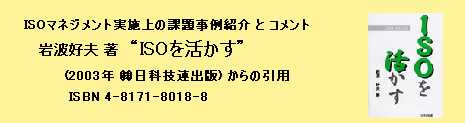
今回 再度 いわゆる特殊工程についてのテーマで、“特殊工程”をどう見るかの問題です。
【組織の問題点】
5年前にISO9001の認証を取得したプラスチック製品メーカーA社では、プラスチック成形工程を ISO9001でいう “製造に関するプロセスの妥当性確認”が必要な “特殊工程”とはしていません。
しかし、同業のB社は “プラスチック成形工程を特殊工程としている” ということを 最近 知って、特殊工程とするべきかどうか迷っているという課題です。
【磯野及泉のコメント】
まず著者・岩波氏は、品質マネジメントシステムの基本及び用語を記載しているISO9000を引用して“特殊工程”の“定義”(厳密には定義の表現になっていません)を紹介しています。そこには“結果として得られる製品の適合が、容易に又は経済的に検証できないプロセス(3.4.1項 参考3.)” と書かれています。つまり “「特殊工程」とは「その工程の後の検査では工程の合否が判定しにくい工程」を意味し、「妥当性の確認」とは「その工程が妥当であるかどうかを事前に検証しておくこと」を意味します。” と 岩波氏は述べています。
*磯野及泉 注:“妥当性確認”は、同じくISO9000では “客観的証拠を提示することによって、特定の意図された用途又は適用に関する要求事項が満たされていることを確認すること。” と定義されています。
一般的に特殊工程の事例として金属溶接が挙げられることが 多いのですが、著者・岩波氏も、溶接後の検査となると破壊検査になってしまうため、溶接の条件を標準化し、その作業の妥当性を確認することによって工程保証するべきだと説明しています。
そしてA社の場合 プラスチックの成形は 事前に原料の配合を含め製造条件が確認検証されているため“特殊工程と考えるのが適切です。” と言いつつも、“A社では、成形後の製品について、できばえの検査を行っています。” したがって “プラスチックの成形工程を特殊工程としないという方法も間違いではありません。” とも述べています。
そして 以下の総括となっています。
*磯野及泉 注:一般的には 製造工程の妥当性確認は いわゆる試作を行なってそれが適合しているだけでは良いとは言えず、適合した試作条件を基準とし、製造工程のパラメータの監視と 結果の記録が含まれます。すなわち、“プロセスの妥当性確認(7.5.2項)”と“プロセスの監視及び測定(8.2.3項)”の合わせ技です。誤解なきよう指摘しておきます。
ISO9001条文の解釈は 著者・岩波氏の指摘通りだと思いますし、自らの行為の結果の妥当性確認はPDCAを実施する上では必要なことだと思われます。それを 検査で行なうのか、工程保証で行なうのかで “特殊工程”という概念を適用するか否かが決まるのだと思います。(但し、ISO9001には“特殊工程”という言葉は登場しません。) そして “検査を省略し、工程保証を自信を持って行なう”には 品質工学の適用による開発を行うのが 良いだろうと思っています。品質工学の泰斗は “あらゆる検査を止めろ!それはムダなことだ!” とおっしゃっているほどです。これまでも幾度か 私の“特殊工程”に関する解釈を説明してきましたが、大略このようなところです。
ところで、“特殊工程の適用”を “迷っている”という プラスチック製品メーカーA社は 厳しい言い方かも知れませんがISO9001の認証を受ける資格はないように思います。まず、会社の管理層以上の 自社技術への自信というか、良い技術の確立への意欲が 感じ取れず、他社動向を聞いて ますますどうして良いのか 迷っている主体性の無さに 情けなさを覚えます。ひいては、経営者のリーダー・シップも欠如していることが 透けて見えるような気がします。
恐らく、日本の多くの企業に見られる“主体性の欠如” だと思われます。ISO9001の認証は このような主体性のない会社には 役に立たないし、また 主体性のない会社に ワールド・ワイドの競争であるメガ・コンペティションに 打ち勝てる訳がなく、遠からず市場から 消え去るべき存在ではないかと思うのです。
ISO9001の認証は 規格の条文を どのように自らの業務に適用し、どの程度まで実施するのか、自らの置かれた状況を厳しく見つめ、リスク回避可能な程度を経験的に考慮して 自らのルール(マニュアル等の文書)に規定し 実施するのが 原則だからです。そのためには 絶えず自らを客観的に認識する主体性が 必要なのです。このプラスチック製品メーカーA社には この主体性が 感じられません。会社のカルチャーには 経営者の性格や気分が 大きく反映するものです。おそらく このようなカルチャーのA社では 経営者は主体性なく、リーダー・シップが希薄なのではないか、と思うのです。
この著者・岩波氏の解説を読んで、主体性の無いAは ますます混迷するのは間違いないでしょう。一般的には ISO審査員はここまでしか 踏み込めません。A社の履歴、技術的経験を含めて十分な観察が 不可能だからです。
自分でどうするか 決めるより仕方ないのです。他人事ではありません。そして、自社技術の高度化を求めるなら “特殊工程”を定めて“検査(コスト)を省略する”のが 自然な方向だと思います。
リスク・マネジメントは 会社経営の非常に重要な側面です。このように 考えてくるとA社は リスク・マネジメントができる状態ではありません。
恐らく、創業者には そのような感覚は有ったのだろう(皆無なら創業は不可能)と思われますが、途中でそれが失われたか、これまで、単に “運が良かっただけ”の会社ではないかと思われます。どうも世間には そのような会社が多すぎるような気がします。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « 長浜グルメ | エスカレータ... » |
| コメント(10/1 コメント投稿終了予定) |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |




