The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
“ISOを活かす―61. 外部文書も最新版の管理を行って、トラブルを防止する”
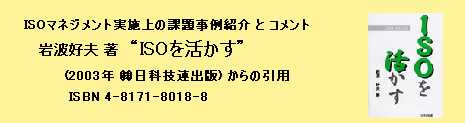
先週はお休みを頂戴しました。今週 再開、外部文書の最新版管理の実用上の問題についてです。
【組織の問題点】
建設会社のA社の内部監査で、次のことが判明しました。総務部で保管されている法規制に関する外部文書が最新版でない。製造部では、顧客図面が、設計部で保管されているものとは日付が違い、最新版でない。
また、これまで、旧図面で作られた製品が出荷されてしまったトラブルがありました。
ISO9001にもとづいて、外部文書はどのように管理すればよいのでしょうか、という課題です。
【磯野及泉のコメント】
著者・岩波氏はISO9001では、4.2.3項で品質マネジメントの文書は、承認と最新版の管理を要求していると指摘しています。また、“社内文書については、管理手順を決めて管理していても、外部文書の管理手順を決めていない企業が多い” とも言っています。次に、ISO9001の4.2.3項を示します。

品質マネジメントシステムを運営するために必要な文書は すべてこの4.2.3項の規定要求事項に従わなければなりません。そして、その文書管理のルールは“文書化”されていなければなりません。最新版管理については c)項、外部文書はf)項に要求されています。しかし、ここでは著者・岩波氏は具体的な 管理手順を示してくれていませんので、ここでは私の対応案を説明しておきます。
まず、外部文書の管理手法としては、その組織の品質マネジメントシステムにとって 必要不可欠な外部文書は何かを明確にして、特定し、その管理手順を ルール化(文書化)しておくことです。
それぞれの 外部文書の主管部署を組織の窓口として決めておき、そこで最新版管理する手順をルール化(文書化)しておくべきでしょう。そうすることで、A社の顧客図面が 製造部と設計部で版が異なるというトラブルは防止するべきです。この場合 設計部が主管部署となるのが適切のようです。これは 恐らく製品の開発や改良のために顧客との打合せは 設計部が窓口となっているため、設計部での文書が最新版になっているものと思われるからです。
顧客関連文書は、改訂のタイミングは把握可能ですが、外部文書である法規制や 規格(例えば JIS規格など)の改訂は その時期を知らぬ間に過ぎることもある可能性があります。したがって、組織にとってその文書内容の変更の影響が大きくない場合には 1年に1回程度は改訂の状況をチェックすることにしておくべきでしょう。
そして、もし、参照するべき外部文書が知らないうちに改訂されていた場合、それが原因でクレームになっていなくても、知らずに顧客に提供された製品やサービスの妥当性の評価をする遡及処置もルール化(文書化)しておくべきです。これには、そのものずばりの適切な規格要求事項はありませんが、7.6の不適切な測定機器で測定した製品を出荷した際の“遡及処置の精神”と8.3の不適合品を出荷してしまった場合の処置に マッチする対応策と言えます。
組織にとって 外部文書変更の影響が非常に大きい場合には その改訂の動きがあるのかどうか、常日頃から業界や官界、学会の動きなどを把握しておけば 察知可能だと思います。また そうすることで、最新の世の中の動きを知り、自らが その業界での先頭に立てる手がかりを得ることも可能となると思うのです。このあたりは、トップマネジメントまたはそれに近い人々の業務となることが多いと思われます。
この一連の活動についてのルール化(文書化)は 困難な側面があるでしょうが、包括的な手順は決めておくべきでしょう。そうしなければ、返って 逆に情報の管理が困難になる可能性があります。この点、経営のトップは 注意深くあるべきです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( )
| « “使いまわし”? | 北京オリンピ... » |






状況が詳しくは分かりませんが、供給先からの約束事なので多くの場合は、問題が起きた時のために保管管理するべきでしょう。もし、ウサギや様から購買仕様書が発せられており、それに供給先も納得していることを示す、証拠があれば供給先からの納入仕様書の重要性は薄れるものとは思いますが…。