The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
“ISOを活かす―44. 欧米式の定期審査によって、ISOの本当の効果が期待できる”
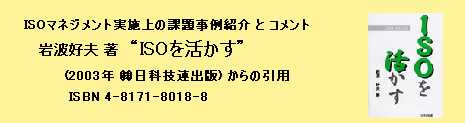
今回から、“第4章 品質マネジメントシステムを改善する方法 その1:監査の活用”に入ります。先ず、今回は 定期審査の性質についての問題です。
【組織の問題点】
昨年ISO9001の認証を取得した測量機器メーカーA社は、最近 定期審査を受けたのですが、昨年の登録審査で指摘されなかった状態を 不適合と指摘されてしまった ということで戸惑いがあるということです。
実際には5件の指摘があり、その内の1件は “顧客アンケートのデータの収集は行われているが、分析と活用は行われていない”というもので、これは 昨年の登録審査時には問題とはならなかったので、昨年の登録審査の指摘のレベルと 今回の定期審査の指摘レベルが 変化しており、審査基準が変わっているのではないかという不信感が 出てきている様子です。
ISO9001の定期審査は、登録審査とは審査基準が変わるものなのか、という問題です。
【ISO活用による解決策】
著者・岩波氏は まずISO9001の認証制度について説明しています。
“ISO9001審査登録(認証)制度の特徴の一つが、認証取得後も定期的に審査が行われることです。これによってISO認証を取得すればそれでおしまいというのではなく、その後も維持改善状況がフォローされるわけで、これがISO認証が顧客や世間に信頼される理由の一つになっています。”
ISO認証が 実際に “世間に信頼されている”か どうかは別にして、定期審査が この種のISOマネジメントの特徴になっていますし、ISO14001等でも同様に実施されています。
そして、ISOマネジメント・システムに この定期審査の仕組があるのは“このシステムが欧米で生まれた”からだとの著者の指摘です。つまり、日本の資格認証は一般的に “一度合格すればその後の定期的な審査は行わない” が、これとは異なると述べています。
しかし、日本には第三者認証の考え方が なかったとは言え、日本のTQCにも内部監査に相当する QA診断は定期的に実施され、似た仕組が用意されていたのは事実です。
著者・岩波氏は 続いて 登録時の審査と その後の定期審査とでは、観点が異なるという主旨の説明をしています。
“たとえば内部監査の実施状況について、登録審査では、「内部監査が計画的に実施されているか。指摘事項に対する是正処置がとられているか」についてチェックされます。これに対して定期審査では、「内部監査の指摘事項は、品質マネジメントシステムを改善するような内容になっているか。またその指摘に対する是正処置は、再発防止になっているか」などの観点からチェックされることになります。すなわち「PDCA改善サイクルが適切にまわっているか」どうかのチェックということになるでしょう。”
“したがって、この例のように、登録審査の際には問題にならなかったことでも、定期審査で問題となることがあります。A社の場合も、ISOを活用して成果を出すことが必要です。定期審査によって、ISOの本当の効果が期待できるのです。”
つまり 定期審査も 継続的改善のツールとして見るべきであるとの見解です。
【ポイント】

【磯野及泉のコメント】
ここで、著者・岩波氏の説明では 認証取得のための登録審査では 品質マネジメントシステムQMSの“適合性”の審査がなされ、定期審査では QMSの“有効性”の審査も付け加わるとの説明であると解釈できます。事実 本書第4章末の“図4‐1 審査の種類”では そのように説明されています。(下表参照)
しかし、適合性の評価というならば、厳密にはISO9001には有効性評価の要求事項8.5.1項(継続的改善)があり、それに適合しなければ “不適合”となってしまいます。

ここは 実際には 審査登録段階では 未だ被審査組織が QMS構築直後であり、ISO9001の要求事項を満たす能力を備えているかどうかに力点をおいた審査になるので、有効性評価の要求事項8.5.1項までを審査対象とするような 審査機関や 審査チームのリーダーは あまり実在しない、と言った方が 正確なのでしょう。
ひょっとして 厳正な審査員が居れば QMS構築直後の登録審査であっても有効性評価の要求事項8.5.1項の不適合があれば、それを指摘する可能性は 論理上ありえると考えるべきでしょう。
ですが、この指摘があった場合でも、具体的に是正内容を示せば、つまり 社内手順(ルール)の変更と それに伴う 社内文書の改訂 などを回答として示せば 登録審査をパスできる可能性は十分にあります。
実際には、この辺に “甘さ”が 見て取れるのが ISOの審査スキームの弱点ではあります。
また 対象組織のQMSにとっての有効性の評価行為の 妥当性を 組織の素人である審査員が適切に評価できるか、というと これが非常に怪しいのも事実で これもISOの第三者認証の問題点であります。したがって、有効性評価の状況の審査について 踏み込んで来ない審査員が ほとんどではないか、というのが これまでの私の経験です。
また被審査組織に 審査のやり方で “不快感” を 与える,トラブルが生じると JRCA(審査員登録機関)に報告しなければならず、審査員資格再任の際に面倒なことになりますので、審査員も その面では慎重にならざるを得ないといった事情もあるようです。同じ審査なら お互い気持ちよくありたい、というのが 審査員側の本音だと思います。したがって 大抵は波風立てない審査になる訳で、指摘事項も、被審査側の納得が得られない指摘は出されません。
それから、このような微妙な部分を認識して 審査機関によっては 登録審査とその直後の定期審査に同一の審査リーダーを起用して、登録時は 8.5.1以外の適合性の評価に重点を置いた審査とし、直後の定期審査に 幾分 有効性評価についての審査に踏み込むような枠組みを考えているようなところもあるようです。そのように、被審査組織のQMSの成熟度に応じた審査を行う 審査機関や 審査リーダーも実在します。したがって、審査基準が変わったように感じる被審査側も多いのが実態なのでしょう。そういった実態を 著者は 指摘したかったのだと思われます。
この辺りの 第三者認証スキームの微妙な部分を 的確に経営者は認識するべきです。そして主体的に自組織の 発展のために 自らの従業員の手前を考え、自組織のQMSの有効性の評価のために定期審査を利用すべきである、というのが 著者・岩波氏の 真意であると思います。
それは、自組織のQMSの有効性の評価行為の多くは経営者のやるべき行為としてISO9001では規定されているからです。(例. 5.1経営者のコミットメント,5.3 品質方針b),5.5.3 内部コミュニケーション,5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプットa) 等)
経営者は 審査員と 審査結論が出た後にでも ざっくばらんな意見交換を行って 自組織の実情を認識するべきでしょう。審査機関によっては、被審査組織の饗応に 応じるなという“お触れ”を出しているところもあるようですが、経営者にとっては、第三者の専門家の評価は貴重です。そのための貴重な審査料であると思うべきです。とにかく 審査員から逃げ隠れするような経営者は失格と言えます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « 明けましてお... | “政治的対立軸... » |
| コメント(10/1 コメント投稿終了予定) |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |




