The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
顧客満足の推定について
“顧客満足”への対応について、かつて指摘していましたように“品質マネジメント”と“品質保証”と“顧客満足”は 密接な関係がありますので この問題は かなり重要です。私は“顧客満足”のために“品質保証”があり、“品質保証”のために“品質マネジメント”があるのだと信じております。
但し ここでの“顧客満足”は ISO9000が想定しているような“不満足でないこと”というような ネガティブではなく、もっとポジティブに“満足”することをイメージしたいと思うのです。つまり、“優、良、可” の “可”のレベルではなくて 限りなく“優”を目指すべきで、そうでなければ“負け組”に転落してしまいます。
詰まるところ 全てのことの発端は「“顧客満足”を どのようにして評価するか」 にかかっていますし、“顧客の気持ち”をどう推定するかは 重要な課題であるべきです。
では“顧客満足”への対応についてISO9001では どのように要求しているでしょう。私の調べたところでは ISO9001では“顧客満足”という言葉は8回登場しているようですが、実質的要求事項としては 次の 箇所ではないかと 思います。
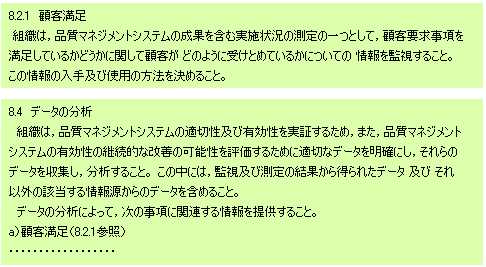
要するに “顧客満足”については 監視するべきで、適切なデータを用いて分析するべきである、ということだと思います。つまり何らかの 客観データ 数量化した指標で監視し、評価しなければならない、ということです。
ところで、“顧客満足”という言葉自体 僭越で顧客の満足度を数字などで忖度などできるものか、という議論もあるようですが、“人間の内面”を議論の全面に持ち出すと 果てしの無い不毛な作業になるように思いますし、マーケティングなどでも課題の客観化が不能に陥るように思いますので この際、そういう議論は 取り下げます。
で、要求事項のデータの話ですが 先にも書きましたように 不特定多数の一般消費者を顧客としているような B to C(Business to Consumer:企業から消費者へ)のビジネスですと 様々なデータを 様々なかたちで入手することは可能だと思います。地域別、時期別の売上や 果ては競合他社の売上さえその気になれば データとして入手できる場合もあるようです。
ですが これが企業対企業のB to B(Business to Business:企業から企業へ)ビジネスでは これが 中々困難になります。このことが、B to Cビジネス出身のISO審査員には 理解し難いようです。曰く
「それならば 顧客にアンケートを取られては どうでしょう」
などという ステレオタイプのご提案をなさるのですが B to Bビジネスでは このアンケート自体が 困難で意味を成さないのです。
どうしてか、B to Bビジネスでは 顧客は 不特定多数ではなく、特定され、個々の顧客の成り立ち、供給(納入)側との関係も 個別に様々なので これを アンケートなどで あぶりだすというのは 不可能です。アンケートでの質問内容は、相手によって変えなければ 聞いても意味をなさないことが多いのです。相手によって質問内容を変えてしまえば、結果を数値化して総括するというのが 不可能になるのは ご理解いただけるでしょうか。
つまり B to Bビジネスでは 8.4 a) の要求事項のデータ監視・分析の実行が 非常に困難な場合が多い、ということです。
では どうすれば良いのか。
私は 顧客で使用されている自社製品の 納入シェアーを何とか探り出すことが 重要ではないか、と思うのです。自分たちの製品を 顧客に納入した数量は容易に把握できますが、顧客が その時期に その製品を使用して 生産することが可能だった数量は 中々 把握できないものです。ですが、これを 販売部隊は 把握する必要があると 思うのです。少なくとも 販売部隊は 顧客とこの程度のコミュニーケションは 持てなければ いけないと思うのです。
このコミュニケーションで、競合他社の様子 が 聞き出せるようだとしめたものですネ。そういう関係を 顧客と持てれば 逆に “7.2.3 顧客とのコミュニケーション” の要求事項くらいは 簡単に 満足できる関係になっているものと思うのです。
また 販売部隊は これくらいの人間力が 持てるように“教育・訓練”されるべきでしょう。
このシェアーの推定は 毎月でなくても数ヶ月毎、或いは 場合によっては1年毎でも良く定期的に実施するのが良いのではないでしょうか。その間の空白は顧客に納入した自社製品の数量や 顧客の対応の様子で 補完、推定可能でしょう。

逆に 自動車会社の多くは この納入シェアーを 積極的に公表して 納入業者の競争を煽っていると伺いました。最近は その傾向は 購買先を絞ってしまうことで、一見穏やかになったように見えるかも知れませんが 基本姿勢は 変わっていないと思います。
自社製品のシェアーの把握は B to Bビジネス,B to Cビジネスいずれにおいても、“顧客満足”を推計し、評価するための基本であると思うのです。
但し ここでの“顧客満足”は ISO9000が想定しているような“不満足でないこと”というような ネガティブではなく、もっとポジティブに“満足”することをイメージしたいと思うのです。つまり、“優、良、可” の “可”のレベルではなくて 限りなく“優”を目指すべきで、そうでなければ“負け組”に転落してしまいます。
詰まるところ 全てのことの発端は「“顧客満足”を どのようにして評価するか」 にかかっていますし、“顧客の気持ち”をどう推定するかは 重要な課題であるべきです。
では“顧客満足”への対応についてISO9001では どのように要求しているでしょう。私の調べたところでは ISO9001では“顧客満足”という言葉は8回登場しているようですが、実質的要求事項としては 次の 箇所ではないかと 思います。
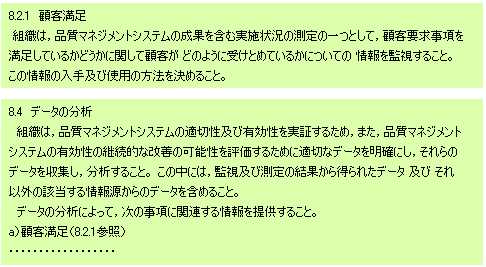
要するに “顧客満足”については 監視するべきで、適切なデータを用いて分析するべきである、ということだと思います。つまり何らかの 客観データ 数量化した指標で監視し、評価しなければならない、ということです。
ところで、“顧客満足”という言葉自体 僭越で顧客の満足度を数字などで忖度などできるものか、という議論もあるようですが、“人間の内面”を議論の全面に持ち出すと 果てしの無い不毛な作業になるように思いますし、マーケティングなどでも課題の客観化が不能に陥るように思いますので この際、そういう議論は 取り下げます。
で、要求事項のデータの話ですが 先にも書きましたように 不特定多数の一般消費者を顧客としているような B to C(Business to Consumer:企業から消費者へ)のビジネスですと 様々なデータを 様々なかたちで入手することは可能だと思います。地域別、時期別の売上や 果ては競合他社の売上さえその気になれば データとして入手できる場合もあるようです。
ですが これが企業対企業のB to B(Business to Business:企業から企業へ)ビジネスでは これが 中々困難になります。このことが、B to Cビジネス出身のISO審査員には 理解し難いようです。曰く
「それならば 顧客にアンケートを取られては どうでしょう」
などという ステレオタイプのご提案をなさるのですが B to Bビジネスでは このアンケート自体が 困難で意味を成さないのです。
どうしてか、B to Bビジネスでは 顧客は 不特定多数ではなく、特定され、個々の顧客の成り立ち、供給(納入)側との関係も 個別に様々なので これを アンケートなどで あぶりだすというのは 不可能です。アンケートでの質問内容は、相手によって変えなければ 聞いても意味をなさないことが多いのです。相手によって質問内容を変えてしまえば、結果を数値化して総括するというのが 不可能になるのは ご理解いただけるでしょうか。
つまり B to Bビジネスでは 8.4 a) の要求事項のデータ監視・分析の実行が 非常に困難な場合が多い、ということです。
では どうすれば良いのか。
私は 顧客で使用されている自社製品の 納入シェアーを何とか探り出すことが 重要ではないか、と思うのです。自分たちの製品を 顧客に納入した数量は容易に把握できますが、顧客が その時期に その製品を使用して 生産することが可能だった数量は 中々 把握できないものです。ですが、これを 販売部隊は 把握する必要があると 思うのです。少なくとも 販売部隊は 顧客とこの程度のコミュニーケションは 持てなければ いけないと思うのです。
このコミュニケーションで、競合他社の様子 が 聞き出せるようだとしめたものですネ。そういう関係を 顧客と持てれば 逆に “7.2.3 顧客とのコミュニケーション” の要求事項くらいは 簡単に 満足できる関係になっているものと思うのです。
また 販売部隊は これくらいの人間力が 持てるように“教育・訓練”されるべきでしょう。
このシェアーの推定は 毎月でなくても数ヶ月毎、或いは 場合によっては1年毎でも良く定期的に実施するのが良いのではないでしょうか。その間の空白は顧客に納入した自社製品の数量や 顧客の対応の様子で 補完、推定可能でしょう。

逆に 自動車会社の多くは この納入シェアーを 積極的に公表して 納入業者の競争を煽っていると伺いました。最近は その傾向は 購買先を絞ってしまうことで、一見穏やかになったように見えるかも知れませんが 基本姿勢は 変わっていないと思います。
自社製品のシェアーの把握は B to Bビジネス,B to Cビジネスいずれにおいても、“顧客満足”を推計し、評価するための基本であると思うのです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « 消費財の顧客... | KES設立5周年... » |
| コメント(10/1 コメント投稿終了予定) |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |




