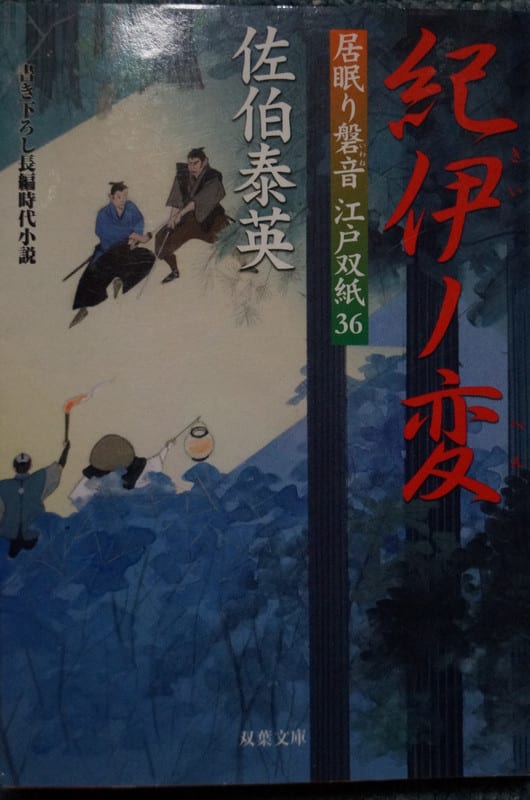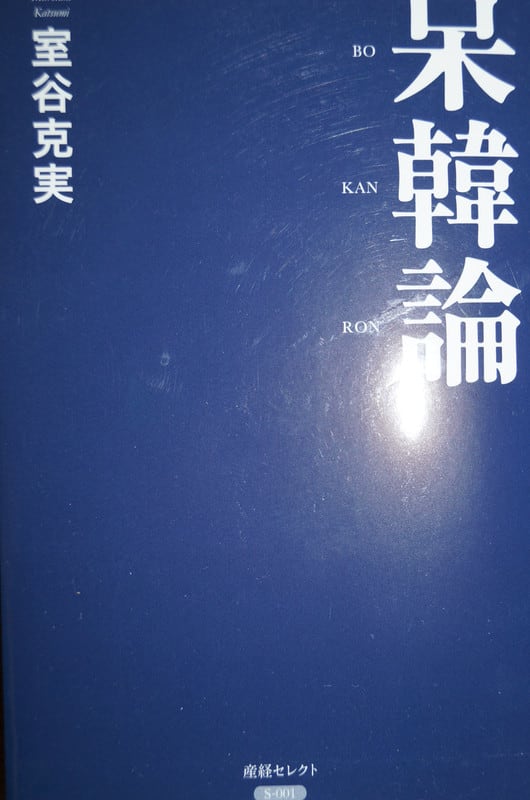尾道市の旧因島市域の週刊ローカル紙に「せとうちタイムス」があります。購読はしていないのですが、時々、WEBバージョンを読ませていただいています。
先日、ふと目にとまったのが「悲運の伊33号潜水艦 三庄ドックでの最期の姿 読者から寄せられた写真」という、2007年に掲載された記事です。
二十歳代前半、衝撃的な描写の小説を読みました。吉村昭氏の「総員起シ」です。昭和19年6月、伊予灘、由利島南方で訓練中であった伊33号潜水艦は潜行するときには閉じておかなければならない弁に修理中に忘れられた木片が挟まれ閉鎖できないまま潜行し、浸水、水深約60mの海底に着底してしまいました。102名が殉職し、2人が脱出に成功します。
由利島近辺。呉から豊後水道を経由して太平洋に出る航路は怒和島水道を抜けてこのあたりを航行します。
<iframe width="425" height="350" src="https://maps.google.co.jp/?ie=UTF8&ll=33.891792,132.583351&spn=0.242526,0.445976&t=m&z=12&brcurrent=3,0x355089d119b7f36b:0xa58e24d21615ddbf,1&output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"> </iframe>
大きな地図で見る
戦後、昭和28年、引き揚げられました。その時、前部魚雷発射管室でベッドに横たわったり、首をつった状態の遺体が腐敗せず、生けるが如く発見されたのです。それを見た脱出に成功し、立ち会っていたO元兵曹が「おい起きろ、総員起シだ」と叫びます。
軍艦乗組員は一心同体、特に生死をともにすることが前提の潜水艦の乗組員は自分だけ助かるという感覚は持ち合わせていないでしょう。この叫びには人間としてのいろいろな思いがしのばれます。
その後、日立造船因島工場で解体されます。せとうちタイムスの記事はこの時の写真が掲載されています。
遺書も多く発見され、「総員起シ」には、士官、兵とも冷静さ、沈着さが書かれています。ある方の読後感ではこれと東日本大震災で日本人が冷静に行動したことが共通しているのではと述べられていました。
しかしながら、潜水艦の内部ではあらゆる手段が講じられ、気圧が高くなり耳がガンガンなり、鼓膜が破れそうで苦しかったと脱出に成功された当時少尉(砲術長兼通信長)の方が平成22年に書かれた記事の中で述べておられます。可能性がなくなった中で従容として死に臨んだのでしょう。
単行本があったはずなのですが見当たりません。本屋に行くと、今年になって発刊された文庫版がありました。若い頃に受けた衝撃が思い出され、その時の不安が現実となることなく穏やかな日を送っていることに感謝です。近くの興居島御手洗に慰霊碑があります。いつか元潜水艦乗りうどん亀さんとお参りに行きましょう。