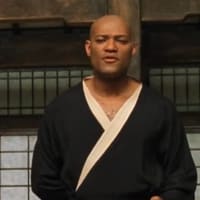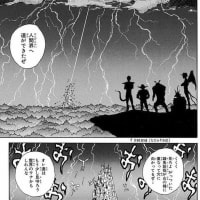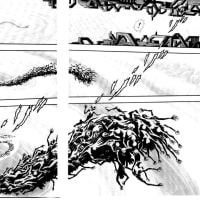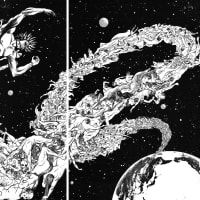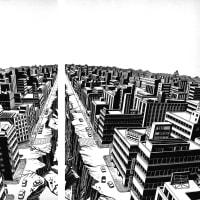・殺人はしてはいけない、と言うことを大前提にして書く。
・究極の理論としては、殺人も仕事の内の一つだが、中抜きしたおかげでうまくいかないというのはたまにニュースになる(中国の五次受け殺人、日本の2次受け殺人)。
それなら現場職制の下手人に、中抜きしていないでかい金額を直接ぽんと払ってやれよとは思う。
・しかしこれは日本の歴史にはこの中間搾取形態はしばしば登場する。
<
作合
さくあい
https://kotobank.jp/word/%E4%BD%9C%E5%90%88-1538572
近世初期の有力農民が、領主と直接生産小農民との間にあって中間搾取する形態。幕藩制社会では、領主―農民の一元的関係が確立していて、田畑の生産物は、その生産活動に必要な部分を生産農民が取り、残りを領主がすべて収取するのを原則とした。しかし、太閤(たいこう)検地段階から近世初期にかけては、持高(もちだか)の零細な小農民に自立しがたいものが多かった。そこで、多くの高をもつ有力農民ないし土豪は、自分の持高の若干を小農民に耕作させて、彼らの自立を助けながら収取し、その収取分から領主へ年貢を納めて、なお手元に若干を残した。この残分が中間搾取分であり、作合とよばれた。作合は一種の小作料である。
>
こうした中でも小作民がそれでよしと思っていたのは、教育の不足、独立心の不足とそれを許さぬ時代背景と独立力の不足である、と。
これは今のアップルやグーグルのデジタル使用量徴収にも現れる。
・究極の理論としては、殺人も仕事の内の一つだが、中抜きしたおかげでうまくいかないというのはたまにニュースになる(中国の五次受け殺人、日本の2次受け殺人)。
それなら現場職制の下手人に、中抜きしていないでかい金額を直接ぽんと払ってやれよとは思う。
・しかしこれは日本の歴史にはこの中間搾取形態はしばしば登場する。
<
作合
さくあい
https://kotobank.jp/word/%E4%BD%9C%E5%90%88-1538572
近世初期の有力農民が、領主と直接生産小農民との間にあって中間搾取する形態。幕藩制社会では、領主―農民の一元的関係が確立していて、田畑の生産物は、その生産活動に必要な部分を生産農民が取り、残りを領主がすべて収取するのを原則とした。しかし、太閤(たいこう)検地段階から近世初期にかけては、持高(もちだか)の零細な小農民に自立しがたいものが多かった。そこで、多くの高をもつ有力農民ないし土豪は、自分の持高の若干を小農民に耕作させて、彼らの自立を助けながら収取し、その収取分から領主へ年貢を納めて、なお手元に若干を残した。この残分が中間搾取分であり、作合とよばれた。作合は一種の小作料である。
>
こうした中でも小作民がそれでよしと思っていたのは、教育の不足、独立心の不足とそれを許さぬ時代背景と独立力の不足である、と。
これは今のアップルやグーグルのデジタル使用量徴収にも現れる。