
引き続き、佐々木高明氏の「山の神と日本人」という本のご紹介をさせていただきます。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
「東北日本の畑神信仰の基層にあるもの」
日本列島における「山の神」の信仰は単一・同質のものではない。
東北日本の「山の神」信仰には、狩猟民や山稼ぎ人などの「山民」の信仰する「山の神」信仰の色が濃く、稲作農民の信仰する「山の神=田の神」の影は色薄いと感じられる。
私は、会津山脈から北上山地に見られる「良い種を持って天から降りて来る畑神の去来信仰」の中に、“稲作以前の神の姿”を強く感じるのである。
「常陸国風土記」に描かれている、稲作民が土着の強者“夜刀神”を山地に祭り上げる説話は、水田稲作民が東北日本に進出した際の、土着の非・稲作民との接触・交渉の典型例の一つと考えることができる。
だが西日本から日本列島の東北部へ、稲作文化をもった人々が進出した際、そこで接触した東北日本の土着文化は、必ずしも採取狩猟のみに依存する文化ではなかった。
既に縄文時代の東北日本における、幾種類かの作物遺体が確認されている。
東北日本において、ある種の農耕が営まれていた可能性を否定するわけにはいかない。
しかもその農耕は西日本の照葉樹林型の農耕とは系統と特色を異にする“もう一つの農耕”であった可能性が少なくないのである。
この「もう一つの農耕」の存在を推測させる根拠は、日本列島の在来作物、特に東日本を中心とした地域の在来作物の中には、南方には系統がつながらず、むしろ北方の東北アジアやシベリアにその系統がつながるような作物がいくつも存在することである。
しかもそれらの作物の伝来は、いずれもかなり古いと想定されている。
アワやキビは、従来は中国・華北の黄土台地がその起源地とされていた。
しかし再調査の結果、その起源地は中央アジアからアフガニスタンを経て、北西インドに至る地域であることが判明した。
アワやキビはそこから、シベリア南部経由の北回りの道とインド経由の南回りの道の両方のルートに分かれて東アジアに伝わったと考えられている。
たとえばアイヌの人たちが古くから栽培しているキビは、本州のものと比べて、極めて早成で草丈が低く色が紫である。
これは中央アジアやヨーロッパのキビに見られる特徴と共通するもので、この種のキビは北方ルートで伝播した可能性が強いという。
大麦、蕪をはじめ、蕎麦の栽培、豚の飼育なども北方の特徴である。
「続縄文時代」の後期(4~6世紀)には・式土器が北海道から東北地方へ南下し、ほぼ現在の秋田・盛岡・仙台を結ぶ線以北の、東北地方の北部に広がるようになる。
また、「ペツ(あるいはベツ、大きな川)」や「ナイ(小さい川)」などに代表されるアイヌ語地名もほぼ同様の分布を示し、東北地方の北部一帯を覆っている。
おそらく現在のアイヌ語に近い言葉を話す集団が・式土器を携えて北海道から南下し、かなりの期間、東北地方の北部一体に定着したと考えて誤りないと私は思っている
他方、律令国家による9世紀初めごろまでの城柵建設の北限も、この文化圏の南限にほぼ一致している。
この線以北は、8世紀まではもちろん、それ以後もかなり長く蝦夷の文化地域であり、北海道南部と連続する同一の文化圏を作っていたと見て差し支えないと考えられる。
北上山地は、まさにこの蝦夷地域の中核地帯であり、そこに分布する焼畑の特異な特色が本州の他の焼畑と異なっている理由は、北方系の畑作農耕がかつて北海道南部やこの地域に展開し、その伝統が今日まで残ったものと考えると、その特色の成立が理解できる。
北方系の雑穀類は、サハリン経由の他に、沿海州あるいは朝鮮半島北部などから日本海を横断するルートを経て、続縄文時代ないしその前後の時代に東北日本の北部などに伝来した可能性も少なくないと考えられる。
727年、最初の渤海国使が山形県の出羽に漂着したのをはじめ、8世紀から9世紀初頭頃にかけて、渤海使の多くが東北日本北部に到着している。
こうした事実から見て、この日本海横断の伝播路によって、北方系の畑作農耕が早い時期に北海道南部や東北北部に伝来した可能性も、決して小さくはないと考える。
(引用ここまで)
*****
この、きわめて学術的な文章を読んで、わたしは、日本における「焼畑」文化ということを、強く意識しました。
わたしの好きな昼ごはんは、おむすびです。
白いお米を塩味でほどよく握ったおむすびほど、おいしいものはないのではないかと思うほどです。
このおむすびは、稲作文化になりますが、それ以前、また、それ以外に、焼畑文化が日本にも色濃く存在したということは、とても衝撃的でした。
今、若い人たちに流行りの「カフェご飯」なるものも、国籍不明、東西混交の食べ物ですが、焼畑文化についても、もう少し勉強しなければいけないと、思いました。
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事
「マタギの世界(1)・・北方の山の神と、山人(やまうど)の生活」
「フィリピン少数民族 守る固有文字・・教える親減少、政府援助もなし」
「マニ教研究その6・・中国での盛衰」
 「アイヌ」カテゴリー全般
「アイヌ」カテゴリー全般「ブログ内検索」で
山の神 13件
焼畑 3件
東北 13件
アフガニスタン 4件
などあります。(重複しています)












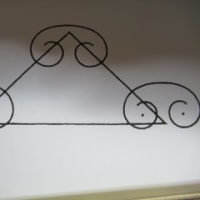


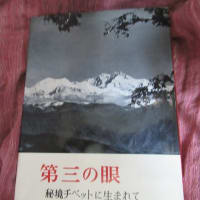







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます