
中央アジア考古学の研究者、堀晄(あきら)氏の「古代インド文明の謎」を読んでみました。続きです。
著者はインダス文明をインドだけで見ることなく、当時のオリエント世界全体の中でとらえようとしておられます。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
インドの中石器時代の人骨の形質人類学的な研究でも、それを支持する結果が出されている。
それはK・A・R・ケネディによる中石器時代人骨の研究である。
彼は12000年~9359年前と推定されるインドの遺跡から出土した人骨の形質を研究し、それらが西アジアの中石器人骨とは異なること、
またヨーロッパの後期旧石器(特に後半の前19000年頃や、前18000年~10000年)の人骨に近いことを明らかにしたのである。
中央アジアやウラル方面から出土する人骨に関するDNA分析は、ほとんど行われていないのが現実であり、形質人類学の研究成果が重要となる。
その中で特に重要なのは、P・C・ドッタの研究であろう。
彼はハラッパー遺跡から出土した人骨をイランのヒッサール遺跡3期(前3000年から2000年)及びエジプト(バダリ期など)の人骨と比較した。
この結果から彼は、
1・従来インドとイランとエジプトが同一のクラスターに入るはずはないとして、「インダス文明」ハラッパー期以前の人骨が研究されていないが、このギャップを埋めることが必要であるとした。
2・パンジャブ地方の現代人の形質は、わずかな違いは認められるものの、ハラッパー期の人骨と同系統であると結論づけた。
1について言えば、西アジアや中央アジア、ヨーロッパを含めた広い範囲の人骨の比較研究を進めなければ結論は出ないであろう。
2はきわめて重要な結果である。
「インダス文明」の人骨と現代のパキスタン北部の人々(いわゆるインド・アーリア系)が形質的に同じ系統に属するということは、歴史的に大きな民族変動がなかったことを示す可能性があるからである。
同時に彼の研究では、インダス文明のハラッパー人とイランのヒッサール人が同じクラスターに入るとされ、現代人のDNA分析データとは異なった様相が、古代インドにあった可能性も示唆されている。
現代インド諸民族のDNA研究は、民族のるつぼと言われる状況を反映し活発に行われている。
その中でも、アナラブハ・バスらの研究は広範な分析を行っており、重要である。
彼らは58のDNA比較指標を用い、次のような見通しを得た。
1・オーストラロ・アジア系が最も古くインドに定着した。
2・チベット・ビルマ系はオーストラロ・アジア系と共通する要素が多く、南中国を起点に定着していったと考えられる。
3・「ドラヴィダ系」はインドの支配的住民であったが、印欧系の侵入によって南に追いやられたと考えられる。
4・上級カーストの構成員は中央アジアの人々と極めて近い。ただし南に行くほど関係は疎遠になる。
この分析結果は、定説である「インド・アーリア侵入説」とは矛盾していない。
中央アジアを介して、印欧語族がインド世界に入ってきたことは確実であろう。
問題は考古学的発掘で得られた人骨のDNA分析が全く進められていないことである。
古代における民族移動の様相を、同時代的な資料で明らかにすることこそ、今後の課題である。
インド・アーリア語は、インドヨーロッパ系言語群の中でイラン語とグループを形成している。
最新の系統樹は、2003年にニュージーランドの言語学者グレイによって発表された。
グレイによれば、現在知られているかぎり最も古い印欧語はヒッタイト語であり、その他の印欧語諸語と分岐したのは8700年前頃と推定されている。
印欧語の拡散の古い段階で、インド・イラン諸語が東方群として分岐している。
やがてそれらはインド諸語とイラン語に分離独立してゆくのである。
インドではヒンディー語は人口のおよそ30%の人々が話し、また十分理解できる人口はおそらくこれ以上の数に及ぶ。
ドラヴィダ語はドラヴィダ族の人々が使用する諸言語で、およそ26の言語が含まれる。
ドラヴィダ語は主として南インドとスリランカで話されているが、またパキスタン、ネパール、そして東部および中央インドの特定の地域でも話されている。
ドラヴィダ語は2億人を超える人々に話されているが、孤立語として、その系統や起源は明らかではない。
ドラヴィダ語と、ウラル語およびアルタイ語のグループの間には著しい類似性が存在し、このことは両者が共通の起源よりの派生であるとはとても思えないにしても、これらの語族の間で展開のある段階において、長期間にわたる接触が存在したことを示唆する。
その他に多数のチベット、ビルマ語派(シナ・チベット語族内の語派)の言語やオーストロ・アジア語族の言語が、少数民族の間で使われている。
印欧語を話す人々は、おそらく印欧語の故地である西方から、ある段階でやってきたに違いない。
それ以前は一般に言われるように、ドラヴィダ語、そしてさらに前にはオーストロ・アジア語が使われていたのであろう。
DNA人類学の成果では、東北インドから南インドにかけては、西北インドとは異なった人間集団がいることが明らかにされている。
彼らはドラヴィダ系言語を話す人々であり、それ以前のオーストロ・アジア語を話す人々はほとんど消滅し、少数民族として存在するにすぎない。
東北インドの人々はDNAの分類では南インドの人々と同じグループをなすが、言語的には西北インドの影響を受け、印欧語系統の言葉を話すようになったと読み取れる。
かつての「インダス文化」地域を含めた西北インドは、インドで最も古く農耕文化が定着した地域であり、その農耕文化はイラン高原から伝えられたことは明らかである。
したがって、「インダス文化」を含めた初期農耕文化の人々は印欧語を話す集団であったと考えられる。
やがてインド・イラン系の言語から独立し、インド・アーリア語を形成していった。
インド・アーリア語が東北インド一帯に広がったのは、「インダス文化」後期から初期鉄器時代にかけての、農業拡張の時代であったと推定するのが、最も素直な解釈であろう。
(引用ここまで)
*****
>かつての「インダス文化」地域を含めた西北インドは、インドで最も古く農耕文化が定着した地域であり、その農耕文化はイラン高原から伝えられたことは明らかである。
>したがって、「インダス文化」を含めた初期農耕文化の人々は印欧語を話す集団であったと考えられる。
私の理解違いでなければ、著者はインダス文明はインド文明と異質なものではなく、連続した文明であると考えていると思われます。
一般的にはインダス文明はドラヴィダ語を話すドラヴィダ族により作られ、アーリア人によるインド文明に淘汰されたと考えられていますが、著者はインダス文明は最初から印欧語の文明であり、理解不能のインダス文字は文字ではなく、呪文のしるしであり、ドラヴィダ語とは関係がない、ということではないかと思います。
>ドラヴィダ語は2億人を超える人々に話されているが、孤立語として、その系統や起源は明らかではない。
>ドラヴィダ語と、ウラル語およびアルタイ語のグループの間には著しい類似性が存在し、このことは両者が共通の起源よりの派生であるとはとても思えないにしても、これらの語族の間で展開のある段階において、長期間にわたる接触が存在したことを示唆する。
著者は、ドラヴィダ語は系統不明の言語であり、起源を跡付けることはできないこと、またウラル語・アルタイ語との親近性から、ドラヴィダ族は印欧語文明とは異なった民族との文化的接触があったことを想定しているのだと思われます。
>タミル(Tamiḻ)という名称は、ドラミラ Dramiḻa(ドラヴィダ Dravida)の変化した形という説もある。
wikipediaによる上記の記述も興味深く思いました。
かつて大野晋氏の「日本語タミル語起源説」が流行ったことがあったことを思い出しました。
そういったことにも考えを広げていければ、と思っています。
追い詰められ、彷徨うミャンマーのロヒンギャ族の方々の姿は、遠い遠い昔の古代ドラヴィダ族の、かつては栄え、消え去った文明を彷彿とさせるように思われます。
 wikipedia「ウラル・アルタイ語族」より
wikipedia「ウラル・アルタイ語族」よりウラル・アルタイ語族は、言語の分類の一つであり、かつては、印欧語族、セム・ハム語族(現在のアフロ・アジア語族)とともに世界の3大語族とされていた。
現在、ウラル・アルタイ語族は、ウラル語族とアルタイ諸語の関連性が否定され、別々に扱われている。
日本語・朝鮮語をウラル・アルタイ語族(アルタイ諸語)に含める説もあった。
共通の特徴としては、膠着語であり、SOV語順(例外もある)、母音調和があることが挙げられる。
しかし共通する基礎語彙は(ウラル語族を除いて)ほとんどなく、上の特徴も地域特性(言語連合)である可能性が高い。
そのため現在は、それぞれウラル語族、アルタイ諸語に分類されている。
 wikipedia「タミル語」より
wikipedia「タミル語」よりタミル語は、ドラヴィダ語族に属する言語で、南インドのタミル人の言語である。
同じドラヴィダ語族に属するマラヤーラム語ときわめて近い類縁関係の言語だが、後者がサンスクリットからの膨大な借用語を持つのに対し、タミル語にはそれが(比較的)少ないため、主に語彙の面で隔離されており意思疎通は容易でない。
インドではタミル・ナードゥ州の公用語であり、また連邦レベルでも憲法の第8付則に定められた22の指定言語のひとつであるほか、スリランカとシンガポールでは国の公用語の一つにもなっている。
世界で18番目に多い7400万人の話者人口を持つ。
1998年に大ヒットした映画『ムトゥ 踊るマハラジャ』で日本でも一躍注目された言語である。
「タミール語」と呼称・表記されることもあるが、タミル語は母音の長短を区別する言語であり、かつ Tamiḻ の i は明白な短母音である。
そのため、原語の発音に忠実にという原則からすれば明らかに誤った表記といえる。
タミル(Tamiḻ)という名称は、ドラミラ Dramiḻa(ドラヴィダ Dravida)の変化した形という説もある。
Tamiḻ という単語自体は sweetness という意味を持つ。
なお、ドラヴィダとは中世にサンスクリットで南方の諸民族を総称した語で、彼らの自称ではなく、ドラヴィダ語族を確立したイギリス人僧侶 Caldwell による再命名である。
 関連記事
関連記事
 「その他先住民族」カテゴリー
「その他先住民族」カテゴリー 「ブログ内検索」で
「ブログ内検索」でインド 15件
ドラヴィダ 3件
アーリア人 6件
などあります。(重複しています)











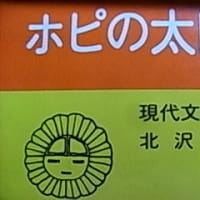

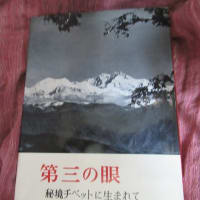











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます