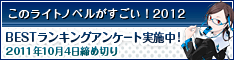初めてパソコンを購入したのは1997年。二台目が2002年頃。そして、三台目が2009年の年末だった。
当時はPCゲームをプレイすることが多く、それなりのスペックを求めていた。しかし、予算的にメモリを積めず、FF11なら快適にプレイできたが、FF14だとかなり厳しい感じだった。
SSDも当時普及し始めた頃で、まだ手が出なかった。初めての液晶モニタとセットで購入したので、それなりに新鮮さはあったし、それ以前のものよりは遙かにスペックアップしていたので満足感はあったが、スペック的にはすぐに物足りないものになってしまう。
それでも、スペック自体には今でもそれほど不満は抱いていない。メモリ不足を感じることは往々にあるが、我慢できないほどではなかった。
問題はトラブルの多さだ。
購入直後から様々なトラブルが起きた。多くは接触不良によるハードのトラブルだと思われた。グラボの挿す位置を変えたり、ハードディスクを換装したり、トラブルを機に色々といじることが多かった。
特にブラックアウトになるトラブルはずっとつきまとった。ほぼ予告なしに起き(あるいは衝撃を受けると発生(PCの載っているテーブルにコップを軽く置いただけでも起きたことがある))、起きたら電源を切る以外に復旧の手がない。
しかも、再起動しようとしても立ち上がらないことが多々あり、復旧に数十分から数時間かかることもあった。
それでも、「たまに」ならまだよかった。この夏、おそらくは暑さも原因だと思うが、このトラブルが頻発した。数十分かけてようやくWindowsが立ち上がったと思ったらまたブラックアウトといった心折れる事態も起きた。
さすがにこれ以上使い続けられない。精神衛生的にも、もうね。
高スペックPCゲームをプレイしなくなったので、グラボ不要。Windowsの起動にかなり時間がかかっていたので、SSD搭載モデルを選択。またメモリも増やした。
メーカーは初代、二代目のPCと同じDELL。注文から二週間ほどで届き、環境の再構築に日々を費やしている。
いちばんの驚きはその静音性。PCってこんなに静かだったっけと思うほど。いや、それほど今まで使っていたPCがうるさかったということだろう。
環境が整うまでにはもう少し時間がかかりそうだが、PCの快適さはいかに精神的に大きいかを実感している。逆に言えば、これまでいかに時間をロスし、精神的苦痛を受けていたか。高い買い物(とはいえ過去に比べると非常に低価)だが、もう元が取れた気がしてしまう。
当時はPCゲームをプレイすることが多く、それなりのスペックを求めていた。しかし、予算的にメモリを積めず、FF11なら快適にプレイできたが、FF14だとかなり厳しい感じだった。
SSDも当時普及し始めた頃で、まだ手が出なかった。初めての液晶モニタとセットで購入したので、それなりに新鮮さはあったし、それ以前のものよりは遙かにスペックアップしていたので満足感はあったが、スペック的にはすぐに物足りないものになってしまう。
それでも、スペック自体には今でもそれほど不満は抱いていない。メモリ不足を感じることは往々にあるが、我慢できないほどではなかった。
問題はトラブルの多さだ。
購入直後から様々なトラブルが起きた。多くは接触不良によるハードのトラブルだと思われた。グラボの挿す位置を変えたり、ハードディスクを換装したり、トラブルを機に色々といじることが多かった。
特にブラックアウトになるトラブルはずっとつきまとった。ほぼ予告なしに起き(あるいは衝撃を受けると発生(PCの載っているテーブルにコップを軽く置いただけでも起きたことがある))、起きたら電源を切る以外に復旧の手がない。
しかも、再起動しようとしても立ち上がらないことが多々あり、復旧に数十分から数時間かかることもあった。
それでも、「たまに」ならまだよかった。この夏、おそらくは暑さも原因だと思うが、このトラブルが頻発した。数十分かけてようやくWindowsが立ち上がったと思ったらまたブラックアウトといった心折れる事態も起きた。
さすがにこれ以上使い続けられない。精神衛生的にも、もうね。
高スペックPCゲームをプレイしなくなったので、グラボ不要。Windowsの起動にかなり時間がかかっていたので、SSD搭載モデルを選択。またメモリも増やした。
メーカーは初代、二代目のPCと同じDELL。注文から二週間ほどで届き、環境の再構築に日々を費やしている。
いちばんの驚きはその静音性。PCってこんなに静かだったっけと思うほど。いや、それほど今まで使っていたPCがうるさかったということだろう。
環境が整うまでにはもう少し時間がかかりそうだが、PCの快適さはいかに精神的に大きいかを実感している。逆に言えば、これまでいかに時間をロスし、精神的苦痛を受けていたか。高い買い物(とはいえ過去に比べると非常に低価)だが、もう元が取れた気がしてしまう。