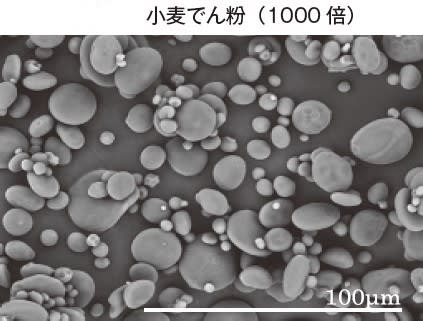ロイテリヨーグルト 1
唐突ですが、自家継代しているヨーグルト(ロイテリヨーグルト)の味が少し酸味を帯びてきたようです。今朝食べたときに舌の先に今までとは違った酸味を感じたのです。( L. reuteri、L. bulgaricus、St. thermophiles の3種類のヨーグルト菌を使った ) 今までに使っていたヨーグルト( R-1 ) ではなく、ロイテリヨーグルトの種を6/19日に継ぎ始めて今朝のヨーグルトが4回目のものになります。
St. thermophilus が出すギ酸のせいだろうか?この間どこかで読んだ、ギ酸の文字が頭の中を過ぎります。舌の先に酸味を覚えたときに、子供の頃、咬んだアリの味が蘇りました。
( ロイテリヨーグルトはL. reuteri DSM17938, L. reuteri PTA 5289株、ブルガリア、サーモフィルス菌を入れて作ったヨーグルトです。乳酸菌以外にはゼラチン、キシリトールなどが入っています。)

ヨーグルト菌、ラクトバシラスに関してこの際、頭の中を整理しておこうと思いました。疑問に思うことが乳酸菌に関して以前からあったからです。
フィルミクテス門( Firmicutes,グラム陽性細菌門)の下位に当たるラクトバシラス目( Lactobacillales ) の中にラクトバシラス属 ( Lactobacillus ) があります。
この中には他に、エンテロコッカス属 ( Enterococcus )、ラクトコッカス属 ( Lactococcus )、ペディオコッカス属 ( Pediococcus )、リューコノストック属 ( Leuconostoc )、ストレプトコッカス属(レンサ球菌属) ( Streptococcus )、ビフィドバクテリウム属 ( Bifidobacterium ) があり、生物活性で分類すると、次の性質があります。
グラム陽性
桿菌・球菌
芽胞を作らない
運動性はない
消費ブドウ糖に対して50%以上の乳酸を生成する
ナイアシン(B3)を必須要求する
ヨーグルト菌が作り出す産生物で分類すると、乳酸のみを作るホモ乳酸菌と、ビタミンC、アルコール、酢酸、ギ酸、葉酸など乳酸以外のものを乳酸と一緒に産生するヘテロ乳酸菌に分類します。
ストレプトコッカス属、ペディオコッカス属はホモで、ラクトバシラス属にはホモとヘテロが混在しています。( 環境によって双方の性質をもつことがあります。)
L. bulgaricusは通性ヘテロ乳酸発酵をしてペプチド、アミノ酸をSt. thermophilusに、thermophilusはギ酸をbulgaricusに供与しあって共に生きていく、いわゆる共生関係があります。
(以下は2015年. Japan Society for Lactic Acid Bacteria から引用させていただきました。)をご覧いただくと興味深いことが解ります。

説明にあるように、共生とは言っても、二つの菌を同じ条件下で牛乳の中に入れるとSt. thermophilusの数がbulgaricusに比べ、急速に伸びています。
共生関係にある二つの菌を、もう少し観察時間を延長した、別の角度でながめた文献を次にご紹介しておきましょう。
Microbes Specific to Yogurt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Yogurtから
Microbial Interactions

Fig 3. L. bulgaricus and S. thermophilus 間における相対密度関係
L. bulgaricusと S. thermophilus間における抗生、共生関係を理解することはヨーグルトを作るうえで重要です。(抗生と共生は正反対の関係です。)二つの菌を一緒に培養するとそうでないときに比べ、香りと乳酸がたくさん作られます。( 図2.(A)の単菌培養のグラフでも明らかです。)
赤線で示されたL. bulgaricusはS. thermophilusよりもタンパク質分解が高い一方、S. thermophilusは、特にアミノ酸のない牛乳の中ではタンパク質分解能が低いのですが、L. bulgaricusは少量のペプチドとアミノ酸(主としてヴァリン)をS. thermophilusのために提供し、その代わりに、S. thermophilusはL. bulgaricusの成長に必要なギ酸を提供する。このような共生関係によって単体で作るよりも早く乳酸を作り出すことになるのです。
抗生現象は酸度がある一定水準を超えたときに起こります。S. thermophilusの成長が止まったときがその時です。L. bulgaricusは酸に対する感受性が低く、成長を続けるのです。培養3時間を超えたとき成長曲線は交差している( fig.3 )
S. thermophilusはpHが4.2-4.4の間で成長が阻害される一方、 L. bulgaricus はpH3.5-3.8であっても耐性があるからです。( fig.3 )で示された成長曲線の理由がここにあります。培養温度と時間はコントロール下に置かれるべきであり、一定の結果が得られた生産物は速やかに冷却し反応を停止すべきです。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/chikusan1924/53/3/53_3_161/_pdfでは
L. bulgaricusとS. thermophilusの共生関係が必ずしもあるとは言えないことを示す、貴重な意見が述べられています。いかに引用しておきます。
タンパク分解力が強ければ遊離アミノ酸が多量に蓄積され、S. thermophilusの代謝活性が高められ、したがって乳酸生産量、ギ酸生産量も増加し、ギ酸を必要とするL. bulgaricusの生育も好都合となる理屈であるが、 S. thermophilus 510タイプのS. thermophilusに対してはむしろ阻害的に働く可能性がある。実際、S. thermophilus 510はL.bulgaricus B5b ( 畜産試株 ) あるいはL, helveticus B-1との組み合わせでヨーグルトスターターに使用されているがが、独特の粘性で良好なテクスチャーをもたらす。この510の性質を生かすにはL. bulgaricus AY のようなタンパク分解力の強いL. bulgaricusよりもL.bulgaricus B5b のようなタンパク分解両区の弱い菌種との組み合わせが適していると考えられる。
このような事象はヨーグルトメーカーでは自明の理として当然扱われていることでしょうから、我々が四の五の言うことではないのですが、知っておいても無駄ではないでしょう。