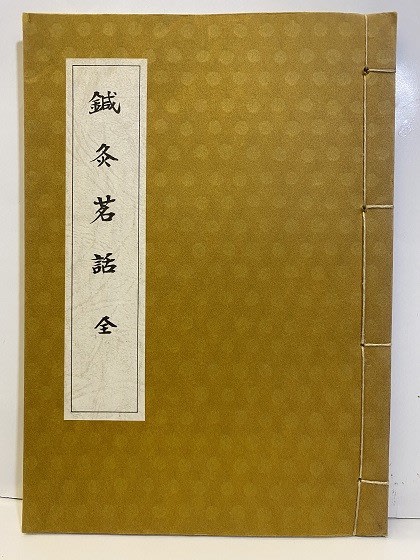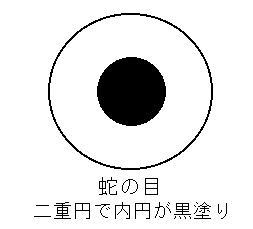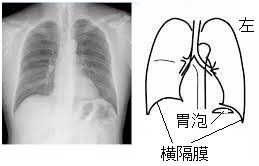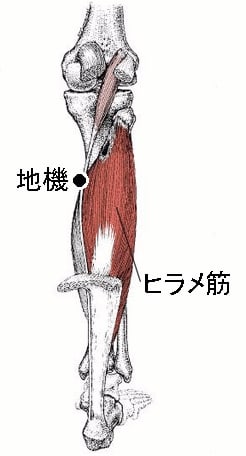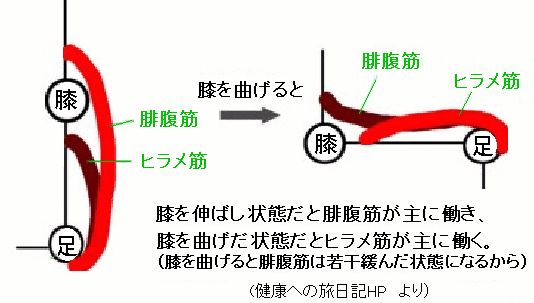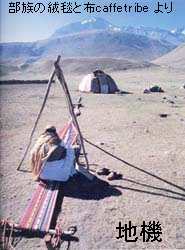1.「鍼灸真髄」を著した頃
代田文誌先生(以下敬称略)の鍼灸は、前半生が沢田流太極療法、後半生は現代鍼灸に変化したことはよく知られている。沢田健の神業のような治療効果に仰天し、心酔したことは「鍼灸真髄」に詳しく記されているが、文誌の年譜を調べてみると、沢田健の治療を初めて見学した時は、文誌は鍼灸免許を取得して、わずか1年しか経過していないことを知った。すでにこの段階で、沢田流を受け入れる下準備ができていたことに驚いた。
ところで沢田流太極療法とはどのような治療法なのだろうか。今となっては、その名前だけしか知らない鍼灸師が多くなってしまったので、その概要を解説する必要があるだろう。これは次回ブログに書くことにする。
2.科学派鍼灸への転向
また文誌の後半生は、現代鍼灸に変化したが、私は沢田健の治療である沢田流太極療法に見切りをつけた理由が知りたいと思うようになった。これについては「經絡論争」(昭和24~25年頃)の時期、經絡肯定派と經絡否定派との間で、医道の日本誌上で討論がなされたが、それについて文誌は次のように記した。
「古典を古典のままに学びとり、これを生ける人体に応用し、それによって古典の真価を証明するとともに鍼灸古典の中に伏在する科学性を見さんとしたと述べた、さらに古典を生ける人体に合わせて実験し、死物の古典を以て生ける活物の人体を読んで、古典の真意をすっかり体得してから、然る後に現代科学を以てこの生ける事実を批判し解刻し、そこに伏在する科学的真理を探り求めねばならぬ」
すなわち文誌の求める鍼灸とは、古典鍼灸ではなく科学的針灸だったことが理解でき、ライフワークとして鍼灸を研究する順序として沢田流鍼灸から入ったとみるべきだろう。
まさしく守破離を地でいった人であった。經絡論争にみる代田文誌の発言を、もう少し詳しく見ていく必要があるだろう。これは次々回ブログで書く予定にする。

上写真は、Data Chef によりモノクロ画像を、疑似カラー化した。
3.代田文誌年譜
<世に出るまで>
1883(明治16) 医制免許規則布告。漢方医排除された。ただし一般大衆に親しまれた鍼灸術は、一般の家庭で盛んに実施され続けた。
1990(明治33) 長野県飯田市の農家に生まれる
1911(明治44) 按摩・針術・灸術の営業取り締まり規則が発布。
1920(大正9)20才 正月に喀血、東京私立錦城中学校を結核にて中退。この闘病体験が以後の死生観に大きく影響し、仏門に入る。この年、マッサージ術、柔道整復術の営業取り締まり規則が発布。
1926(大正15)26才 早稲田大学文学部通信教育卒。
鍼灸術検定試験合格し鍼灸師となる。当時は針灸学校というものはなく、鍼灸師の元で4年間以上修業をしたという証明書があればそれが針師灸師試験の受験資格となり、試験を経て鍼灸師となることができた(鍼灸師免許という大層なものではなく業として鍼灸してもよいという鑑札だった)。代田文誌は飯田市の盲人鍼灸師の処で「4年修業した」というニセ証明書を書いてもらい、ともかく鍼灸師になることができた。今となっては考えられないことである。
(皮内鍼で有名な赤羽幸兵衛も、当時のカネで金5円で証明書を書いてもらった。)
※20才~27、8才まで、結核により長い療病生活を過ごしていた。
<第1期(沢田流鍼灸と現代医学の研修時代)>
1927(昭和2)27才 沢田健氏に師事(以降12年間。沢田健死去まで)、 同年母、やすえ死去
(沢田健氏の見学を見学し始めた段階では、ほぼ針灸臨床経験ゼロだった)
※沢田健は1877(明治10年)大阪の剣道指南の家に生まれた。青年時代に京都武徳殿で柔術を修業し、活殺自在の法や接骨術を習得。青年期、朝鮮に渡り、釜山で鍼灸治療所を開設。
1922(大正11年)、後に沢田健の門下生となる城一格氏の招きで、45才で日本へ帰国。城氏は沢田に鹿児島で針灸免許を取得させようとしたが、灸の免許取得はしたが針の免許は取れなかった(当時の都道府県の針師灸師の認定試験の合格率は20%前後)。東京で開業。関東大震災(1923)で一切を焼き尽くすも、再び小石川雑司ヶ谷にて治療院を再開。
※代田文誌著の沢田健治療の見学記「鍼灸真髄」は昭和2年~昭和12年のもの
1929(昭和4)29才 東大の医学解剖学教室で勉強(以降2年間)
1930(昭和5)30才 父、代田安吉死去(昭和2年の母の死後、父も生きる気力を喪失)
1931(昭和6) 31才 長野県日赤病院研究生(以降3年間)
昭和8年頃から東京は上野駅前の旅館「東洋館」で出張治療開始。月1回、治療日は一両日。
1936(昭和11)36才 長野に移転
1937(昭和12)37才 結婚(夫人の名前は、やゑ)
1938(昭和13)38才 澤田健は疔を背中に発病。同年61才にて死去
文誌は、この年より終戦頃(昭和20年)まで、茨城県東茨城郡内原村にある満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所の衛生課顧問として、灸療所の開設および開拓医学の指導を行なってきた。この施設で訓練を受けた者たちは満州へ送られたが、敗戦と前後してソ連軍が満州に侵攻したことにより、落命した者も多い。
<2期(GHQ旋風と科学派鍼灸の確立へ)>
1939(昭和14) 39才 代田文彦(元、東京女子医大教授)出生
昭和8年この頃、1944(昭和19) 44才 長野市で開業。倉島宗二、塩沢幸吉らと共同で臨床に従事(1966年, 代田68才)まで。代田文誌は、末尾が、7、8、9のつく日。すなわち月9日間担当。
他の二名の先生も同様に月9日づつ担当した。 この頃の東京出張は、東大正門前の新星学寮で施術。治療は6畳、2組の布団。助手を1~2名使って非常に多忙だった。治療費は初回500円、次回以降は400円。
もぐさ一袋30円。なお 同時期、長野市で行った治療代金は、初回170円、次回以降130円だった。
※新星学寮とは、篤志家H氏が主として優秀学生のために共同管理、共同経営した学生寮。
毎月、月初めの、一両日。東京以外でも松本・上田等でも出張治療。これは日帰り、または一両日の治療だった。
1945(昭和20) 終戦
1947 (昭和22) 昭和21年、日本国憲法制定に伴い、GHQは鍼灸禁止令を指示しようとしたが、
石川日出鶴丸(当時、三重医学専門学校長)は「鍼灸術ニ就イテ」という陳情論文を提出。また同年、代田は日本鍼灸医学会の再建を決意。
元京都大学生理学教授の石川日出鶴丸博士の門下に入り、求心性自律神経二重支配法則などを学ぶ。
1948(昭和23)48才 鍼灸術禁止令解除。日本鍼灸学会発足
金沢大学病理学教室石太刀雄博士の下で内臓ー皮膚血管反射の研究開始。
1949 (昭和24)49才 皮電計について研究開始。東京小石川にて開業
※この頃から約2年間、「經絡論争」が起こった。經絡否定派は、代田文誌、米 山博久。經絡肯定派は、柳谷素霊、竹山晋一郎ら。昭和25年米山はついに「經絡非否定論」を医道の日本誌上に発表。
1951(昭和26)長野県鍼灸師会初代会長(昭和40年まで)
1960(昭和35)日本針灸皮電研究会(現、日本臨床鍼灸懇話会)を発足
1967頃(昭和42頃)67才 東京の井の頭公園傍に移転し、針灸院開業
1974(昭和49)74才 死去