土がメタボになる理由。K
野菜の場合・・・
有機物は分解・発酵過程を経て、「硝酸」となった時点ではじめて
植物に吸収・利用されるとされています。
タンパク質 →アミノ酸 →アンモニア →亜硝酸 →硝酸
といった順番です。
したがって硝酸に分解するまでは効かない〔未分解の状態ならEC
メーターでも計れませんし〕。そこでありがちになるのは、
有機物をやったのに効かないな。足りなかったのかな。
と、ヒトにおもわせがちになること。ヒトがそう思って、さらに有
機物を施用してしまいがちになることです。
この行為がさらなる有機物の施用をよび、結果的に土をメタボ化さ
せる遠因ともなります。
さらに・・・未分解の有機物の大量施用の影響は、土がメタボ化す
るだけではとどまりません。
植物の根に障害をもたらします。その原因はふたつ。
■ 有機物の分解に伴う硫化水素やメタンなどの有害なガスの発生
■ 土中の有機物が分解されるときに生じておこる酸素不足
です。
その結果、お花や野菜の地下部が生育不良となり、その後地上部
の生育不良もひきおこしてしまうのです。
さらにここからです。
まだ有機物が足りないと思いこんで、さらに有機物を施用したら・・・
いったいどうなってしまうのでしょうね。
こういった有機物の分解の過程がよくわかるのは、水を貯めてみる
ことです。それまで見えなかった分解の過程で発生するガスが、見
えるようになりますよ。
ぶくぶくぶくぶく、ぶくぶくぶくぶく
つっつくたびに、アワ がいっぱい。
◎ たとえば水田。
水田に未熟有機物をたくさんいれた状態で、田植した場合には
水が温み始めるころからガスの発生が始まります。
そんな水田の中をハダシで歩くと、ガスの存在を肌で体感できますよ。
そんなとき思うんです。生き物たちのためにも、水中や土中に
酸素をいれてあげたいなって。
 「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」
「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」
野菜の場合・・・
有機物は分解・発酵過程を経て、「硝酸」となった時点ではじめて
植物に吸収・利用されるとされています。
タンパク質 →アミノ酸 →アンモニア →亜硝酸 →硝酸
といった順番です。
したがって硝酸に分解するまでは効かない〔未分解の状態ならEC
メーターでも計れませんし〕。そこでありがちになるのは、
有機物をやったのに効かないな。足りなかったのかな。
と、ヒトにおもわせがちになること。ヒトがそう思って、さらに有
機物を施用してしまいがちになることです。
この行為がさらなる有機物の施用をよび、結果的に土をメタボ化さ
せる遠因ともなります。
さらに・・・未分解の有機物の大量施用の影響は、土がメタボ化す
るだけではとどまりません。
植物の根に障害をもたらします。その原因はふたつ。
■ 有機物の分解に伴う硫化水素やメタンなどの有害なガスの発生
■ 土中の有機物が分解されるときに生じておこる酸素不足
です。
その結果、お花や野菜の地下部が生育不良となり、その後地上部
の生育不良もひきおこしてしまうのです。
さらにここからです。
まだ有機物が足りないと思いこんで、さらに有機物を施用したら・・・
いったいどうなってしまうのでしょうね。
こういった有機物の分解の過程がよくわかるのは、水を貯めてみる
ことです。それまで見えなかった分解の過程で発生するガスが、見
えるようになりますよ。
ぶくぶくぶくぶく、ぶくぶくぶくぶく
つっつくたびに、アワ がいっぱい。
◎ たとえば水田。
水田に未熟有機物をたくさんいれた状態で、田植した場合には
水が温み始めるころからガスの発生が始まります。
そんな水田の中をハダシで歩くと、ガスの存在を肌で体感できますよ。
そんなとき思うんです。生き物たちのためにも、水中や土中に
酸素をいれてあげたいなって。
 「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」
「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」 












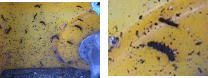 ← ポリタンクの壁面でも こんなふうに。
← ポリタンクの壁面でも こんなふうに。