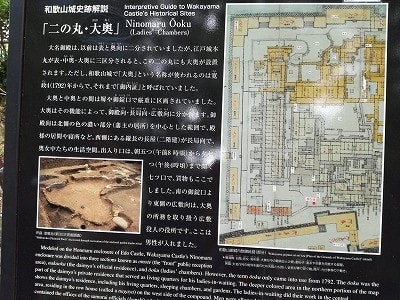鎌倉長谷寺@鎌倉市長谷 3-11-2。

大和の長谷寺とどのような関係なのか分からないが、十一面観音菩薩像(長谷観音)を祀る鎌倉・長谷寺を始めて訪ねた。

観音山の裾野に広がる下境内と、その中腹に切り開かれた上境内に分かれている。

高山樗牛住居碑 - 山門を入って左手に立つ。
明治期の思想家高山樗牛は病没する直前の1901年(明治34年)頃、長谷寺境内に住んだことがあり、1959年にこれを記念する碑が建てられた。

久米正雄胸像
1891年(明治24) - 1952年(昭和27)
鎌倉ペンクラブ初代会長、久米の3回忌にペンクラブによって設置された。

十一面観音菩薩像(長谷観音)が安置される観音堂。

「見晴台」からは鎌倉の海と街並みが一望できる。

鐘楼。
梵鐘(重要文化財)は観音ミュージアム内。
鐘楼には複製品が下げられている。

弁天堂の近くに、弁天窟がある。

シュウメイギクが咲いていた。

木造十一面観音立像(本尊)
像高9.18メートルの巨像で、木造の仏像としては日本有数。
造立年代は定かでないが、室町時代頃の作と推定されている。
左手に水瓶、右手に数珠と地蔵菩薩の持つ錫杖を持ち、方形の磐石の上に立つ。いわゆる「長谷寺式十一面観音」様式。

大和の長谷寺とどのような関係なのか分からないが、十一面観音菩薩像(長谷観音)を祀る鎌倉・長谷寺を始めて訪ねた。

観音山の裾野に広がる下境内と、その中腹に切り開かれた上境内に分かれている。

高山樗牛住居碑 - 山門を入って左手に立つ。
明治期の思想家高山樗牛は病没する直前の1901年(明治34年)頃、長谷寺境内に住んだことがあり、1959年にこれを記念する碑が建てられた。

久米正雄胸像
1891年(明治24) - 1952年(昭和27)
鎌倉ペンクラブ初代会長、久米の3回忌にペンクラブによって設置された。

十一面観音菩薩像(長谷観音)が安置される観音堂。

「見晴台」からは鎌倉の海と街並みが一望できる。

鐘楼。
梵鐘(重要文化財)は観音ミュージアム内。
鐘楼には複製品が下げられている。

弁天堂の近くに、弁天窟がある。

シュウメイギクが咲いていた。

木造十一面観音立像(本尊)
像高9.18メートルの巨像で、木造の仏像としては日本有数。
造立年代は定かでないが、室町時代頃の作と推定されている。
左手に水瓶、右手に数珠と地蔵菩薩の持つ錫杖を持ち、方形の磐石の上に立つ。いわゆる「長谷寺式十一面観音」様式。