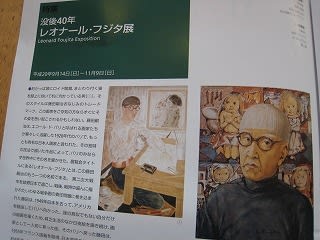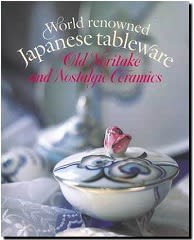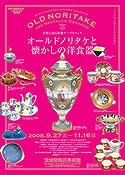六義園のライトアップ
11月22日~12月14日、夜9時まで開園。
12月14日で終了したが、駒込の六義園の「紅葉と大名庭園のライトアップ」を見る機会を得た。洗練された照明技術により幽玄の世界に遊ぶことが出来た。係員に「環境・照明デザイナーの漆原美代子さんが演出したのか?」と訊いてみたら、漆原さんではないが、照明デザイナーの手による、との事だった。
入場する際警備員が注意しているが、通路は点々と樹木の上、或いは路傍から薄明かりが灯り、余ほど気を付けないと危ない。一部は立ち入りが禁止されている。
ほのかに浮かび上がる光景は、東京に居ることを忘れ、あたかも夜の京都の庭園に佇む感じである。
水戸でも桜の季節に、旧県庁舎のお壕の前がライトアップされる。強すぎる照明は桜の花の美しさを台無しにしてしまう。
街路灯のみで充分なのに。
仲春と仲冬を比較することに多少の無理はあろう。六義園のライトアップはしっとりとした秋から冬へ情緒を感る事が出来た。
11月22日~12月14日、夜9時まで開園。
12月14日で終了したが、駒込の六義園の「紅葉と大名庭園のライトアップ」を見る機会を得た。洗練された照明技術により幽玄の世界に遊ぶことが出来た。係員に「環境・照明デザイナーの漆原美代子さんが演出したのか?」と訊いてみたら、漆原さんではないが、照明デザイナーの手による、との事だった。
入場する際警備員が注意しているが、通路は点々と樹木の上、或いは路傍から薄明かりが灯り、余ほど気を付けないと危ない。一部は立ち入りが禁止されている。
ほのかに浮かび上がる光景は、東京に居ることを忘れ、あたかも夜の京都の庭園に佇む感じである。
水戸でも桜の季節に、旧県庁舎のお壕の前がライトアップされる。強すぎる照明は桜の花の美しさを台無しにしてしまう。
街路灯のみで充分なのに。
仲春と仲冬を比較することに多少の無理はあろう。六義園のライトアップはしっとりとした秋から冬へ情緒を感る事が出来た。