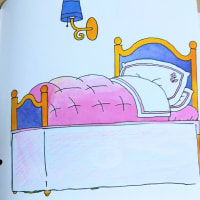金曜日の小学生国語クラスでは、5月の前半に2週にかけてこちらの本を読みました。
前半はマララ・ユスフザイさんの2013年7月12日の国連での演説。
そして後半は、それを踏まえて、石井光太さんが考えたことです。
戦争や貧困というと外国の話のような感覚を持つ方もいらっしゃるかもしれません。しかし、後半では、日本国内でも、貧困、差別、虐待、いじめといった、子供たちを取り巻く多くの問題があることが述べられています。
それを解決し、平和な世界にしていくためには、教育が大切であるということが述べられています。
本書に、
「戦争はいけない、と言うだけでは戦争は止まらない。
差別はいけない、と叫ぶだけでは差別はなくならない。」
とありますが、本当にその通りだと思います。
自分の考えを作り上げるためには、様々な価値観に触れ、その中から自分が望むものを選んでいく力が必要です。
学校では、得意なことも不得意なこともさせられ、気の合う人もいれば気の合わない人もいます。学校は勉強をする場でもありますが、色々な価値観に触れる場でもあります。
楽しい経験も苦しい経験も、大人になってみると両方大切だったと感じます。
そして両方経験した上で、やはり皆が楽しく幸せを感じられる世界が、望ましい世界だと思います。
そして、その自分の考えを誰かに伝えるためには、言葉が必要です。
その言葉を身につける場所が学校だと、筆者は述べています。
この本が書かれたのは2013年ですので、時代が大きく変化した今、筆者の意見が当てはまらない部分もあるかもしれません。けれども、自分の考え、言葉を持つことの大切さは変わらないと思います。
読み始めたときは、「難しそうな本だな~」という表情をしていた生徒さんたちも、いつのまにか真剣な顔で聞いてくれていました。
学ぶことの本質について考えてくれれば、嬉しいです。
にほんブログ村 ←いつも読んでくださりありがとうございます!ランキングに参加しています。クリックしていただけると嬉しいです!
塾教育ランキング ←こちらもクリックしていただけると嬉しいです!