建築・環境計画研究室
*当ページの文章や画像の無断引用・転載を禁じます*
*どなたでもアクセスできる,オープンスペースのみ,写真掲載していますが,転載はご遠慮ください*
仙台の多世代複合施設「アンダンチ」さんを訪問しました。

2階テラスからの見下ろし。中庭を囲んで,4つの棟(アンダンチレジデンス,看護小規模多機能,レストラン+保育所,就労支援+地域交流スペース)が建っています。
アンダンチは,仙台の方言の「あなたの家(あんだ・ん・ち)」にかけて,「あなたの「地(場所)」と,「知(知恵)」という意味を込めて付けられた名前とのこと。
お話しをうかがい,
・住まい(生活の拠点)である *ただし,ここで生活は完結しない
・地域の人々の居場所をつくる,活動の場を提供する
・学びをキーワードとして,成長と関係性の中での学び合いがある
というコンセプトがそのまま反映されているなと感じました。
こども,若者,高齢者,医療や介護・支援が必要な人もそうでない人も,様々な人々にとっての日常の中にある居場所となっています。
手がかりのある余白の空間がちりばめられていることで,そこを活動の場として見いだしたり,そこから新たな活動が生まれたり。活動を通して,自分の役割を見いだし,それが自己肯定感にもつながります。とてもすてきです。
敷地に入るとまず,ヤギがいます。このヤギの小屋は建築の学生さんたちと一緒に造ったとのこと。さすが山の羊,高いところに登る習性があるそうです,そんなヤギの習性を組み込んで設計されており,ヤギのくろごまさん,高い場所が定位置です。白いだいふくさんは日陰になっているスキマにいます。暑いですねえ今日は。

ランドスケープデザイナーの方が入られて,四季折々の表情のある草木,花や果樹が植えられた豊かな庭。「造ってみてあらためて思ったけど外構大事! 地域との接点になる空間なので,外構がウェルカムって言ってないと入りにくいですよね」とのこと。本当にそうだと思います。
その場所に来た人が一番最初に見るのは外構ですから。だから団地再生を外構から始めましょう!という提案でリデザインされた左近山団地(STGK:熊谷玄)でもそのようにおっしゃっていました。

子供が遊びたくなる仕掛け。正面に見えるのは「アスノバ」。

地域の方がちょっとお散歩に来たり,「レジデンス(サービス付き高齢者向け住宅)」の方が外に出られたりするときにも使われているベンチ。イベント時にも大活躍。居られる場所を提供する=ウェルカムですよ・ぜひここに座ってゆっくりしてくださいと環境が発信することの意味を再認識します。

路地的空間,奥まできれいに見え隠れの空間が作り込まれ,奥性を感じられます。

レジデンス(サービス付き高齢者向け住宅)の入口には駄菓子や「福のや」があります。1階のラウンジスペースは,こどもたちが駄菓子を買って,溜まって遊べるスペースにもなっています。こどもたちが騒がしくしていると,入居者さんが「うるさい!」と一喝するシーンもあるとか。公共の場での集まり方・楽しみ方を学ぶ,社会性を身につけるための場にもなっているのです,とのこと。「和気あいあい」だけではない,生の関わりですね。本当に大事。
多様な居方のできる,畳のスペースやソファスペース,テーブルなど,素敵な家具が置かれたラウンジスペースや食堂は,子育てサークルや地域の子供の活動の発表場所,放課後のこどもたちの居場所,趣味や生涯学習の場など,地域の方の活動の場としても活用されています。まずは気持ち良く「ただ居ること」ができる,「余白」があることで,活動の場として見いだされています。
こうして多世代の交流(直接的にも,間接的な居合わせの意味でも)の場が実現し,高齢者の方と,こどもたちとが世代を超えて関わることができる。2018年7月にオープンして,お看取りもすでに経験されたそうです。
こどもたちは,人生の完成期にある人々の姿を近しく見聞きすることで,人生は有限だよ,そのなかでなにをするの? ということを考えさせてくれる。それが高齢者の最期の大仕事でもあるのではないか,と。
このお話しには大変感銘を受けました。ある人が,その人生を完成させること,そこに次の世代が寄り添うことは,そのこと自体が見送られる側にとってもひとつの「お役目」と言えるのではないか。それは人々を見送っていく側にある(調査先等でいろいろな方と関わり,そして見送ってきました。近しい人をゆっくりと見送る日々でもあります)と思っていた身としては救われる気持ちがします。見送られることにも,すばらしい価値がある。それを完成させるのは関係性である。
(誰でもアクセスできるオープンスペース以外は写真アップ&レポートしないので,レジデンスの方はここまで!)

就労支援+地域交流スペース「アスノバ」の物販コーナー。障碍者の制作等の販売スペースとして始めたところ,地域で趣味のものづくりをしている方たちが,自分たちも作品販売の場が欲しい,ということでレンタルスペースとしても活用することになったそうです。(この振り返りも素敵なカフェのようなスペースなのですが,ご利用者さんがお食事中でしたので)
で,またそのネットワークが口コミで拡がって,「アンダンチ」の利用者の拡がり(知っていただく,来ていただく)につながっているとのこと。
講義などで「売り買いはエンタメ」とお話ししていますが,やっぱりそうですよねと認識を新たにします。メルカリ,minneなどネット活用のサービスもそうですが「つくる」「うる」「みつける」「かう」楽しいです! 「つくる」「うる」は,利用者であり,主体として関わる者でもあるという点で,主体的「活用者」を拡げる活動ですね。

自然食レストラン「いろは」さんから庭の方向を見る。


美味しい「寝かせ玄米」の定食をいただきました。三種類の玄米ごはんから,おかわり自由。もっちもちで美味しいです。
炊いてから3日寝かせるからこそのこの食感!という店内の説明文章を読んで,「天の星は昔の光」って詩があったね‥という話題など(そこまで昔じゃない)。



ロゴもとってもオシャレですよね。「デザインで“福祉”との心理的距離感を縮める,親近感を持ってもらう」というきもちで,グラフィックデザインも建物も,考えていくことが大事だと,関わったデザイナーさんたちとのグループで議論されたそうです。「デザインで心理的距離感を縮める」,とても心強いワードだと思います。
「福祉施設ってどうしてもちょっと違う場所だっていう感じがありますよね‥拒絶されているというか,自分たちとは違う世界だというか。自分が設計に関わるまではそういう印象がやっぱりありました」という,ご参加の設計者さんの感想が印象的でした。
それは,ご利用者さんたちを守りたいということだからというのは勿論です。「オープンにすることで守る」「地域の目を入れることで守る」という“積極的な守り”って,でもまだ一般的ではないですねと。“開かれた学校”についてのせめぎ合いとも共通します。
①オープン,②シェア,③混在。共生コミュニティのキーワードはこの3つに集約されるのではないかという仮説で議論をしています。
今回また,その議論が深まりました。

ありがとうございました。とても勉強になる,また楽しい時間でした!
はじめに,以下は幅広い計画系の一部に位置する,また大学に籍を置く研究・教育を業とする筆者の個人的見解であることをお断りいたします。
建築学会の会員誌「建築雑誌」の編集グループから,「研究と設計の関係について,建築計画の研究者の立場から寄稿してください」というご依頼をいただきました。2018年の9月号に掲載された記事です。もともとは研究者と設計者は別れておらず,研究と設計を両方やっていくことが基本だった。そこから,役割・活動範囲が分化していき,研究者でもある設計者,設計者でもある研究者の割合は少なくなった。もう一度,研究と設計を統合的に捉える必要があるのではないか。そういった問題意識のもとでの寄稿依頼でした。今の,計画分野ならではの状況と課題認識についても盛り込んでください,というリクエストもありました。
そのお題に対して寄稿をしましたが,分量の制限があり(編集とレイアウトのご都合があり,3段階くらいで減っていきまして),カットした部分がかなりあります。せっかくなので,加筆してフルバージョンを残しておこうと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
研究者と建築家。そう呼べばそれらが異なるように聞こえても,両者は根本的には「建築の職能者」グラデーションのなかに定位する位置と広さの違いに過ぎないと考える。設計の対象は大小の建築物全体に加えて,インテリア,テンポラリ空間,使いこなし,コンセプト,制度や仕組み,ガイドライン,イベント,まち・・と多様である。それらの実践を大きく捉えると,開発・製作・技術や専門的知見の橋渡しなども含まれ,これらに一切関わらない「研究者」は逆に珍しい。設計者や事業者選定(の支援)などもまた,専門的知見や技能と社会の橋渡しにあたる。一方,建築計画分野を顧みれば,拡大の時代に分化した専門分野が複合化・多機能化によって再統合されていく時代にあって,また人口と居住域の縮小が起こり社会支援の統合化も進むなかで,各職能者個々の定位エリアは拡大を免れず,多面的展開が必要になる。例えば従来の施設類型ごとの研究,その類型だけの研究という取り組み方はとても困難になっている。
その加速する変化の中での研究と設計の関係を考えると,同時に,自己研鑽を含む教育や次世代育成を無視できない。新たな人材や視点が導入され続けなければ,その分野は衰退し消滅する。建築の職能者個人や組織は,研究・設計・教育を3枚羽根とする風力発電機のように,ニーズや社会的課題という風を受けて価値を創造する。3つのバランスは多様であってしかるべきだが,極端に偏りがあれば創造の効率が悪く,強い風でしか動けない。

写真:3枚羽根の風車。(フリー素材)
一方で,大学の研究者の多くに社会貢献として実践の比重を高める圧があることを危惧してもいる。研究成果を活かした研究者自らによる実践活動は,大学や研究,研究者の成果や価値を視覚化しやすい。もちろん,実践活動を通して研究にリアリティのある進展が見込め,その価値は高い。だが皆が二兎,三兎を追えば,あるいは追わなければならないと強制すれば,結局は研究も設計も追求しきれないこともあるだろう。知識や技術が高度化・複雑化するなかで,幅広い研究や実践,教育を一人ですべて突き詰めることは不可能だ。その意味で,連携して3枚の羽根を成す体制が必要である。
現実的には,自分の強みとなる研究・設計の分野を芯に,他とつながるための手(興味関心,共通言語としての最低限の知識や技術,敬意)を持つ「連携できる職能者」は強い。つなぐこと=ハブ機能そのものも重要な職能である。
また敢えて言えば,自分は大学では一度は研究にしっかり取り組める体制をつくりたいと考えている。設計課題や長期インターンシップは必須になっているカリキュラムが一般的である。一方,研究による本質の探究や,そもそもを考える力と技術の獲得は,その実現のためのデザインの選択肢の拡がりや,他の研究分野への興味や基礎知識という手を増やすことにつながる。
結論として,個人の職能領域の広さもさりなん,相互補完できるサブスキルをそれぞれが持つ戦士(設計に強い人),魔法使い(研究に強い人),ヒーラー(教育に強い人)のそろったパーティが強い。いかなる勇者も,1人では強敵に勝てない。全員が“すべてできる”“バランス型の”賢者を目指す必要もない。それぞれの得意が突き詰められていくなかで,新たな展開や突破口が生まれる。
学会はさしずめ,こうした様々な得意をもつ職能者たちの出会いと別れ(新たな連携)の場である。

図:Quest of RED (This is some kind of game to advance with balanced Parties of Research, Education and Design)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
賢者の石は,一般的には赤いものだと思われているようですね。合わせてみました!

【羽田空港にて】
空港を見て、「おっ、公立刈田綜合病院の外来受付&待合みたい!」と思う反転現象。 pic.twitter.com/oLgleH99PI
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月10日 - 20:48
エントランスホールと一体になった外来受付・待合は,空港の出発ロビー・チェックインカウンターホールをイメージしているそうです。
【クアラルンプール国際空港にて】
エリンギ pic.twitter.com/miilmAHshn
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月11日 - 07:13
トイレのサインで男女の色分けをするのは日本風、世界共通ではない。…ここ、クアラルンプール国際空港メインターミナルでは、サインはモノトーン、タイルは色分けされてます。日本の会社でしょ、と思ったら、黒川紀章氏設計、メインターミナルの施… twitter.com/i/web/status/1…
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月11日 - 07:18
夜明けの定点観察 pic.twitter.com/feTu11qXYo
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月11日 - 08:22
飛行機の乗り継ぎで,4時間ほどのんびり過ごしました。
【コタキナバル国際空港,コタキナバル市内にて】
コタキナバル国際空港。両方、青い。 pic.twitter.com/2PXGDKhPUf
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月11日 - 14:29
いまグッといける分だけどうぞスタイル、底が三角の紙コップ。これお酒でやるとあの勝負する系のやつですよね pic.twitter.com/OHplVQV27i
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月11日 - 15:44
火事でも飛び降りない方がいいと思うんです pic.twitter.com/XMtWTEcKGK
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月11日 - 18:54
道路面フルオープンのショップハウス・レストラン、道に目一杯はみ出して屋台風に。飲食とまちが近い、近いどころか一緒になっている。茶柱立った pic.twitter.com/HMSW4JbE8z
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月11日 - 20:18
道の車通り抜けをやめて(?)フードコートにしている。地図で見ると道。飲食は生活の場面にして、人が集まる仕掛けでもある、ということが形になっている。(マレーシア、コタキナバル) pic.twitter.com/0b6QnEYNWm
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月11日 - 20:23
中央分離帯を挟んで、半分ずつ歩行者信号が青になるルール。曲がってくる車と歩行者の接触が少なくなる?(中央分離帯に人がたまるのだが)「半分、青い。」 pic.twitter.com/U4e2rrMvDy
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月11日 - 20:26
こんなところに日本人…というしるし、点字ブロック(視覚障害者用誘導ブロック)。この交差点にだけあった。 pic.twitter.com/xfLClp6hzp
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月11日 - 20:28
視覚障害者用誘導ブロック(点字ブロック)は,日本発の文化/バリアフリーデザインの設備。
他の国でも時々見ることがありますが,「途中で切れている」「なぜそこだけ敷設した??」「誘導ブロック(線状ブロック)と警告ブロック(天井ブロック)の使い分けが違う」「柱にあたる」「そもそもなんのために置かれているかよく分かってないらしい」といった光景とセットで発見されるのがしばしばです。ぜひ観察してみてください。
引いたらばしゃーって出てくるんじゃないかと怖くて引けない取っ手。溢れるビールを恐れぬ者だけがこの扉を開けるがよい。 pic.twitter.com/l871sFyYU3
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月11日 - 21:12
とてもリゾーティな景色ですが、これはお昼の場所。それ以外は普通にカンファレンスルームで発表を聞いてます(それは普通に普通の素敵なお部屋で、そして寒いです)
もうプール飛び込みたい pic.twitter.com/w8gcm6TYkr
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月12日 - 13:48
プレゼン終えてお出かけ。市場。野菜、果物、乾物、お菓子、屋台とフードコート…活気がある、そして安い(写真は人がなるべく写らないように撮ってます)。リサイクルのお店があるのが特徴的、その場で仕立てている。欧米などから買い付けて、アジ… twitter.com/i/web/status/1…
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月12日 - 20:28
買いたいなー、料理したいなーと思いますが…今回の宿はキッチンないのでアキラメ。いつもはミニ包丁とかの現地の食べ物を楽しもうセットを持ってくるんですが今回は準備の余裕がなさすぎた。買えるのは包丁いらないランブータンくらいかな、1キロ… twitter.com/i/web/status/1…
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月12日 - 20:31
フードコート。共働き世帯が多く、家で料理するより外食が安いので、外で食べる人が多いとのこと。家族で召し上がってるグループもたくさん。テーブルの上のココナツは、風が吹いたとき用の「おもし」だそうです。重いものねココナツ! ムスリムが… twitter.com/i/web/status/1…
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月12日 - 20:35
ナイトマーケット。日中は駐車場で(駐車場が慢性的に不足しているそう)、出店は夕方から。狭い、密度高いマーケットも、広いマーケットもある。衣料品、アクセサリ(時計、カジュアルな宝石、靴、鞄、帽子など)を扱う。テンポラリな機能の出現で… twitter.com/i/web/status/1…
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月12日 - 20:54
かに、えび、貝、魚、知らない青菜の炒め物、揚げ卵豆腐?などなど…美味。民族ダンスのショーも拝見しました。マレーシア全体で多いマレー系、中華系、インド系に加えて、ここボルネオのSABAH州ではカザダンドゥスン族、漁業民のカジャウ族が… twitter.com/i/web/status/1…
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月12日 - 22:44
海辺のオープンスペースが等間隔スポットでした。 pic.twitter.com/QCNzN4z6JV
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月12日 - 22:47
「鴨川アベック等間隔の法則」については, 森田孝夫,京都・鴨川河川敷に坐る人々の空間占有に関する研究 On Territorial Behavior of the People Enjoying the Evening on the Bank of the Kamo River,日本建築学会 学術講演梗概集. E, 建築計画, 農村計画 1987, 745-746, 1987-08-25 をぜひ読んでください。森田先生最高。
そして三日月と星。三日月うつりませんけど🌙のかたち。 pic.twitter.com/MoZrGjkDyu
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月12日 - 22:50
海上の町。漁業民のカジャウ族の集落。「桟橋」状の道と、家、という構成。時々、集会スペースになっている小屋も。町の「基本的構成要素」について考える… pic.twitter.com/h2KSP1r1TG
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月13日 - 18:31まちなかに引き込まれた海水の上で暮らす集落もある。こちらは、海水の循環が不十分で水質汚染が発生し(水が黄色くなるとか)てしまうこともあるとのこと。 pic.twitter.com/hwzGZZu2dH
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月13日 - 19:28こちらは河口近くの水上集落 pic.twitter.com/Yng6TohEWs
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月13日 - 19:29こんなところにひよこさんボート… pic.twitter.com/3FasUUXCqX
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月13日 - 19:30マングローブの林。この林に囲まれた汽水域で、カキなどの養殖、漁業をしながら暮らしている集落。 pic.twitter.com/FxK5V85ryL
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月13日 - 19:35サンセットビーチ。南シナ海をのぞむ浜辺。 pic.twitter.com/iRy2ujc5s5
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月13日 - 19:35学生たちですが、背景も良いので立っているだけで絵になりますね pic.twitter.com/zEU6SsBPUV
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月13日 - 19:37歌詞『椰子の実』
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月13日 - 19:40
名も知らぬ 遠き島より
流れ寄る 椰子の実一つ
故郷の岸を 離れて
汝(なれ)はそも 波に幾月(いくつき)
旧(もと)の木は 生いや茂れる
枝はなお 影をやなせる
われもまた 渚(なぎさ)を枕
孤身(ひとりみ)の 浮寝(うきね)の旅ぞ実をとりて 胸にあつれば
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月13日 - 19:41
新(あらた)なり 流離(りゅうり)の憂(うれい)
海の日の 沈むを見れば
激(たぎ)り落つ 異郷の涙
思いやる 八重の汐々(しおじお)
いずれの日にか 国に帰らん
(作詞:島崎藤村、作曲:大中寅二)
worldfolksong.com/sp/songbook/ja…こういう風景か!ていうの初めて見ました twitter.com/yamada__asuka/…
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月13日 - 19:42
おおっ、珍しい。遠目からのサインはモノカラーなのに近づくと男女色分けトイレサイン発見(スリや・サバ) pic.twitter.com/7yHOMawH2X
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月13日 - 21:52…と…思ったけど
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月13日 - 21:52
…後付けかなこれ?
色分けのサインは後から紙ぺらに印刷して貼ってあるだけだ pic.twitter.com/Ku1WI5s9s0寿司屋がいっぱい…やっぱり、和風の文化を持ち込んだんだなー pic.twitter.com/ltYwfdkaxw
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月13日 - 21:53(あとから、という意味です)
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月13日 - 21:58
全く何も見えないと思いますけど、
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月14日 - 00:52
空一面の星、三日月がかかるマングローブの林の中の川をゆき、
チラチラとまたたきながら飛び交う蛍を見てきました。
全く何も見えないですね。写真や動画やレコードに残せないことはなんて多いんだろ。 pic.twitter.com/rZVHXDlrPI
海外出張(地方でもだが、より移動コストが大きく機会の少ない、の意味)で、学生さんに行きたいところには行ったか、食べたいものは食べたか、買いたいものは買えたか、見たいものは見えたか、を気にするのは、学生時代のトラウマのせい。最初の国際会議が「え、あれ?」続きで、反面教師になった。
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月14日 - 22:49
本当,良い勉強させていただいて。20年弱経ってもネタになるくらいでありがたいです。きっとあと20年は言ってると思う。最初の刷り込みって大きいわ・・
ホテル近くの店で最後の日のディナーを堪能。
エビ、チリクラブ、子羊のペッパー炒め、揚げ豆腐あんかけ、ローカル野菜の炒め物(サバ・ベジタブルと言われたがよくわからない)、スイートサワーチキン(酢豚の鶏バージョン)、カキのニンニク・パクチーソース蒸し、どれも美味しゅうございました。
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月14日 - 22:58
島崎藤村(しまざきふじむら)は、島崎不二雄(本名:同じ)と藤村素雄(本名:藤村智生)との2人による詩人、小説家、漫才コンビ。1897年結成。ボケ役の島崎に藤村が冷静にツッコミを入れるスタイル。持ちネタは「話の流れが千曲川〜」「まだ… twitter.com/i/web/status/1…
— 子供相談室 (@out0724) 2018年9月15日 - 08:58ショッピングセンター、KK(コタ キナバル)PLAZAのトイレサインは赤字に白抜き。先日のショッピングモールはショッキングピンクに白抜きだったけれど、「過度に、色に意味を与えている」文化圏ではできないカラーリング。 pic.twitter.com/VoS1pTKsUt
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月15日 - 09:42コタキナバル国際空港、通ったなかで一箇所だけ内側の壁のに男性=青、女性=赤、の配色を発見。サインは全てモノ・カラー。 pic.twitter.com/wFEONJGyXL
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月15日 - 13:31クアラルンプール国際空港。赤青タイルでないトイレもあり。サインはいずれもモノ・カラー。ユニバーサルトイレは、緑のカラーリング。(施工会社の違い?和風カラーリングからその後改修された?詳細不明ですが) pic.twitter.com/zJungvcKj1
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月15日 - 13:47エリンギ、そしてたくさんのエリンギ。 pic.twitter.com/3pDroBU1ty
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月15日 - 14:05トイレの使い方についてのお願い、の掲示。かわいい。 pic.twitter.com/a7WgEe0OoO
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月15日 - 14:26
あー、ザ・ニホン。 pic.twitter.com/Oj5WUEdnPi
— やまだ (@yamada__asuka) 2018年9月15日 - 23:07
このトイレの性別と対応させた色分け,「わかりやすい」ので良い工夫ですねと思っていたんですけど(実際,10年前はそう教えていた),今のご時世に合っているか,今の価値観と対応しているかという観点から,あんまり良くないなと今は思っています。男女共同参画社会をめざし(まだ実現できてない),セクシャリズムへの反省が浸透してきた時代。小学生のランドセルも男女好きな色を選べるようになっている時代。好きな色の鞄,今日の気分の色の服を自由に選べる時代,LGBTへの理解も進みつつあるこの時代に,男は青・黒。女は赤。という固定概念を公共の建築物やサインが植え付けてくるこの国のサイン計画は,ちょっと立ち止まって考えてみたりしないのかしら,と。
ラフなレポートです。
廃校舎になった学校,学校の余裕教室(児童・生徒数が設計時点よりも少なく,結果として余っている教室)を活用しようという動き,以前からありますがここ10年くらいで聞く頻度が上がったように思います。
当研究室でもいま,「学校改修型の特別養護老人ホームでは,(もともとそれ用に設計されているわけではないので多少の無理もあって)介護者の負担感は大きいのだろうか?」という検証型研究のテーマが一つ,動いています。
ちょっと面白い学校改修・用途転用事例があると聞くと,「え?じゃ見学に行きます。いつがいいでしょう」状態で過ごしておりますが,先日また一つ拝見したのでそのレポートを。
同行された先生と,道中で建築計画研究はどこに行くのか‥という議論があったのですが,ますます「利用」に向かっていくのでしょう。というのが小職の返答でした。
それは従来の「使い方研究」となにが違うのかということも重ねて議論になりましたが,「新築建築物の検証と,次の新築のための素材集めとしての使い方研究」から,「その(種の)(既存)建物のなかでの使い方≒カスタマイズ,現状をもとにした改良・リカレント」の比重が高くなっていくのかと。
それに対して,「それってインテリアなの?」というご質問もあって,「そもそも,建築とインテリアを分けることはできないのではないですか,少なくとも包含関係で。建築ってソフトからハード,人間の心理・行動デザインからストラクチャーまで複数の軸による幅広いグラデーションの総体だと思いますけど‥」というちょっと曖昧な返答をしました。
「それ(利用者と建築物を経時的につなぎつづけるデザイン)ってインテリアなの?」
うーん‥どう考えますか?
はい。
今回お邪魔したのはこちらです。「道の駅 保田小学校」。

「買う(地場特産物の販売),食べる(飲食施設),泊まる(宿泊+入浴施設),知る(情報発信拠点)」の機能をもつ都市交流施設へと生まれ変わった小学校校舎,です。
コンペで早稲田の古谷誠章先生を代表とするN・A・S・A設計共同体が選定されて実施された事例,首都圏大学研究室連携で,多数の研究室・学生さんが関わったようです。

地域の主要道路(内房と外房をつなぐ幹線道路のひとつ)に面した立地だったので,道の駅としての再生が可能であったという,立地特性を活かしたプロジェクトとお見受けしました。
外房の側のエリアでうかがったのですが,この「道の駅 保田小学校」ができたために,バイパス完成で遠のいてしまった人の流れがこの幹線道路にも戻ってきた,とのこと。

小学校舎としての外皮に,一皮「まちの縁側(2階)」兼1階の庇の役割の構造体を重ねています。

ここは1階の商店へのアプローチ空間や,外構との緩衝領域になっています。

角度を変えると学校らしい雰囲気にも見えます。

お店のディスプレイに活用されている跳び箱。
「え,備品の除却申請はしてあるよね」などと思う程度には毒されている。

おくればせ。全体はこんな感じです。

水飲み場がそのまま(周囲はちょっと盛って平らにしてあります)残っていたりはノスタルジーを誘います。

旧校舎2階。宿泊施設として使われています。

元々の教室を2つに割って,4人部屋として提供されています。

宿泊施設+入浴施設(日帰りでも利用可!)はオープンにご利用いただけるとのことで,利用者も多いそうです。
建築系大学の方,ゼミ合宿にどうでしょう。
教室棟の2階教室群→宿泊室,の南側に増設された箇所には,「まちの縁側」が設けられています。

宿泊室のすぐ外側なので,どうだろう‥というところもあるかもですが,17時までの利用となっています。時間帯で棲み分け作戦です。

進んでいくと,旧校舎の外皮をそのまま活かしていますので,校章が見えたり,時計が見えたりします。

この角度で見ないものなので新鮮。
外皮側に設けられたパネルは可動式で,蓄熱ボードを兼ねているとのこと。

ちょっと面白い警告。掲示物は「保田小学校校長」の名前で出されているので。

ブーゲンビリアですね,綺麗な花ですが

確かに痛い。引っかかれました。警告意味なし

旧体育館は,物産館に使われています。

中は地産の美味しいもの素敵なもの,の直売所です(お客様が多かったので写真はNG)。
体育館の骨格だけ残してあと改修なので,全く違和感ありません。

学校にはつきもの,の金次郎さんがいたり

学校らしさと,また違う場らしさと,共存を感じられる事例でした。
神戸の北野☆工房のまちでもそうでしたが,


「学校らしい単位空間(教室)」はそのままでも,商業施設の場合はそこからのあふれ出しや開口の雰囲気づくりで感じがかなり変わります。
こちらは中廊下型なので,片廊下型の保田小学校よりも廊下(内観)には商業施設の感じが出しやすいようです。

逆に教室らしい雰囲気を活かした利用をしているブースもあります。


歴史を残す観点でも,改修利用らしい意味を強調するという点でも,「学校らしさ」は残したい。けれど残りすぎると新しい用途となじみにくい部分もある場合も。「らしさ」をどこに落とすかは重要ですね。商業施設ではそのあたり,「ノスタルジーをウリにしたテーマ型商業施設」もあるなかで比較的納まりが良さそうです。
生活施設だとどうでしょう? 特別養護老人ホーム,サービス付き高齢者住宅,などに改修される例もありますがそのあたりだと。「学校や病院のよう(な全制的施設)に見える入居型高齢者施設,は新型特養に至る従来型施設への反省の表現としてしばしば用いられてきました。このへんはポイントになりそうです。
外観は商業施設にしては開口部が少ない,出入り口が限られる,という点でフラッと入店,を誘いにくいという面はありそうです。北野は。
保田の場合は,入口動線が車出入りに限られる→動線処理がしやすく安全,敷地内では1階店舗への入口を元テラス型だった形状を活かし,外廊下型として再整備したので出入りしやすい,という状況です。
一口に学校といっても,構造も立地もそれぞれなので,新しい用途との組み合わせでは考慮すべき点が違いますね。
そんなことを思った見学でした。ありがとうございました。



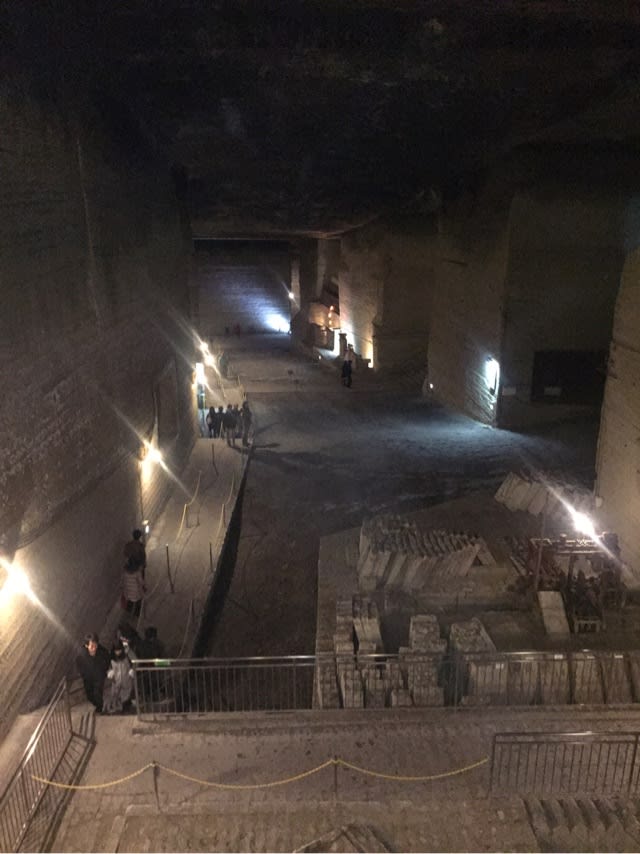


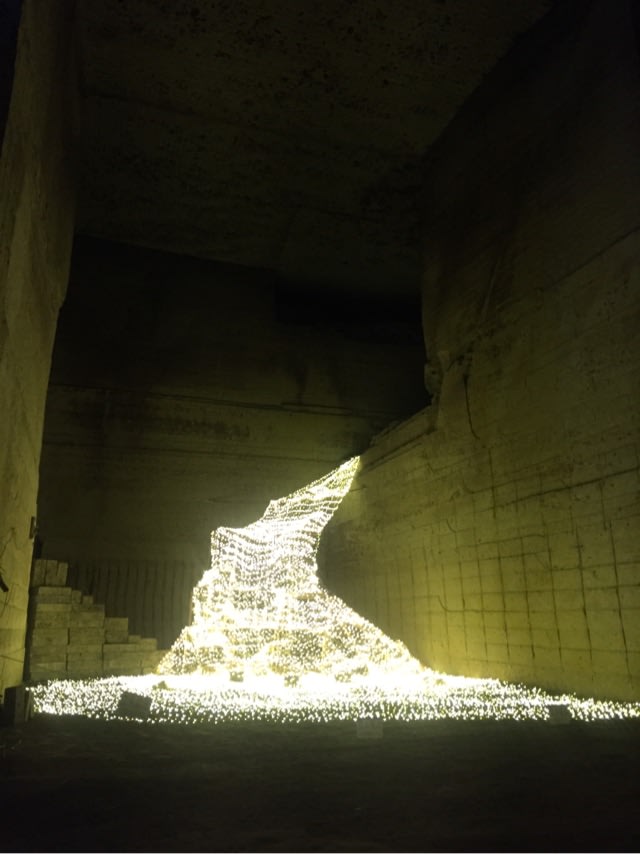


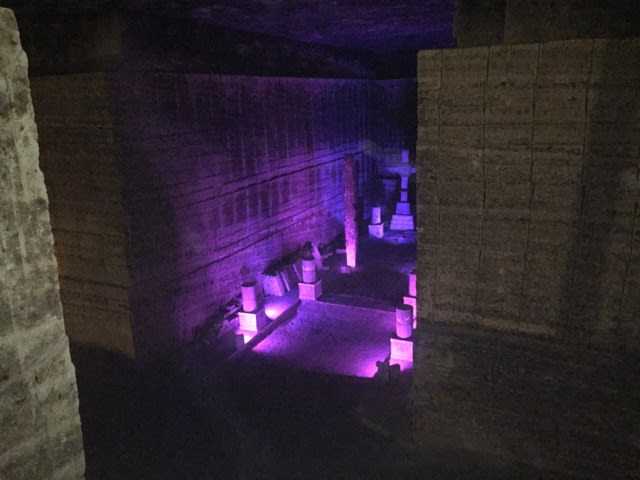













「♪ 京の五条の橋の上」で始まる「牛若丸」の舞台,五条大橋は京都駅の北東方向,鴨川にかかっておりますが

(googlemap)
今日は京の五条の横断歩道橋の話です。今日・京・橋。
福祉転用京都会議の,見学会会場の下見,会場との事前打ち合わせ・準備の日に,福祉転用・コミュニティ研究の関係で団地をいろいろ見て回る時間をつくれました。
その話はまた別として,その移動中に「へえ,そうなんだ」がいろいろあった橋の話。
五条通を歩いておりますと,

たまたま時間あるよってことで,一部ご同行いただいた都市デザイン研究室の先生が「おお,あれは面白い」とおっしゃる。
「なにが面白いですか?」

この歩道橋だそうです。
「え,どこが??」
「橋脚の繊細さ,リベット留めの意匠,橋桁の薄さ・手すりの低さによる見附のシュッとした比率,マンション側への配慮として取り付けられている見切り板・・(延々)・・・」
「あー…そういうものですか…」
都市デザインの分野と,建築計画の分野の目の付け所の違いというか,ちょっと目から鱗でした。
さらに進むと交差点に架かっている歩道橋がありまして,

同じ意匠です。きっと五条通の拡幅の際に,一斉に架けられたのでしょうね。
「設置基準が変わったんだな,あとから手すりがつけられてる。やっぱりこういうデザインは今はできないですよ」
「え,なんで分かりますか?」
「ここ」
「?」

「橋の銘板の上に,手すりが来てるでしょう」
「あー,なるほど。先生,ちょっと建築探偵みたいです」
登ってみますと,

確かに見附が薄いので。シュッとしていて見通しが利いています。
美しいなって気持ちがしました。
「そして確かに手すり低いですね。」

「でしょう,落ちそうでしょう。僕の半分くらいです。今はもうこの基準は変わってしまっているので,こういう歩道橋はもう作れません」
(先生は背が高くていらっしゃるのでちょっとアンフェアな気がしますが)
「はい,手すり低いですね。既存不適格ってことですね」
「あとはっきり言ってめちゃくちゃ揺れますね」

銘板がありました。
「1965年の歩道橋指針」基準でつくられた,1970年3月竣工の歩道橋だそうです。
46年前。それは頑張ってきましたね。
あと個人的に面白かったのが,

バイクマーク,それ?
スクーター専用? そうなの?
あと,届きそうで届かない

アアアアア なんとかしてあげたいけどどうにもならない

この照明は,納め方がちょっと当初設計じゃなさそうだから,後付けされたのかなあ。
などと写真を撮っていたら,通りかかった老夫婦に「何の写真を撮っているのですか?」と訊かれました。
ええ,気になりますよね。そうですよね。
「イヤこの歩道橋,古いデザインなんですけど,今だと基準が変わってしまってこういうのつくれないので。面白いところが色々あるなと思って」
「ああ…そういうものですか? 普段見ているけど気付かなかったな」
「そうですねえ,身近にあると当たり前で気付きにくいことってありますよね」
「そういうお仕事をなさっているんですか?」
…“そういうお仕事”? …まあ,大局としてはそうかな…?
「あ,はい,そうですね。建築関係で」
「いつ本が出るんですか?」
「「本?」」
「まだちょっと…出版の目処はついていないんですけどね」
「あ,そうですか。じゃあ,がんばってくださいね!」
「ありがとうございます!」
「…励まされてしまいました」
「励まされてしまいましたね」
「若干誤解されてしまいました。…じゃあ,がんばりましょうか」
「がんばりましょう。え,何を?」
「調査の本筋に戻りましょう」
「ですね」
というわけで京の五条の橋の上のお話はこれでおしまいです。
あのすれ違った老夫婦も含めて,居合わせたひとたち“それぞれ”,見るところが違うなあ。
同じ世界に居合わせても,それぞれの環世界(Umwelt)のなかで生きているんだな,見えているもの感じているもの読み取っているものすべて違うんだな。
という,出会いとすれ違いと気づきの物語でした。
(参考)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
京の五条の橋の上
大のおとこの弁慶は
長い薙刀ふりあげて
牛若めがけて切りかかる
牛若丸は飛び退いて
持った扇を投げつけて
来い来い来いと欄干の
上へあがって手を叩く
前やうしろや右左
ここと思えば またあちら
燕のような早業に
鬼の弁慶あやまった


















時々冷たい雨が降るけど,あたたかい日差しに満ちあふれるようにするのが設計の醍醐味ではないでしょうか。
どうもです。
研究の打ち合わせで,カッコイイ大学キャンパスに来ました。


巨匠の作品です。
カッコイイ。
よくドラマのロケに使われるそうで,教職員・学生に撮影のお知らせ(その時間帯に出ないでくださいとか,協力依頼)が来るんだそうです。



この大学の方(非建築系)に,キャンパスカッコイイですね? とお話をうかがうと,ロケなどに使われるカッコイイ建物なのは良いよね,でも「迷う」「寒い」「使いにくい箇所が」と色々ご評判があるようで。
(自分は守衛室がわからず,守衛室前に立っている守衛さんに,守衛室の場所を聞いてしまいました。バス降車場から死角になっていて見えなかったのです。ココだよと言われてもわかりませんでした。ビックリするくらい,見えないのです。そういう人が多いので,守衛さん,守衛室から出てずっと立ってらっしゃるのかと思いました。寒いのに。。。)

これが守衛室。
カッコイイ(意匠)と,使いやすい・迷わない(計画,環境行動),心地よい(環境設備)と,もちろん安全(構造,防災)を融合させていく,それらのバランスの中でどの辺に設計を落とすか。というのは総合芸術としての建築の課題そのものだな。と感じました。
でもかっこよかったです。写真たくさん撮りました。こういうのも建築の力だものなあ。。

こうやって後付けで経路表示貼られちゃうと,あ,動線認知にだめ出しされてる。
と読み取るのが計画の人。で,どういう風だったら良かったのだろうかと,考える。勉強する。次につなげる。
住宅/集合住宅
集合住宅いろいろ(ロンドン近郊,パリ近郊,シュトゥットガルト近郊)
ヴァイセンホーフ・ジードルンクWeissenhofsiedlung (Stuttgart)
美術館/博物館/展示場
ポルシェミュージアムPorsche Museum (Stuttgart) Designed by Delugan Meiss Associated Architects
ケ・ブランリー美術館Musée du quai Branly Designed by J. Nouvel, G. Clément and P. Blanc
保育所/幼稚園/プレイルーム
学校
公共建築
公園/ランドスケープ
病院/クリニック
パトリック・ブランによるミュゼ・ドゥ・ケ・ブランリーの「生きた壁」。雨上がりでしっとり濡れていて、みなさんがそっと手を触れられていた。人を優しくする壁。 pic.twitter.com/ZRvdwqV32E
ケ・ブランリー、内部。外側に見えているハコ、内側からはそれぞれ趣向を変えた展示スペース。まったく探検家の気分。直接ご覧になったときの感動を大切にすべく、仔細はぶきます。 pic.twitter.com/WRMRr92xoZ
ケ・ブランリー内部。緩やかなスロープで構成されていて、見えない人が手触りでルートを辿り、展示を楽しめる仕掛けがあります。車いすでももちろん大丈夫。触る壁は革張り。実際に数人お見かけしました。一緒に楽しめること、じんわり嬉しい。 pic.twitter.com/WzFo6fHkqI
ちなみに、ケ・ブランリーは夕暮れ時に行くのがおすすめ。
外観をみているうち、だんだんと宵闇に沈んでいく庭、ライトアップで茂みはさらに深く見え、
夜の博物館の赤と黒基調の内装に黄色みの光で展示物が怪しく浮かび上がる。

(ほんと,暗くて撮れないので,写真撮るなら昼間です。目は暗順応してるけど,カメラは物理反応なので・・だけど夜の雰囲気最高)
「はこ」は夜はソトとの境界のガラスが見えなくなって,中からはさらに浮かんで見えます。
てすりのぐにゃぐにゃがおもしろい。
興奮覚めやらず外に出るとキラキラのエッフェル塔。最高。


Pavillon de l'Arsenal。都市計画や,集合住宅や複合施設による都市再開発等の地区計画の展示場。最新のプロジェクトなどもたくさん紹介ありおもしろい。地図になくわかりにくいけどSully Morland駅のすぐ近く。 pic.twitter.com/kH5AVRIVZX