「設計・パフォーマンス(DP)Ⅴ」の小学校課題の事例見学会。
育英学院サレジオ小・中学校(設計:藤木隆男建築研究所)の見学会に参加してきました。
大学生当時,やっぱり3年生だったのかな? の小学校課題で,同じく訪問していますのでかれこれ十数年ぶり・・(その間に,敷地内の別の建物の見学会には参加していたのですが)。
なにも知らない状態で見たときと,その後曲がりなりにも教鞭を執りながらしばらく過ごしたあとで見たときと,やはり感じるところは違うもの。
「へー。こういうのもアリなのか」から「ううむ,これをやられているのですよね。そうですよね」への変化? ダメだ,表現できてない。でもそんな感じ。

武蔵野の森の中の「村」という風情,こんなに木々が大きかったっけ? ちょっと印象が違います。
軒高と屋根の高さ,設置面積/立面のバランス=建物全体のフォルム印象が,
こどもたちが描く「おうち」にぴったり。
自分たちの家という,心象風景そのものと合致するのでしょうね。

木々の間に,各教室(棟)が。

各学年1教室の棟,ワークスペースがテラス側に□と○がかみ合うようにせり出していて,
テラスにはスラロームした空間がつくられています。
すかっと見通せないこの感じ。奥行きや場所性を感じるし,行きたいなと思います。

それぞれの教室は,学年ごとに高さ方向のデザインが変えられています。
1年生から6年生まで,心身の成長著しいですから。
小さいこどもには,少し低い場所が,落ち着けます。
(と,いう説明をどのように受けか,未だに覚えていました。いやあ,実体のもつ力というのはすごいです)

中学校の中庭。
もっと大きかったような気がしたのですが,なぜだろう。
(一緒に行った非常勤の先生も同様におっしゃっていました。なぜだろう)
写真で見るよりもずっと,親密な空間です。
全体に,高さがぐっと抑えられているので(用途地域の高さ制限の関係で),
教室(の定員)の規模も通常の40人学級に比べて30人学級。小さいのです。
で写真で見るよりも,全体のスケールが小さいというわけで,
ちょっとたとえはアレですが“全体に小さい”ミニチュア建物を見ているのと
同じで,写真の印象よりもぐっと小さく身体性にフィットする空間です。

教室を北側に配置,オープンスペースを南側っていうのはアリですか?って
その前の講義の時間に学生さんに聞かれていたのですが(アリだよ~と答えましたが),
ここに20年前から答えがありましたね。北側に教室が配置され,中庭を介して南から
陽光差し込むオープンスペース/縁側状の廊下空間があります。
北側からの落ち着いた光で勉強,くつろぎやじゃれあいの時間は南側の活動的エリアで。
北側の窓からは,南からの光に照らされた新緑の木々が美しく輝いています。
教室の外(北側)には広い屋上テラス。制作等の活動にも使われるそうです。

ドン・ボスコ記念聖堂も見せていただきました。(懐かしい!)
アイビーが,以前みたときよりも塔のずっと上まで登っています。
時間が建築を美しくしていくな。って思うのは,ため息が出るほど嬉しい瞬間。

パイプオルガンが設置されている2階部分から。こちらに上がらせていただいたのは始めてかも。
音楽の先生がちょっとだけね,とパイプオルガンで弾いてくださいました。感動。
出たところで記念撮影。ご案内くださった先生方と。
(見学会に参加された方はこちらにアップしてありますのでどうぞ。PWは「地域施設計画2013」のと同じです)

中学校の入口まで戻って,解散。
「再訪」の価値,繰り返し見ることの価値について実感した機会でした。
本も論文も読み返す,好きな建物も街も,何度も行く。
本当に優れた作品や文章,また自分と波長が合うものには,
その時々の自分のレベルや興味関心や,抱えてる問題や課題や,によって,
違った答えやヒントを見いだすことができるよな,と。
ご案内くださった先生方,学校の皆様,本当にありがとうございました。










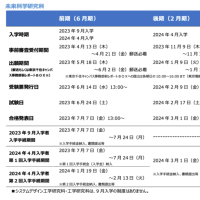

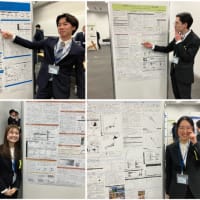

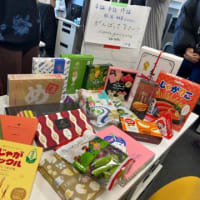



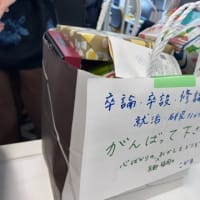



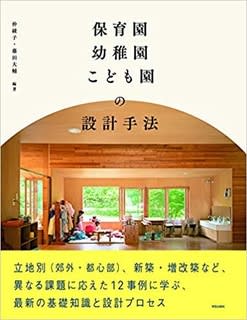
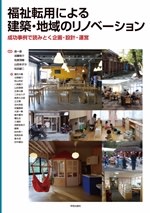



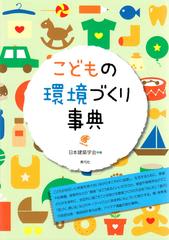



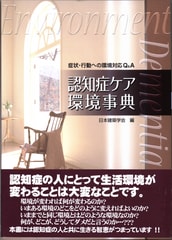

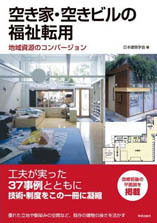





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます