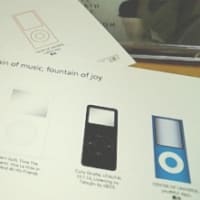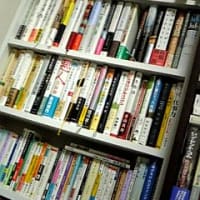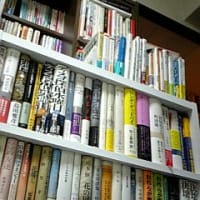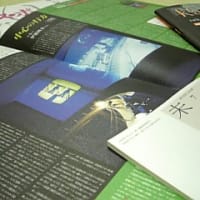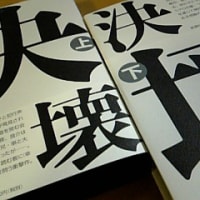[01]『生物と無生物のあいだ』(福岡伸一/講談社現代新書)
[02]「ケータイ小説は『作家』を殺すか」(『文學界 08年01月号』)
[03]『国家論』(佐藤優/NHKブックス)
[04]『組織を伸ばす人、潰す人』(柴田励司/PHP)
[05]「乳と卵」(『文學界 07年12月号』)
[06]『In Rainbows』Radiohead
[07]『オン・ザ・ロード』(ジャック・ケルアック/河出世界文学全集)
[08]『国家の罠』(佐藤優/新潮文庫)
[09]『ヘルメスの音楽』(浅田彰/ちくま学芸文庫)
[10]『エセーⅡ 思考と表現』(モンテーニュ/中公クラッシクス)
[11]『犬身』(松浦理英子/朝日新聞社)
[12]『AERA '08.2.4』(朝日新聞社)
[13]「カフカ『城』ノート(1)――小説をめぐって(三十四)」(保坂和志/『新潮 07年11月号』)
▶ずいぶんと間があいてしまったので、その間に目を通していたものを列挙すると立派な読書家のように見えなくもない。でも、実際のところは、あいかわらず毎日8分間読書術。いや、もう少しは読んでいるか。世の中を震撼させている「とにかく効率!なにより効率アップ本」が1冊も入っていないので、ますます効率が悪くなるばかりだ。
▶しかし、たとえば[01][08]のような本は作者が巧みだし、新しい発見も多く、たとえ8分に毛の生えた程度の時間であっても、一気に150ページくらいまでは読み進めることができる。たいへん面白く、世の中のガイドラインに素直にしたがって、もっと早くに読んでおくべきだったなあ、と思う。たとえば、『生物と無生物のあいだ』のこんな発想は、さまざまな考えや行動に援用できる。
「肉体というものについて、私たちは自らの感覚として、外界と隔てられた個物としての実体があるように感じている。しかし、分子のレベルではその実感はまったく担保されていない。私たち生命体は、たまたまそこに密度が高まっている分子のゆるい「淀み」でしかない。しかも、それは高速で入れ替わっている。この流れ自体が「生きている」ということであり、常に分子を外部から与えないと、出ていく分子との収支が合わなくなる」(P163)
「つまり、エントロピー増大の法則に抗う唯一の方法は、システムの耐久性と構造を強化することではなく、むしろその仕組み自体を流れの中に置くことなのである」(P167)
「抗うな。受け入れろ。全ては繋がっている」とは、『ザ・ワールド・イズ・マイン』のあまりにも有名な箴言だが、最近この考え方を、解釈を拡大しながら(もしくは収斂させながら)少しまじめに分解してみようと思っている。これは、きっと明日アップするエントリーにも関連した話かもしれない。そんなときに、福岡が言う生物学のファクトはよい補助線になる。
▶[02]は、テーマ同様、ペラペラな鼎談だ。全体的に話すこともあまりなく場が途切れているような印象を与える。本来であれば、鈴木謙介が気の利いた意見で場を混ぜ返すはずなのだろうけれど、いまいち真剣に論じる気もないようにみえる。これを読む限りは、また、たとえ東浩紀がいくら推奨したとしても、ケータイ小説を通読するということはネタにしか過ぎないように思えてくる。ジャンルとしてあることに異論はないけれど、鼎談でもかかれたように、「浪花節」であり「大衆演芸」であり、もうひとこと加えるなら「女性週刊誌」であるわけだから、だれもがこぞって是非を議論するものではないということだろう。つまり、ケータイ小説が流行っているから、同じような内容の月9の例の脚本家が再び降臨してきたと見えたとしても、そこにはあんまり関係性はないのである。
▶[03]は柄谷の「世界共和国」のくだりになって俄然面白くなってきた。少し遡って、議論・論争における「事実」「権利関係」の規定の大切さ(権利関係で争っても答えはでない)といったくだりなども、これはいわゆるインテリジェンスの初歩の初歩なんだろうけれど、言われてみれば納得がいく。先の[08]『国家の罠』と交互に読むと、ほとんど佐藤の思考に侵されてしまう。
▶本棚から[04]『組織を伸ばす人、潰す人』が落ちてきたので、端を折っていたページを再読してみる。やはり、いいことが書いてあるなあと思える、その理由は明らかで「いま、ワーカーはとてつもなく忙しい、忙しくなった」という前提に立っているからだ。おそらく自身がそうだったのだろう、その「とてつもなさ」に高いリアリティがある。「忙しさを伝染させてはいけない」といった提言は、そういった状況のなかにおいて唱えて初めて意味をもつし説得力をもつ。
▶働き通しの日曜日の夜に衝動的に[06]『In Rainbows』を。日本からのDLは面倒そうだったし、なにより、いくら?と問われても、相場感がないので、ネット購入はあきらめていた。相場感がわからないくらいのもんだから、曲の善し悪しもよくわからない、という感じになるか、と思っていたところ、意外に体になじみ、だから毎日夜中の30分の帰宅路で聞いている。あっという間に終わる短さが残念。
▶例によって、[07]~[10]は、書店の敵で購入。河出の世界文学全集には大きな興味をもっていなかったのだけれど、さすがに書店に並ぶと気になる。すでにリョサの『楽園への道』も古書店で見つけてはいたんだけれど、リョサなので踏み切れず(『楽園…』は面白いらしいけれど)、あくまでも新訳なので買う気もなかった『オン・ザ・ロード』を装丁と価格に負け購入。この調子で新古書を発見していけば全巻そろってしまうかもしれない。
▶[12]『AERA』が面白そうだったので久しぶりに買ってみた。「金融危機」は同時多発しているが、危機に向う最初のアクション(危機を決壊させた引き金ではなくあくまでエントロピーの初動)まで、同時多発というわけではないだろうから、そこまで遡って特定することは可能なのだろうか。たとえば、ゴールドマン・サックスの某が、クラシックなハンバーガーにがっつきながら、ケチャップで汚れたマーカーでホワイトボードに書きなぐったちょっとした思いつきがそもそも原因だとか。
しかし、証券化はともかく債権の証券化というのはわからない。あいかわらず金で金を買うという感覚にもついていけない。時間と情報の差益にしちゃあ度が過ぎていないか、と思うし、実物とか愛顧がないなかでの商売って始終不安と猜疑と嫌悪に苛まれているのではないか、と思うのだけれど、そうではないのかな。そうではないのだろうな。きっとエキサイティングなんだろうな。
▶[13]の『新潮』の去年の11月号をずっと東京の家に置きっぱなしにしていたためほとんどさらっぴんの状態だったのだけれど、大阪に持ち帰るタイミングで、ちらりと除いたらはまってしまった。いずれ発売される単行本に委ね、保坂の連載はほとんど斜め読みしかしていないのだが、これはしっかり読みきってしまった。いわゆるカフカの精読なのだけれど、言葉の並び方・使い方といったレベルの微細な表現技法にまで話がおよび(これは、『アメリカンスクール』の解説も同じ)、常人ではない人間の文章思考を浮き彫りしている。ルールに適用されない言葉の配列、微妙にズレた(誤った)用法。これらはテクニックではなく、言葉というものに対する感覚の違いであり、そこに音楽のような自由があることがわかる。このことが始めて実感できた。
[02]「ケータイ小説は『作家』を殺すか」(『文學界 08年01月号』)
[03]『国家論』(佐藤優/NHKブックス)
[04]『組織を伸ばす人、潰す人』(柴田励司/PHP)
[05]「乳と卵」(『文學界 07年12月号』)
[06]『In Rainbows』Radiohead
[07]『オン・ザ・ロード』(ジャック・ケルアック/河出世界文学全集)
[08]『国家の罠』(佐藤優/新潮文庫)
[09]『ヘルメスの音楽』(浅田彰/ちくま学芸文庫)
[10]『エセーⅡ 思考と表現』(モンテーニュ/中公クラッシクス)
[11]『犬身』(松浦理英子/朝日新聞社)
[12]『AERA '08.2.4』(朝日新聞社)
[13]「カフカ『城』ノート(1)――小説をめぐって(三十四)」(保坂和志/『新潮 07年11月号』)
▶ずいぶんと間があいてしまったので、その間に目を通していたものを列挙すると立派な読書家のように見えなくもない。でも、実際のところは、あいかわらず毎日8分間読書術。いや、もう少しは読んでいるか。世の中を震撼させている「とにかく効率!なにより効率アップ本」が1冊も入っていないので、ますます効率が悪くなるばかりだ。
▶しかし、たとえば[01][08]のような本は作者が巧みだし、新しい発見も多く、たとえ8分に毛の生えた程度の時間であっても、一気に150ページくらいまでは読み進めることができる。たいへん面白く、世の中のガイドラインに素直にしたがって、もっと早くに読んでおくべきだったなあ、と思う。たとえば、『生物と無生物のあいだ』のこんな発想は、さまざまな考えや行動に援用できる。
「肉体というものについて、私たちは自らの感覚として、外界と隔てられた個物としての実体があるように感じている。しかし、分子のレベルではその実感はまったく担保されていない。私たち生命体は、たまたまそこに密度が高まっている分子のゆるい「淀み」でしかない。しかも、それは高速で入れ替わっている。この流れ自体が「生きている」ということであり、常に分子を外部から与えないと、出ていく分子との収支が合わなくなる」(P163)
「つまり、エントロピー増大の法則に抗う唯一の方法は、システムの耐久性と構造を強化することではなく、むしろその仕組み自体を流れの中に置くことなのである」(P167)
「抗うな。受け入れろ。全ては繋がっている」とは、『ザ・ワールド・イズ・マイン』のあまりにも有名な箴言だが、最近この考え方を、解釈を拡大しながら(もしくは収斂させながら)少しまじめに分解してみようと思っている。これは、きっと明日アップするエントリーにも関連した話かもしれない。そんなときに、福岡が言う生物学のファクトはよい補助線になる。
▶[02]は、テーマ同様、ペラペラな鼎談だ。全体的に話すこともあまりなく場が途切れているような印象を与える。本来であれば、鈴木謙介が気の利いた意見で場を混ぜ返すはずなのだろうけれど、いまいち真剣に論じる気もないようにみえる。これを読む限りは、また、たとえ東浩紀がいくら推奨したとしても、ケータイ小説を通読するということはネタにしか過ぎないように思えてくる。ジャンルとしてあることに異論はないけれど、鼎談でもかかれたように、「浪花節」であり「大衆演芸」であり、もうひとこと加えるなら「女性週刊誌」であるわけだから、だれもがこぞって是非を議論するものではないということだろう。つまり、ケータイ小説が流行っているから、同じような内容の月9の例の脚本家が再び降臨してきたと見えたとしても、そこにはあんまり関係性はないのである。
▶[03]は柄谷の「世界共和国」のくだりになって俄然面白くなってきた。少し遡って、議論・論争における「事実」「権利関係」の規定の大切さ(権利関係で争っても答えはでない)といったくだりなども、これはいわゆるインテリジェンスの初歩の初歩なんだろうけれど、言われてみれば納得がいく。先の[08]『国家の罠』と交互に読むと、ほとんど佐藤の思考に侵されてしまう。
▶本棚から[04]『組織を伸ばす人、潰す人』が落ちてきたので、端を折っていたページを再読してみる。やはり、いいことが書いてあるなあと思える、その理由は明らかで「いま、ワーカーはとてつもなく忙しい、忙しくなった」という前提に立っているからだ。おそらく自身がそうだったのだろう、その「とてつもなさ」に高いリアリティがある。「忙しさを伝染させてはいけない」といった提言は、そういった状況のなかにおいて唱えて初めて意味をもつし説得力をもつ。
▶働き通しの日曜日の夜に衝動的に[06]『In Rainbows』を。日本からのDLは面倒そうだったし、なにより、いくら?と問われても、相場感がないので、ネット購入はあきらめていた。相場感がわからないくらいのもんだから、曲の善し悪しもよくわからない、という感じになるか、と思っていたところ、意外に体になじみ、だから毎日夜中の30分の帰宅路で聞いている。あっという間に終わる短さが残念。
▶例によって、[07]~[10]は、書店の敵で購入。河出の世界文学全集には大きな興味をもっていなかったのだけれど、さすがに書店に並ぶと気になる。すでにリョサの『楽園への道』も古書店で見つけてはいたんだけれど、リョサなので踏み切れず(『楽園…』は面白いらしいけれど)、あくまでも新訳なので買う気もなかった『オン・ザ・ロード』を装丁と価格に負け購入。この調子で新古書を発見していけば全巻そろってしまうかもしれない。
▶[12]『AERA』が面白そうだったので久しぶりに買ってみた。「金融危機」は同時多発しているが、危機に向う最初のアクション(危機を決壊させた引き金ではなくあくまでエントロピーの初動)まで、同時多発というわけではないだろうから、そこまで遡って特定することは可能なのだろうか。たとえば、ゴールドマン・サックスの某が、クラシックなハンバーガーにがっつきながら、ケチャップで汚れたマーカーでホワイトボードに書きなぐったちょっとした思いつきがそもそも原因だとか。
しかし、証券化はともかく債権の証券化というのはわからない。あいかわらず金で金を買うという感覚にもついていけない。時間と情報の差益にしちゃあ度が過ぎていないか、と思うし、実物とか愛顧がないなかでの商売って始終不安と猜疑と嫌悪に苛まれているのではないか、と思うのだけれど、そうではないのかな。そうではないのだろうな。きっとエキサイティングなんだろうな。
▶[13]の『新潮』の去年の11月号をずっと東京の家に置きっぱなしにしていたためほとんどさらっぴんの状態だったのだけれど、大阪に持ち帰るタイミングで、ちらりと除いたらはまってしまった。いずれ発売される単行本に委ね、保坂の連載はほとんど斜め読みしかしていないのだが、これはしっかり読みきってしまった。いわゆるカフカの精読なのだけれど、言葉の並び方・使い方といったレベルの微細な表現技法にまで話がおよび(これは、『アメリカンスクール』の解説も同じ)、常人ではない人間の文章思考を浮き彫りしている。ルールに適用されない言葉の配列、微妙にズレた(誤った)用法。これらはテクニックではなく、言葉というものに対する感覚の違いであり、そこに音楽のような自由があることがわかる。このことが始めて実感できた。