 久しぶりの東京駅からの新幹線は、先行列車の事故かなにかで、1時間ほど遅滞した。おかげで、乗車直前に八重洲古書街で購入した青山真治の『雨月物語』を、名古屋につくまでに読み終えることができた。『雨月物語』については、上田秋成のものはもとより、石川淳、後藤明生らのリメイク訳なども含めテキストとして読んではいないのだけれど、この青山真治のバージョンは、ほとんど口承伝聞レベルでもれ聞く限りでしかない本家『雨月』の物語の筋やエピソードの連関性・円環性などを巧みに継承し、かつ彼なりの映像視点と中上視点をうまく付加することでオリジナルと見紛うかのように仕上げている。
久しぶりの東京駅からの新幹線は、先行列車の事故かなにかで、1時間ほど遅滞した。おかげで、乗車直前に八重洲古書街で購入した青山真治の『雨月物語』を、名古屋につくまでに読み終えることができた。『雨月物語』については、上田秋成のものはもとより、石川淳、後藤明生らのリメイク訳なども含めテキストとして読んではいないのだけれど、この青山真治のバージョンは、ほとんど口承伝聞レベルでもれ聞く限りでしかない本家『雨月』の物語の筋やエピソードの連関性・円環性などを巧みに継承し、かつ彼なりの映像視点と中上視点をうまく付加することでオリジナルと見紛うかのように仕上げている。何を書いても中上健次という評価は、青山真治の場合、けっして否定的な話ではなく、中上の普遍性を追及する精読がなければ完成しえないそのスタイルを前に、むしろ小説のオリジナリティといった議論は不問になる。中上が憑依し、逆に青山が憑依する。そこで生まれてくるテキストは、これもまたひとつの小説の形である。
「夏には勝四郎の腕も足も、倍の太さになっていた。顔は陽に焼け、髭に覆われた。土は勝四郎の汗を吸い、だんだんと畑の格好をなして広がっていた。鍬の柄もまた勝四郎の血に黒く染まり、手に馴染んでいた」
これは、『雨月物語』でいうところの「浅茅が宿」のエピソードでひたむきな妻・宮木に亡霊となって待たれた男が幻想から覚め妻亡きあと、生きていく意志をあらたにする場面であり、けっして『枯木灘』や『岬』の1シーンではない。しかし、自宅に戻り宮木との幻夜のあと、宮木の死を受け止め現実の生気を穏やかに漲らせていくその表現方法として、この中上的なる人間の躍動は、もっとも相応しいように思える。「浅茅が宿」は、青山版では、「蛇性の婬」のサブストーリー的な扱いとなっているが、現の世のたくましさをあらわすこの表現が、雨月全体に流れる時代性と幻想性を、「いま、ここ」に架橋している。そして、そのテキストが表さんとしているのはまさに「血」のことである。
人間は「血」からは逃れられず、それはときに善きに作用し生きる源泉となり、ときに悪しきに作用し人を縛り続ける。このたんなる生理学的な液体に人はなぜ惑わされるのか。とき同じくして単行本となった『サッド・ヴァケイション』が、呪縛としての衝撃的な血の物語であるとすれば、雨月の血は生きるよすがとしての血の物語であるように思える。
秋成が中国の伝奇譚を換骨奪胎し『雨月物語』を記したように、青山もまた新しい『雨月』を創りあげた。物語冒頭の描写を読む限りにおいて、また亡霊との壮絶にして超常的な戦闘を青山真治がどう撮るのかという点において、映画版にも期待できる。
「最後の一兵が絶命したあと、尾根から霧が流れ落ちてきた。
天から降りてくるこの世ならぬもののようにも巨大な瀑布のようにも見えるその霧は、累々と横たわる屍骸たちを嘲るように青々と生気を漲らせた草原を、一瞬にして隠した。たが夥しい血と肉の臭気はその濃霧によっても、またときおり吹き流れてくる風によっても、隠しえるものではないほどに充満し、とめどなく湧き上がってくる。」












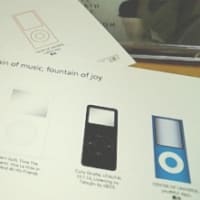
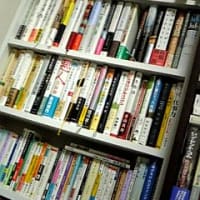
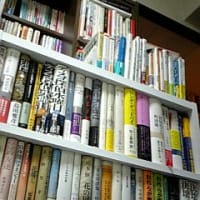

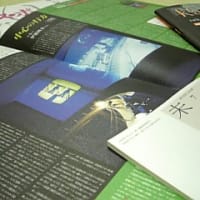

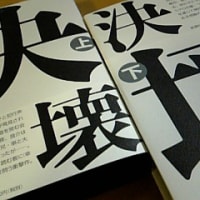

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます