
自分でBLOGを書いて、かつRSSリーダーやアンテナなどで、人文系や書評的なBLOGをいくつか読み続けている毎日を過ごしていると、ある意味で、BLOGの世界にとっぷり嵌ってしまうわけで、とても初歩的なことだけど、リアルとバーチャルのトレンドが混濁してしまう。ブログの世界のトレンドは、けっして現実の世界のトレンドではなく、現段階では、まだ狭い世界であるということを戒めなければならないだろう。
このことは『ユリイカ 4月号』の「特集:ブログ作法」を読んでいる自分を俯瞰すればよくわかる。
今号の『ユリイカ』は、わたしがふだん巡回しているようなBLOG上では、当然のことながら相当の話題になっている。したがって、こういった形で、発売日から数日たって紹介するのは、気が引ける。畢竟、まだ語られていない新しい批評的な切り口で紹介しなければ、とか、アホなことは書けないなあと、気構えてしまう。
しかし、実際のところは、『ユリイカ』は、『文藝春秋』と違って、全国のどこの書店でも手軽に入手できるような雑誌ではない。そもそも、『ユリイカ』なんていう雑誌は多くの人が知らないだろうし、存在を知っていたとしても、『ユリイカ』の今月号がブログ特集であることをいちはやく察知するには、毎月『ユリイカ』の発売日を心待ちにしているような人でない限り難しいだろう。もしくは、数ヶ月前に執筆者の誰かが「ユリイカに書いてる」とか「喋った」とかBLOG上で公開したのを知らない限りは。
また、同誌で登場している対談者や執筆者もBLOGの世界ではおなじみな人が多く、なかなか面白いメンバーを選んでくるなあ、と思ってしまうのだが、たとえば、わたしが毎日のように閲覧しているのでおなじみのように錯覚してしまう「陸這記」の仲俣暁生さんなんて人をリアルの世界だけで生きている人がどれだけ知っているのか。よほどの本好き、文学好きでない限り『極西文学論』なんて本を書店で発見できないだろうにもかかわらず、リアルの世界でついつい「)仲俣暁生が、出てんだよね」なんて話してしまい、「えっ、誰それ?」と、怪訝な顔をされるわけだ。
同誌に「史上最弱のブロガー」を寄稿しているバーチャル師匠・内田樹もそうだ。もちろん、彼の場合は『寝ながら学べる構造主義』などを契機として、リアルの世界でその発想力と筆力でかなりの人気著述者にはなっているのだが、現在は、それ以上にBLOGの世界での露出が多く、人気が加速しているように思えてしまう。ご自身のBLOG「内田樹の研究室」の精力的な執筆はもとより、平川克美さんとの「東京ファイティングキッズ2」BLOG、そしてこれらを引用するBLOGの多さ。わたしのBLOG界では、まさにカリスマ教授である。しかし、これも実際の世界とは大きな乖離があって、たとえば、自社の事務所にいるスタッフの95%くらいは、内田先生のことを知らない、という現実がある。
「『ブログ作法とは何か』とは何か」といったメタ的な評論を寄稿するだけでなく、上野俊哉・泉政文という人のわかりにくいエッセイのなかで「試行空間」にも触れられている北田暁大さんの『嗤う日本のナショナリズム』だって、世間的にはネット&BLOG界や青山ブックセンターほどは話題になっていない。
もちろん、ここまで述べたことは、わたしの偏った趣味領域の範囲なので、リアルの世界で話が通じにくい人が多いのは当然のことだ。しかし、一方のわたしのBLOG界では(場合によっては、このBLOGを読んでいただいているような方の世界では)、毎日のように 、『ユリイカ』や仲俣暁生や『嗤う日本のナショナリズム』が議論されているというリアルもある。
そして、これはじつはトレンドの錯覚を起こすということが問題ではないような気がしてきた。WEB、BLOGなどのインターネットの世界は、コミュニケーションを拡散させていく機能がある一方で、逆に世界をどんどん凝縮させ、狭窄化していく機能もある、ということを課題化する方がどうやら正しそうだ。狭い世界でしか拡がらない。バーチャルが故に、バカの壁をおっ立てやすい、という言い方もあるかもしれない。RSSリーダーで似たようなBLOGを毎日ザッピングするという行為は、世界が拡がっているような気分にさせるが、けっしてそんなことはないということだ。
わたしがひそかにブックマークしている「Nachklang/日々の残響」なんて哲学(現象学)系ディシプリン系BLOG(?)が、『ユリイカ』に紹介されてしまうあたりも、世界の狭さを物語っているのかもしれない。
このBLOGも、当初は、マーケティングや現代思想の話題などを拡散的に、しかもアバウトに書き連ねていこうと考えていたんだけれども、現状では、文学の話題に凝縮していっている(テーマ偏重については、近いうちにコレクトしていこうと考えているけれど)。
少なくともわたしにとっては、BLOGはコミュニケーションと情報取得を、(いい意味でも悪い意味でも)凝縮していくために作用しているようだ。
では、拡がるWEBコミュニケーションとは?『ユリイカ』の特集の冒頭の対談「はてな頂上作戦」(※1)では、すべての対談者がSNSにも「はまっている(いた)」と、熱く語られていて、たまたまわたしもミクシィの招待状をいただいたこともあり、少しそちらのほうで拡散のコミュニケーションの可能性について体験してみたい、とは思う。
というような『ユリイカ』の紹介の仕方なら、発売後、数日たっても許されませんでしょうか。
いや、ほんとは、いずれかのエッセイをとりあげて批評的に論じるのがベストなんだろうけど、お気づきのようにBLOGとかネット、その「作法」については、相対的にはまだまだ「ごまめ」なので、意見をもてないんですよね。
------------------------
(※1)仲俣暁生、栗原祐一郎らによる対談「はてな頂上作戦」を読むと、BLOGを「はてな」と2重もちにしてもいいかなあと、と思わせる。キーワードリンクが魅力的だし、引用、脚注などの挿入も賢そうだ。idを取得しているため、試しに、gooブログでエントリーしているものをあげてみたのだが、キーワードリンクがたくさんついて、うれしくなってしまった。ただ、いかんせんテンプレートのデザインが酷すぎるし、なんだろうなあ、ブラウザー上でのスクロールがスムーズでないのも気になるんだよなあ。


このことは『ユリイカ 4月号』の「特集:ブログ作法」を読んでいる自分を俯瞰すればよくわかる。
今号の『ユリイカ』は、わたしがふだん巡回しているようなBLOG上では、当然のことながら相当の話題になっている。したがって、こういった形で、発売日から数日たって紹介するのは、気が引ける。畢竟、まだ語られていない新しい批評的な切り口で紹介しなければ、とか、アホなことは書けないなあと、気構えてしまう。
しかし、実際のところは、『ユリイカ』は、『文藝春秋』と違って、全国のどこの書店でも手軽に入手できるような雑誌ではない。そもそも、『ユリイカ』なんていう雑誌は多くの人が知らないだろうし、存在を知っていたとしても、『ユリイカ』の今月号がブログ特集であることをいちはやく察知するには、毎月『ユリイカ』の発売日を心待ちにしているような人でない限り難しいだろう。もしくは、数ヶ月前に執筆者の誰かが「ユリイカに書いてる」とか「喋った」とかBLOG上で公開したのを知らない限りは。
また、同誌で登場している対談者や執筆者もBLOGの世界ではおなじみな人が多く、なかなか面白いメンバーを選んでくるなあ、と思ってしまうのだが、たとえば、わたしが毎日のように閲覧しているのでおなじみのように錯覚してしまう「陸這記」の仲俣暁生さんなんて人をリアルの世界だけで生きている人がどれだけ知っているのか。よほどの本好き、文学好きでない限り『極西文学論』なんて本を書店で発見できないだろうにもかかわらず、リアルの世界でついつい「)仲俣暁生が、出てんだよね」なんて話してしまい、「えっ、誰それ?」と、怪訝な顔をされるわけだ。
同誌に「史上最弱のブロガー」を寄稿しているバーチャル師匠・内田樹もそうだ。もちろん、彼の場合は『寝ながら学べる構造主義』などを契機として、リアルの世界でその発想力と筆力でかなりの人気著述者にはなっているのだが、現在は、それ以上にBLOGの世界での露出が多く、人気が加速しているように思えてしまう。ご自身のBLOG「内田樹の研究室」の精力的な執筆はもとより、平川克美さんとの「東京ファイティングキッズ2」BLOG、そしてこれらを引用するBLOGの多さ。わたしのBLOG界では、まさにカリスマ教授である。しかし、これも実際の世界とは大きな乖離があって、たとえば、自社の事務所にいるスタッフの95%くらいは、内田先生のことを知らない、という現実がある。
「『ブログ作法とは何か』とは何か」といったメタ的な評論を寄稿するだけでなく、上野俊哉・泉政文という人のわかりにくいエッセイのなかで「試行空間」にも触れられている北田暁大さんの『嗤う日本のナショナリズム』だって、世間的にはネット&BLOG界や青山ブックセンターほどは話題になっていない。
もちろん、ここまで述べたことは、わたしの偏った趣味領域の範囲なので、リアルの世界で話が通じにくい人が多いのは当然のことだ。しかし、一方のわたしのBLOG界では(場合によっては、このBLOGを読んでいただいているような方の世界では)、毎日のように 、『ユリイカ』や仲俣暁生や『嗤う日本のナショナリズム』が議論されているというリアルもある。
そして、これはじつはトレンドの錯覚を起こすということが問題ではないような気がしてきた。WEB、BLOGなどのインターネットの世界は、コミュニケーションを拡散させていく機能がある一方で、逆に世界をどんどん凝縮させ、狭窄化していく機能もある、ということを課題化する方がどうやら正しそうだ。狭い世界でしか拡がらない。バーチャルが故に、バカの壁をおっ立てやすい、という言い方もあるかもしれない。RSSリーダーで似たようなBLOGを毎日ザッピングするという行為は、世界が拡がっているような気分にさせるが、けっしてそんなことはないということだ。
わたしがひそかにブックマークしている「Nachklang/日々の残響」なんて哲学(現象学)系ディシプリン系BLOG(?)が、『ユリイカ』に紹介されてしまうあたりも、世界の狭さを物語っているのかもしれない。
このBLOGも、当初は、マーケティングや現代思想の話題などを拡散的に、しかもアバウトに書き連ねていこうと考えていたんだけれども、現状では、文学の話題に凝縮していっている(テーマ偏重については、近いうちにコレクトしていこうと考えているけれど)。
少なくともわたしにとっては、BLOGはコミュニケーションと情報取得を、(いい意味でも悪い意味でも)凝縮していくために作用しているようだ。
では、拡がるWEBコミュニケーションとは?『ユリイカ』の特集の冒頭の対談「はてな頂上作戦」(※1)では、すべての対談者がSNSにも「はまっている(いた)」と、熱く語られていて、たまたまわたしもミクシィの招待状をいただいたこともあり、少しそちらのほうで拡散のコミュニケーションの可能性について体験してみたい、とは思う。
というような『ユリイカ』の紹介の仕方なら、発売後、数日たっても許されませんでしょうか。
いや、ほんとは、いずれかのエッセイをとりあげて批評的に論じるのがベストなんだろうけど、お気づきのようにBLOGとかネット、その「作法」については、相対的にはまだまだ「ごまめ」なので、意見をもてないんですよね。
------------------------
(※1)仲俣暁生、栗原祐一郎らによる対談「はてな頂上作戦」を読むと、BLOGを「はてな」と2重もちにしてもいいかなあと、と思わせる。キーワードリンクが魅力的だし、引用、脚注などの挿入も賢そうだ。idを取得しているため、試しに、gooブログでエントリーしているものをあげてみたのだが、キーワードリンクがたくさんついて、うれしくなってしまった。ただ、いかんせんテンプレートのデザインが酷すぎるし、なんだろうなあ、ブラウザー上でのスクロールがスムーズでないのも気になるんだよなあ。














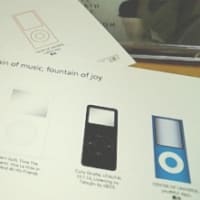
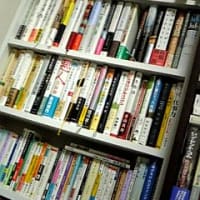
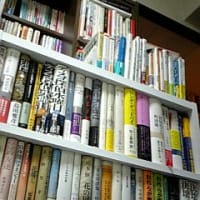

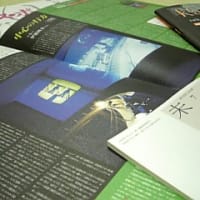

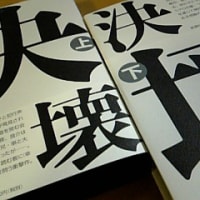

試行空間は、上野さんと北田さんが公開討論してる頃、よく読んでました。いまはぜんぜん読んでません。
>WEB、BLOGなどのインターネットの世界は、コミュニケーションを拡散させていく機能がある一方で、逆に世界をどんどん凝縮させ、狭窄化していく機能もある
これは言い得て妙だなと思いました。僕もそんな気がする、今日この頃です。
でもこれはあくまで僕の実感ですが、「どんどん世界が凝縮させ、狭窄化し」ていく印象を受ける一方、インターネットで情報を取得したり、ブログを運営をすることによって、以前より、圧倒的に底辺が広がっているような気が僕はしますね。個人差はあると思うんですけど、僕の場合、幅広く様々なブログを読むようにしてます。
で、僕はむしろこれから「課題化」されるべきテーマはコミュニケーションじゃなくて、著作権の方なんだと思います。ブログで画像や歌詞や本の文章を勝手に引用しまくっている僕のような(?)人間が、今後、問題になってくるんだと思います。先週の金曜日やっていた『朝生』を見て、こんなことを思いました。
このエントリーで紹介したようなBLOG界の人々の話題が、リアルの世界ではいまいち通じにくいなあ、という思いを端緒としているわけですが、じつのところは、課題の立て方すらわかっていないのが現状です。拡がっているのか狭まっているのかわからない。拡がるってなんなのか?狭いって?という感じです。
いっぽう、余計な情報もたくさんはいってきて、たとえば読まなければならないとオブセッションにかられる本なども増えてきて、情報の上澄みだけを掠め取るとらざるをえない現状もあり、処理能力をあげることと、逆に入り口を狭めることを両輪で考えなければならないなあ、とも考えています。いってしまえばリテラシーを磨くという、ことになるのでしょうが、こんな便利な言葉ですませてしまってよいものかどうか。
また、著作権なんて、新しいテーマを振ってくる人もいるし(笑)。
『朝生』は、そんな話題にまで及んでいたのですか。冒頭、いつもの堀江文脈だったので寝てしまいました。
>たとえば読まなければならないとオブセッションにかられる本なども増えてきて、情報の上澄みだけを掠め取るとらざるをえない現状もあり…
この感覚わかりますね! 僕はフジテレビでやっていた『お厚いのがお好き?』を好きで見ていたのですが(いまはわけのわからないデザイン系の番組になってしまいましたが。ウラタさんは、この番組、以前、ここで紹介されてましたよね。僕もあの「新しいキップ」の回、見ました!)。この番組の最終回はブラッドベリの『華氏451』でした。「近い将来、人々は誰も本を読まなくなり、情報も表層的にしか意味をもたくなるだろう」ということが『華氏451』ではテーマにされているわけですけど、ブログの世界なんかを見ていると、『華氏451』が問題視していた世界が拡大しているんじゃないか? と思ったりします。これは僕の憶測ですが、ブログはめちゃくちゃ読むけど、本を読まない人って多いような気がしますね。ブログだけで、表層的に情報を取得して、それで終わり。本を読んでいることが徳のある行為だとは思いませんが、ウラタさんのいわれる通り、いずれにしろ「思考力=リテラシー」を磨くことは必要ですね。
これは良い意味ですけど、「浅く広く」をモットーに、「たまに深く」語るブログって好きです(笑)。例えば、ウラタさんのようなブログ。読んでいて、勉強になりますね。
『朝生』は最終的にネット全般に問題が議論が展開されてました。2ちゃんねるや、ブログの有効性や問題点(著作権・モラル・匿名性)について真剣に議論してました。
例えばもし今後、ブログの世界で著作権を守るための規制が厳しくなったら、ブログ人口は確実に減ると思います。僕もたぶんブログをやめます(というか、やめざる終えない)。難しい問題ですよねえ…。
また遊びにきます。ていうか、村上龍の新作、すごいおもしろそうですねえ…。ああ、読まなきゃいけない本が多すぎて、困ります。
長文駄文、失礼しました。
BLOGはもちろんですが、まずWEBの登場によって、じつは、ぼくたちは毎日もの凄い量のテキストにまみれた生活をおくることになってしまったわけで、このことを評して「活字離れはおきていない」という意見もあるわけですが、じつのところは、ケンスケさんのおっしゃるとおり、ほんとかよ、というところはありますね。
意見がいいやすいことは加速度的にいいやすくなってしまって、いっぱしの意見を言った気になってしまうのですが、その影で、考えがまとまりにくいこと、オリジナルなことが、スポイルされていってしまっているような気もします。自戒も込めて。
ネットワーク上で、表層的にオピニオンは集中していく?あ、なんだか課題がたてられそうな気がしてきた。ありがとうございます。
村上龍の新作は、試みとしても面白いです。ただ、おそらく多くの意見が、最高傑作!とか、小説の新しい形!などになりそうだし、批評の場が、「13歳のハローワーク」と同じような政治経済のステージになりそうなので、なんとかテキストのみを読みとる批評的な考えを求めようとしているところです。その意志さえ麻痺してしまうほどの愉楽があって、困りものなんですけど。