土曜日にクライアントから受注した営業戦略のような企画の討議用資料がいったん脱稿したため次のミーティングまでの合間を縫ってちょっと書いてみる。
もちろん材料は『半島を出よ』。上巻までを急ぎ足で読んでみた。しかし、急ぎ足で読むには、あまりにも情報量が多すぎて、疲れるテキストではある。
とりわけ、北朝鮮反乱軍である高麗軍については、そもそも人名や地名にリテラシーがないため、それぞれのプロフィールが明確に設定されているにもかかわらず、誰が誰だかわからなくなる。タフな経歴と連動したかたちでのタフなキャラクターじたいも立っているはずなのだが、やっぱり名前と一致しない。
これはイシハラグループにもいえることで、それぞれのメンバーが少年時代に壮絶な人生を送っているにもかかわらず、その出来事じたいは強く記憶に残るのだが、カタカナで表記された人名とはどうも一致しない。
いっぽうで、内閣情報調査室や、会議で議論する総理大臣、官房長官さらには、福岡県知事、市町などの漢字表記の名前は覚えやすく、どれだけ唐突にでてきても特定できる。
もし、高麗軍やイシハラグループのキャラクターが、漢字で記名されていれば、状況は大きく変わっただろうとも感じる。
 これはどういうことだろうか。もちろんめくるめくような登場人物の多さにも起因しているだろうが、それ以上に、カナ文字はどう組み合わせても意味のない記号にしかならず、意味のない記号を付与されている人間は意味のない人間ということを表明しているようにも思える。これは、上巻の後半、高麗軍が逮捕し、ひどい拷問をおこない、そのうえですべての財産を収奪する重犯罪人たちを「1号」「2号」と称する発想に通底するものがあるし、物語で頻繁に語られる住基ネット→国民ID化とも結びつく。
これはどういうことだろうか。もちろんめくるめくような登場人物の多さにも起因しているだろうが、それ以上に、カナ文字はどう組み合わせても意味のない記号にしかならず、意味のない記号を付与されている人間は意味のない人間ということを表明しているようにも思える。これは、上巻の後半、高麗軍が逮捕し、ひどい拷問をおこない、そのうえですべての財産を収奪する重犯罪人たちを「1号」「2号」と称する発想に通底するものがあるし、物語で頻繁に語られる住基ネット→国民ID化とも結びつく。
そもそも、村上龍は、登場人物にカタカナを使用することが多く、わたしはそに意図について見聞したことがないのだが、今回の物語においては、どこにでもある記号として抹消されそうになった一部品であっても、意志と強みを有したものであれば生きる個を確立できる、という村上龍の基本精神をより明確に表したのだろうか。それとも、名前をもち誰かに認識されることが強いということではない、誰に認識されなくても希望をもてることこそが強さをつくるということを表したのか。
おそらく、この小説は、その物量と登場人物数の相似や(おそらく起こるであろう)カタルシスの描き方という点で、『シンセミア』と比べなければならいない部分がいくつかでてくると思われるが、そのひとつに「名前」をあげていいのかもしれない。じつのところ「名前」はその人物を造形していく上では効率的な記号ではある。しかし、造形されたくないという物語の意志を受け入れるという考え方もある。「この群像こそが主人公だ」と考える場合、後者の手法を選んでしまいそうだが、『シンセミア』は、同じ群像劇ではあるが前者で成功している稀有な例かもしれない。
『半島を出よ』についても、すべてを漢字記名で読み直したとき、おそらく物語の印象はずいぶん異なり、そこに答えが見つかるのかもしれない。また、下巻では、漢字表記の名前の人々が、ある程度、重要な役割を占めてくるようなので、なにかヒントが見つかるかもしれない。いや、見つからないかあ。というか、どうでもいいことなんだろうなあ、きっと。
------------------------
 さて。あまり賢くない印象批評的な横道にそれてしまったが、半分を読んでみての感想にもどると、現在、わたしの頭をかすめているのは、「これを、小説と呼んでいいのか」という考えである。正確に言うと「これまでの小説というジャンルの枠内で議論していいのか」ということになる。それは、『半島を出よ』が、あきらかに、これまで小説の創作手法で書かれたものではないという推測に起因する。もちろん実際にそうなのかはわからない。しかし、この小説はいくつかの点で、プロジェクトにおけるチーム作業の産物であり、アンカーを務めたのが村上龍ではないか、ということが明示的だ。
さて。あまり賢くない印象批評的な横道にそれてしまったが、半分を読んでみての感想にもどると、現在、わたしの頭をかすめているのは、「これを、小説と呼んでいいのか」という考えである。正確に言うと「これまでの小説というジャンルの枠内で議論していいのか」ということになる。それは、『半島を出よ』が、あきらかに、これまで小説の創作手法で書かれたものではないという推測に起因する。もちろん実際にそうなのかはわからない。しかし、この小説はいくつかの点で、プロジェクトにおけるチーム作業の産物であり、アンカーを務めたのが村上龍ではないか、ということが明示的だ。
膨大な参考資料収集と取材を、物語のなかで正確な描写として昇華させていく作業は、あまりにもノンンフィクションの創作手順である。
また「あとがき」では『13歳のハローワーク』から継続したプロジェクトチームの「メンバー」への謝辞が明示されているが、それだけではなく、創作現場への「物資の供給」といった言葉が使われているところをみれば、かなりの度合いで共同作業であったことがうかがえる。もし、短期間でアウトプットしていたとすればなおさらさだ。大きな虚構を村上龍が描き、リアリズムのための小さな事実をプロジェクトで埋めていったというところか。これはなにか、壮大なエンターテイメント映画を製作する作業のようだ。
また、この作業は企業のコミュニケーションツールとして、カタログを作っていくという作業にも似ている。企業と顧客と競合にまるわる膨大なファクトをまず集め、優先順位をつけながら、よりわかりやすいコミュニケーション構造でアウトプットしていくことをゴールとするカタログ制作作業だ。『半島を出よ』は、過去、発信において遺憾なく発揮された幻冬舎マーケティングスタイルが、創作作業にも如実に浸透してきた最初の例になるかもしれない。
もし、これを小説と呼ぶなら、『13歳のハローワーク』もまぎれもなく小説であり、そこまでいえないとしても、村上龍と見城徹もしくは石原正康は『13歳のハローワーク』の作業のときにこのスタイルで小説を創作すればどうなるのだろうか?ということに着想した、とはいえるかもしれない。
もちろん、最終的にテキストに落としたのは村上龍であることは間違いないし、アウトプットがテキストの羅列である以上、どう書いても許されるのが小説というジャンルではある。
ノンフィクションの手法という観点でみれば、カボーティの『冷血』といった前例もあるし(これは正真正銘のノンフィクションではあるが)、実際の創作作業は多かれ少なかれ編集者との共同作業でもある。
しかし、いっぽうで、小説とはきわめて個人的な作業である、という意見もあるだろう。
これらのことを考えていくと、結局は、この最新作も文芸批評的な読み方をされない可能性は高い(批評的な読み方はされるかもしれないが)。前半に限って言えば、そこにある教えは、なにか普遍的な教えである、というより、ビジネスや政治経済の世界において成功するためのノウハウのようである、という点でも、批評的な材料が少ない。
それでも、批評するとすれば、それは「リアル」ということかもしれない。この技法による成果は、読み手が違和感や物足りなさを感じることなく物語の世界に没入できるところだが、しかし、逆に村上龍のこれまでの大型小説に見られた、疾走感やシャープネスが滞っているような印象も生み出してしまっている。これは「リアル」を追求すればするほど、「リアル」から遠ざかっていくことなのだろうか、という読み方だ。
このことについての結論をあせる必要はないだろう。下巻に突入しつつ、ゆっくりと考えてみたい。
いろいろと批判めいたことを書いてしまったが、エキサイティングでスリリングな物語であることは間違いないので、ようは読む側の構えを変えるということだけの問題、という気がしないでもないが。
------------------------
↑参った。なにが言いたいのか分からねえ。
↓「本&読書のblogランキング」で、
↓浄化してください。すみません。


もちろん材料は『半島を出よ』。上巻までを急ぎ足で読んでみた。しかし、急ぎ足で読むには、あまりにも情報量が多すぎて、疲れるテキストではある。
とりわけ、北朝鮮反乱軍である高麗軍については、そもそも人名や地名にリテラシーがないため、それぞれのプロフィールが明確に設定されているにもかかわらず、誰が誰だかわからなくなる。タフな経歴と連動したかたちでのタフなキャラクターじたいも立っているはずなのだが、やっぱり名前と一致しない。
これはイシハラグループにもいえることで、それぞれのメンバーが少年時代に壮絶な人生を送っているにもかかわらず、その出来事じたいは強く記憶に残るのだが、カタカナで表記された人名とはどうも一致しない。
いっぽうで、内閣情報調査室や、会議で議論する総理大臣、官房長官さらには、福岡県知事、市町などの漢字表記の名前は覚えやすく、どれだけ唐突にでてきても特定できる。
もし、高麗軍やイシハラグループのキャラクターが、漢字で記名されていれば、状況は大きく変わっただろうとも感じる。
 これはどういうことだろうか。もちろんめくるめくような登場人物の多さにも起因しているだろうが、それ以上に、カナ文字はどう組み合わせても意味のない記号にしかならず、意味のない記号を付与されている人間は意味のない人間ということを表明しているようにも思える。これは、上巻の後半、高麗軍が逮捕し、ひどい拷問をおこない、そのうえですべての財産を収奪する重犯罪人たちを「1号」「2号」と称する発想に通底するものがあるし、物語で頻繁に語られる住基ネット→国民ID化とも結びつく。
これはどういうことだろうか。もちろんめくるめくような登場人物の多さにも起因しているだろうが、それ以上に、カナ文字はどう組み合わせても意味のない記号にしかならず、意味のない記号を付与されている人間は意味のない人間ということを表明しているようにも思える。これは、上巻の後半、高麗軍が逮捕し、ひどい拷問をおこない、そのうえですべての財産を収奪する重犯罪人たちを「1号」「2号」と称する発想に通底するものがあるし、物語で頻繁に語られる住基ネット→国民ID化とも結びつく。そもそも、村上龍は、登場人物にカタカナを使用することが多く、わたしはそに意図について見聞したことがないのだが、今回の物語においては、どこにでもある記号として抹消されそうになった一部品であっても、意志と強みを有したものであれば生きる個を確立できる、という村上龍の基本精神をより明確に表したのだろうか。それとも、名前をもち誰かに認識されることが強いということではない、誰に認識されなくても希望をもてることこそが強さをつくるということを表したのか。
おそらく、この小説は、その物量と登場人物数の相似や(おそらく起こるであろう)カタルシスの描き方という点で、『シンセミア』と比べなければならいない部分がいくつかでてくると思われるが、そのひとつに「名前」をあげていいのかもしれない。じつのところ「名前」はその人物を造形していく上では効率的な記号ではある。しかし、造形されたくないという物語の意志を受け入れるという考え方もある。「この群像こそが主人公だ」と考える場合、後者の手法を選んでしまいそうだが、『シンセミア』は、同じ群像劇ではあるが前者で成功している稀有な例かもしれない。
『半島を出よ』についても、すべてを漢字記名で読み直したとき、おそらく物語の印象はずいぶん異なり、そこに答えが見つかるのかもしれない。また、下巻では、漢字表記の名前の人々が、ある程度、重要な役割を占めてくるようなので、なにかヒントが見つかるかもしれない。いや、見つからないかあ。というか、どうでもいいことなんだろうなあ、きっと。
------------------------
 さて。あまり賢くない印象批評的な横道にそれてしまったが、半分を読んでみての感想にもどると、現在、わたしの頭をかすめているのは、「これを、小説と呼んでいいのか」という考えである。正確に言うと「これまでの小説というジャンルの枠内で議論していいのか」ということになる。それは、『半島を出よ』が、あきらかに、これまで小説の創作手法で書かれたものではないという推測に起因する。もちろん実際にそうなのかはわからない。しかし、この小説はいくつかの点で、プロジェクトにおけるチーム作業の産物であり、アンカーを務めたのが村上龍ではないか、ということが明示的だ。
さて。あまり賢くない印象批評的な横道にそれてしまったが、半分を読んでみての感想にもどると、現在、わたしの頭をかすめているのは、「これを、小説と呼んでいいのか」という考えである。正確に言うと「これまでの小説というジャンルの枠内で議論していいのか」ということになる。それは、『半島を出よ』が、あきらかに、これまで小説の創作手法で書かれたものではないという推測に起因する。もちろん実際にそうなのかはわからない。しかし、この小説はいくつかの点で、プロジェクトにおけるチーム作業の産物であり、アンカーを務めたのが村上龍ではないか、ということが明示的だ。膨大な参考資料収集と取材を、物語のなかで正確な描写として昇華させていく作業は、あまりにもノンンフィクションの創作手順である。
また「あとがき」では『13歳のハローワーク』から継続したプロジェクトチームの「メンバー」への謝辞が明示されているが、それだけではなく、創作現場への「物資の供給」といった言葉が使われているところをみれば、かなりの度合いで共同作業であったことがうかがえる。もし、短期間でアウトプットしていたとすればなおさらさだ。大きな虚構を村上龍が描き、リアリズムのための小さな事実をプロジェクトで埋めていったというところか。これはなにか、壮大なエンターテイメント映画を製作する作業のようだ。
また、この作業は企業のコミュニケーションツールとして、カタログを作っていくという作業にも似ている。企業と顧客と競合にまるわる膨大なファクトをまず集め、優先順位をつけながら、よりわかりやすいコミュニケーション構造でアウトプットしていくことをゴールとするカタログ制作作業だ。『半島を出よ』は、過去、発信において遺憾なく発揮された幻冬舎マーケティングスタイルが、創作作業にも如実に浸透してきた最初の例になるかもしれない。
もし、これを小説と呼ぶなら、『13歳のハローワーク』もまぎれもなく小説であり、そこまでいえないとしても、村上龍と見城徹もしくは石原正康は『13歳のハローワーク』の作業のときにこのスタイルで小説を創作すればどうなるのだろうか?ということに着想した、とはいえるかもしれない。
もちろん、最終的にテキストに落としたのは村上龍であることは間違いないし、アウトプットがテキストの羅列である以上、どう書いても許されるのが小説というジャンルではある。
ノンフィクションの手法という観点でみれば、カボーティの『冷血』といった前例もあるし(これは正真正銘のノンフィクションではあるが)、実際の創作作業は多かれ少なかれ編集者との共同作業でもある。
しかし、いっぽうで、小説とはきわめて個人的な作業である、という意見もあるだろう。
これらのことを考えていくと、結局は、この最新作も文芸批評的な読み方をされない可能性は高い(批評的な読み方はされるかもしれないが)。前半に限って言えば、そこにある教えは、なにか普遍的な教えである、というより、ビジネスや政治経済の世界において成功するためのノウハウのようである、という点でも、批評的な材料が少ない。
それでも、批評するとすれば、それは「リアル」ということかもしれない。この技法による成果は、読み手が違和感や物足りなさを感じることなく物語の世界に没入できるところだが、しかし、逆に村上龍のこれまでの大型小説に見られた、疾走感やシャープネスが滞っているような印象も生み出してしまっている。これは「リアル」を追求すればするほど、「リアル」から遠ざかっていくことなのだろうか、という読み方だ。
このことについての結論をあせる必要はないだろう。下巻に突入しつつ、ゆっくりと考えてみたい。
いろいろと批判めいたことを書いてしまったが、エキサイティングでスリリングな物語であることは間違いないので、ようは読む側の構えを変えるということだけの問題、という気がしないでもないが。
------------------------
↑参った。なにが言いたいのか分からねえ。
↓「本&読書のblogランキング」で、
↓浄化してください。すみません。














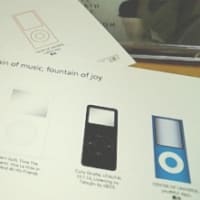
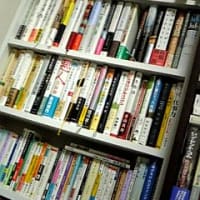
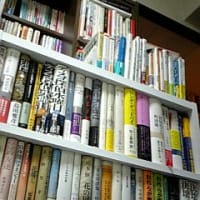

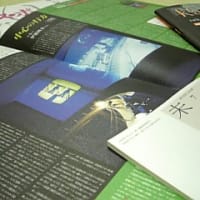

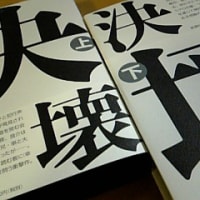

時々、ブログを拝見しております。
私は村上龍に関しては、近年読むたびにがっかりすることが多くて読まなくなってしまったのですが、このような反応を読むと読みたくなってしまうので、危険です。
どうも新しい物語の作り方を見出したのでしょうか?
骨太のブログで、今後どのような本のどのような紹介がされるか、楽しみです。
疾走感やシャープネスが滞っているような印象、それがリアリズムに起因しているというのは僕も強く感じました。僕は物語の作り方が変わったのではなく、物語の世界に対する構築の方法が徹底的にリアリズムに即しているのだと思います。『五分後』では作家の想像力によって世界を構築したのに対して、本作では徹底的な取材と情報分析によって近未来の世界を構築した。そこが両作品の質を決定的に変えているのだろうと思います。そのせいか、威力は小さいが極度に正確なピンポイントミサイルのような印象を受けました。今まで読んだ村上龍の作品の中でも一番重かったです。
ていねいなコメントをいただきありがとうございます。
重要なのは、これを書くことができるのは少なくとも日本では村上龍しかいない、ということと、ある意味で、アンガージュマン的な文学の新しい形式ではないか、と感じています。そこで気づいたのは、ドン・デリーロという作家に近い部分があるのではないかということです。デリーロも、アメリカ社会におけるありうるべき陰謀とありうるべき偽史を活写していて、彼の場合はリアルに書くことで、ほんとうのリアルを実現しているわけですが、そのぶんキアリーさんのおおしゃるようなピンポイントさが、日本人には(もしくは米国人にとっても)わかりにくくなっています。もし、お読みでなければ『アンダーワールド』http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4105418017/ttb0e-22 をご覧ください。
いつか、2つを対比しながら書いてみたいと思います。
ご意見に触発されましたので、これからもコメントなどよろしくお願いします。
余震が続いているようですが、大丈夫でしょうか。
「半島を出よ」は、現在、下巻の最初のほうで、福岡市民と高麗軍のストックホルム症候群のような関係が始まったところです。本筋ではありませんが、こういうところを見るにつけ、村上龍という人は、九州をほんとうに愛しているのだなあ、と思ってしまいます。
そういったところは、じつは小説としては逆にノイジーなのですが、その人柄に免じて許させてしまうところも龍の魅力ともいえます。
shuhitsuさんがWEBで指摘されているように、いま書店の新刊コーナーでは、ほんとうに久しぶりに龍と春樹が並んでいるわけですが、どちらがどうというより、本好きとしてはこの2人がこれだけ長きにわたって書き続けているということに喜びを感じたいところです。春樹が新作だったらもっとよかったんですけれどねえ。
お薦めしていただいた「アンダーワールド」を読んでから書き込もうと思っていたのですが、当分読めそうにありません。ですが必ず読むつもりですので、読んだ暁には拙い書評を書かせていただきたいと思います。
村上龍は「半島を出よ」において疾走感や爆発力のようなものが乏しいことに自覚的だと思います。それらが衰えや加齢に伴う作風の変化に起因するものでないことは今作から明らかです。国家に関わる深遠なテーマや困難なモチーフに果敢に挑戦する村上龍は相変わらずエネルギーの塊です。
つまり村上龍は疾走感や爆発力を抑制してまでもあえて「精度」を選択していると思うのです。商業主義的だと彼を非難する文章をときどき見かけますが、そういった人々に退屈だと捉えかねられないにも関わらず、村上龍は「精度」を選択した。
読後、なぜ「精度」を高めてリアリティを表現しなければならなかったのか疑問でした。
それについて思ったのですが、北朝鮮というモチーフが彼に執拗なまでの細部の描写を要求したのではないでしょうか。10年、20年前に北朝鮮を書いたならばこれほどまでに精緻である必要はなかったかもしれませんし、戦争物のエンターテイメント作品を盛り上げるために想像による北朝鮮を物語に組み込むことも許されたかもしれません。しかし、北朝鮮という存在が顕在化した現代において、北朝鮮を想像することは許されないでしょう。今、北朝鮮という存在は綿密な取材に裏付けられた正確な細部の積み重ねでしか語ることが許されない。「半島を出よ」は精密な細部と900ページを要求し、村上龍はそれに応えたのだと思えてなりません。
名前のカタカナ表記に対する考察が面白いなぁと感じて最初の文章をつい書いてしまいました。
物語において個を回復する。非常に興味深くて惹かれました。
コリョとイシハラグループがカタカナ表記ですが、コリョもイシハラグループも日本にとって外部です。カタカナ表記はその外部性である、という凡庸な解釈をしていた僕にとって目から鱗が落ちるような発想でした。
どうも連レス失礼しました。
最近は『半島を出よ』の検索で、当BLOGを訪れる方が多く、あらためて、龍の人気を感じている次第です。
キアリーさんのコメントにはいくつかの重要な示唆があると思います。
ひとつは、「疾走感や爆発力を抑制してまでもあえて「精度」を選択した」というところで、これにより新しい小説の形がうまれた可能性があるということかもしれません。エンターテイメントのかたちをとってしまいがちですが、本来的にはそうではない。たんたんと事実のような虚構をつくりあげていく静かな小説。
そういった意味で、『半島を出よ』は実際は幻冬舎が15段の新聞広告を使い、読者を煽り大々的に喧伝するようなものではないのかもしれません。
北朝鮮へのスタンスについては、『群像』でのインタビューがなにかのヒントになるかもしれません。
いずれにしても、キアリーさんに触発されたことをベースに、いちどエントリーをあげたいと思います。
とりいそぎお礼まで。