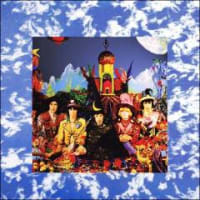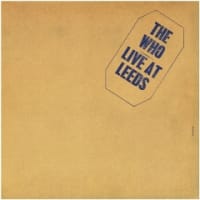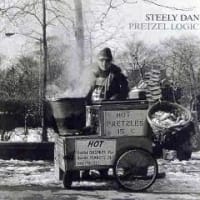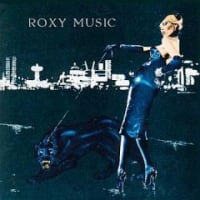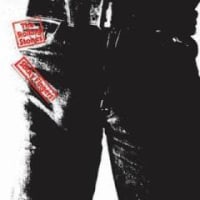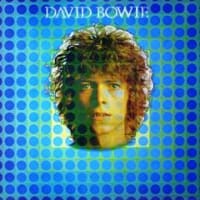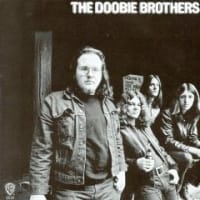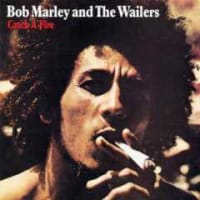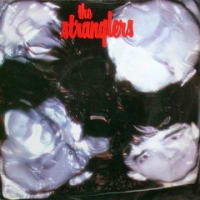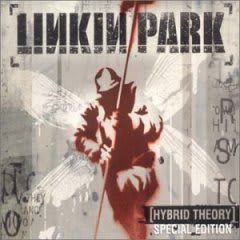
歴史、特に日本史が大好きな私であるが、実は昭和史は余り得意ではない。理由は色々あって、私の小中学生時代である昭和時代というのは、まだ余り天皇に関する議論が自由でなかった。同時に戦前、特に何故日本は戦争に走ったか、また戦中、更には戦後GHQ配下に置いて何が行われたかに関する検証なんて、今の様に自由な意見を言ってはいけない風潮であった。それともう一つ、こっちはもっと大事で、日本史の教科書は大体半分以上が幕末~明治時代より後のことにも係わらず、日本史の講義は当たり前の様に先土器文化あたりから始まる。そして日本史の先生というのは、大概、大学の卒論等、専門分野を授業でも引っ張る。だから、殆どの場合、一年間で第二次世界大戦まで辿りつかない。だからその後は「自習」になる。ところが、私の先輩の大学教授は一般教養の日本史の授業を現代から遡っていく方式を試したところ、これが学生に「わかりやすい」と大好評であったという。なぜならそういうアプローチは、まさに今ある自分のルーツを探すことと同じだかららしいが、これには納得で、例えば現代の「法律」や「制度」が過去の時代ではこうだったという物事の検証は、結果が分かっているだけにその時代時代でこのように工夫してきたという多面的な見方に繋がると思う。
なんでこんなことを言っているのかは、このリンキン・パークというバンドの登場は、まさに私が半ば諦めていたことに希望を与えてくれたからだ。それはこのバンドの音楽が、なるほどここに来たのかという納得もあったが、逆にこの音楽を受け入れたことによって見えてきたのが前述した「歴史の遡り」と同じアプローチによって私自身が失いつつあったものを取り戻すきっかけとなったからだ。
リンキン・パーク。私は実は名盤「メテオラ」を最初に聴いたのだが、この音に出会った喜びも(いつも大袈裟みたいに言っているようだが出会いの感激常日頃にある)忘れない。そう、この音はヘビメタとヒップホップの融合であった。それもただの融合なんてものじゃない。明らかにこれはポップ音楽の新境地開拓である。私は一瞬でこのバンドと音楽の大ファンになった。そして考えた。そう、ここから元を辿っていけばいいのだと。以前にも書いたが私はラップやヒップホップは、その音が出現した頃にポップ音楽と離れていたためにすっかりこのムーブメントを捕まえ損ねてしまった。これは大きな失敗であったし、その後もヘビメタはサバスの全盛期を知っているからなんとか理解できたが、ラップやヒップホップはたしかに1970年代後半にN.Yのストリートで話題になっていた時分にはたまたまそこに居たので肌で感じていた(当時は寧ろ、ブレイクダンスの方が流行っていた)が、その後はビッグヒットになった人たちしか分からなかったし、今世では残念ながらこの音楽は理解できないと思ったものだった。だがこのリンキン・パークは実にわかりやすい音であり、そこにあるヒップホップの要素は実に闊達としていて、また同時にそういう原型に対しての敬意が受け取れる音楽であった。しかも彼らのオリジナリティというのは大変高く、同時に今までのロックとは違った、新時代を彷彿させるものでもあった。この作品の発売はまさに2000年。この年はあのエミネムがヒップホップ領域で革命的な作品を発表する年でもあり、また、レディオヘッドが「キッドA」というある意味でロックの概念を一掃してしまう作品を発表した年でもあった。奇しくも、この年に彼らは、まるで音楽ファンに望まれるが如く、センセーショナルに登場した。
作品タイトルの「ハイブリッド・セオリー」は、かつてリンキン・パークが名乗っていたバンド名である。しかも、彼らがワーナーと契約した際に同名のバンドがいたためにバンド名を変えざるを得なかった。その際に彼らが定期的に車で通りかかっていたサンタモニカの公園の名前に因み、"LINCOLN PARK"への改名を提案したが、インターネットのドメイン名がおさえられていたためにまたまた断念。結局、同じ発音である"LINKIN PARK"に落ち着いたのだが、アルバムタイトルにしたということで、彼らが自分たちの音楽に対する自負と初志貫徹の志しの強さを感じるのであるが。
こちらから試聴できます