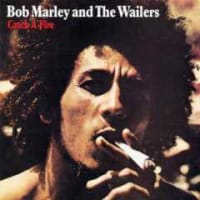この世にたった二人だけ存在する、目に入れても痛くないだろうと思える年上の方が、かれこれ7年前になるだろうか、女子高校に入ったばかりの頃、なにを思いついたのか中学まで頑張って来たテニスを捨てて、「ケイオン」に入ると言い出し、パートはベースをやると言うことになり、そういう面倒臭い話だが喜んで引き受けることになったが、弦楽器は略経験のない娘だったので、フェンダー・ジャズベースのコピーモデルを神田楽器店街に買いにいった。その帰路、クルマの中でどんな曲を演奏するんだと聞いた際に即答したのが、「レッチリの"Scar Tissue"」だって言ったので、なんて怖いもの知らずの愚か者かと思った。そんな娘だから長続きはせず、2年くらいしたら殆どジャ・ベーもどきを弾かなくなった。勿体無かったが真っ赤なボディーだから流石に筆者が扱うこともなく、今はタンスの肥しなのだろうか。なので、未だにこの作品を聴くたびに「そこ」から入ってしまう。レッチリに取って、こんなに大事な作品を、そんなところから入ってしまって申し訳ないが・・・。
この作品はレッチリの新たな決意と出発を記念する意義のあるアルバムである。その伏線は前作「ワン・ホット・ミニット」にも見られたが、薬物中毒という死の淵からジョン・フルシアンテが奇跡的に生還。そしてジョン抜きではこのバンドは成り立たないということを、身をもって感じていたレッチリのメンバーに支えられ、お互いの信頼と強い団結によって制作されたのが本作品である。史上最強テクニックバンドとも言われるレッチリであるが、よく言われるように、彼らは決して高度なテクニックだけで集まったバンドではなく、思想的にも、哲学的にも思いを同じくする、言わばソウルメイトであることは周知の事実である。しかし、それは、故ヒレル・スロヴァクがそうであっても、ジョンは自身がその領域には達せないという自責の念と、一方で彼を現実逃避に追い込んだのではないかというその他のメンバーの自省もあり、この作品の制作に当たっては、過去をすべて削ぎ落としてもこの1枚を作る、という意志と創造力の産物であるといっても過言ではないであろう。まさに、ここに奏でられているのが新生レッチリなのである。一般的にこのアルバムでレッチリはメロウになったと言われるがそうではなく、多分、優しさとか思いやりが音に現れてきたのだと思う。アルバムタイトルの"Californication"は"California"と"fornication"(姦淫)の造語であるが、これは、彼らが拠点としてきたカリフォルニアを中心としたアメリカ文化の敗北のことだという。確かにこのタイトル曲の歌詞には、"The sun may rise in the East at least it settles in the final location"(太陽は東から昇るだろうが、終着駅は決まっている)、"Everybody's been there and I don't mean on vacation"(誰もがそこへ行くが、それはバケイションじゃない)など、前述の敗北を示唆する意味深な言葉が多い。
そして、そんなアルバムが、これまでのキャリアで最高のセールスと評価を与えられた。これによってレッチリは自他共に、世界最高のロックバンドとして認められたことになった。筆者はタイトル曲の歌詞で、"Cobain can you hear the spheres Singing songs off station to station"(コバーン、おまえに聴こえるか 天の歌がそこらの局から流れているのを)という箇所が最も気になった。レッチリはオルタナの終焉をこんなところで予測していて、これは複雑な思いであるが、同時にそれは21世紀に全く新しいオルタナティブが生まれることへの預言でもあるのではないかと。
こちらから試聴できます