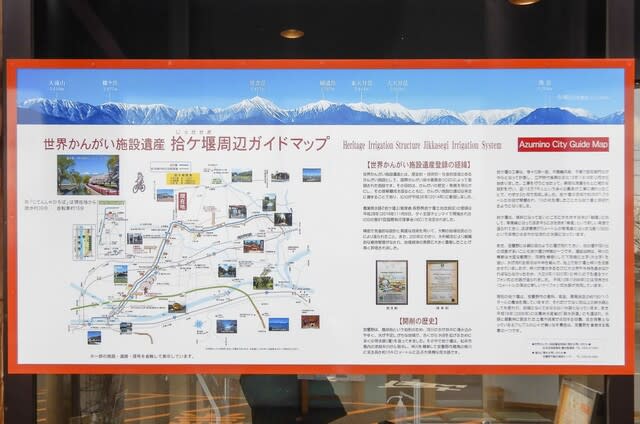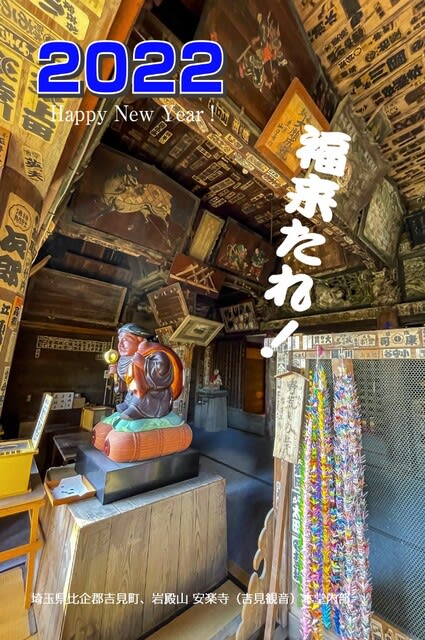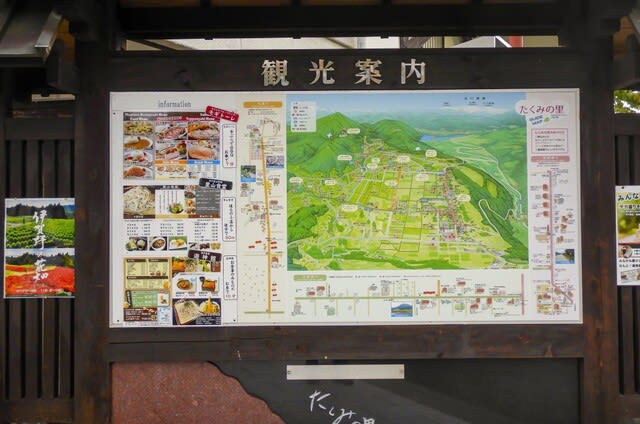今回も前回取り上げた水元公園の続きです。
元々は水元公園の駐車場が「しばられ地蔵」が有る業平山南蔵院に近く、園内を通ってお寺をメインに記事にしようと思っていたのですが、園内に沢山の種類の鳥達がいたので、結局鳥達の写真が多くなってしまいました。
ただ鳥に付いては全くの門外漢、最初から鳥の撮影で行ってはおりませんし、鳥名が違っているかも知れません。また下手な写真のオンパレードとなってしまいましたが、たった2時間も居なかった公園で沢山の種類の鳥を見かけ、バードウオッチングの場所としてご紹介した次第です。鳥名が違っている場合はご指摘頂ければ幸いです。
では一番多く見かけ、のさばっていたユリカモメから・・・

群れて飛んでいたユリカモメ、東京都の鳥としても指定されている。1.

ユリカモメ2.

ユリカモメ3.

ユリカモメ4.

ユリカモメ5.

ユリカモメ6.

ユリカモメ7.

ユリカモメ8.

ユリカモメ9.

ユリカモメ10.

ユリカモメ11.

ユリカモメ12.

ユリカモメ13.

ユリカモメ14.

2番目は池の杭に止まっていたカワウ1.

カワウ2.

カワウ3.

カワウ4.

カワウ5.

カワウ6.

カワウ7.

カワウ8.

3番目はオオバン1.

オオバン2.

オオバン3.

4番目はポピュラーなカルガモ1.

カルガモ2.

カルガモ3.

5番目、写真は1点だけですが、キンクロハジロ。

6番目、集団のホシハジロ。

7番目、そしてこちらは結構見かけたヒドリガモ1.

ヒドリガモ2.

ヒドリガモ3.

ヒドリガモ4.

ヒドリガモ5.

ヒドリガモ6.

ヒドリガモ7.

ヒドリガモ8.

ヒドリガモ9.

ヒドリガモ10.

ヒドリガモ11.

ヒドリガモ12.
後はオマケ、下手な鳥に写真のお口直しに、近所の公園、未だ咲き残った白いサザンカ。

サザンカ(ツバキ科)その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.
今回はここまでです。次回は小鳥をメインにご紹介したいと思います。
最後までご覧頂き有難うございました。
元々は水元公園の駐車場が「しばられ地蔵」が有る業平山南蔵院に近く、園内を通ってお寺をメインに記事にしようと思っていたのですが、園内に沢山の種類の鳥達がいたので、結局鳥達の写真が多くなってしまいました。
ただ鳥に付いては全くの門外漢、最初から鳥の撮影で行ってはおりませんし、鳥名が違っているかも知れません。また下手な写真のオンパレードとなってしまいましたが、たった2時間も居なかった公園で沢山の種類の鳥を見かけ、バードウオッチングの場所としてご紹介した次第です。鳥名が違っている場合はご指摘頂ければ幸いです。
では一番多く見かけ、のさばっていたユリカモメから・・・

群れて飛んでいたユリカモメ、東京都の鳥としても指定されている。1.

ユリカモメ2.

ユリカモメ3.

ユリカモメ4.

ユリカモメ5.

ユリカモメ6.

ユリカモメ7.

ユリカモメ8.

ユリカモメ9.

ユリカモメ10.

ユリカモメ11.

ユリカモメ12.

ユリカモメ13.

ユリカモメ14.

2番目は池の杭に止まっていたカワウ1.

カワウ2.

カワウ3.

カワウ4.

カワウ5.

カワウ6.

カワウ7.

カワウ8.

3番目はオオバン1.

オオバン2.

オオバン3.

4番目はポピュラーなカルガモ1.

カルガモ2.

カルガモ3.

5番目、写真は1点だけですが、キンクロハジロ。

6番目、集団のホシハジロ。

7番目、そしてこちらは結構見かけたヒドリガモ1.

ヒドリガモ2.

ヒドリガモ3.

ヒドリガモ4.

ヒドリガモ5.

ヒドリガモ6.

ヒドリガモ7.

ヒドリガモ8.

ヒドリガモ9.

ヒドリガモ10.

ヒドリガモ11.

ヒドリガモ12.
後はオマケ、下手な鳥に写真のお口直しに、近所の公園、未だ咲き残った白いサザンカ。

サザンカ(ツバキ科)その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.
今回はここまでです。次回は小鳥をメインにご紹介したいと思います。
最後までご覧頂き有難うございました。