とんぼ生まるげに凄まじき人の世ぞ
(とんぼうまるげにすさまじきひとのよぞ)

「生まる}を「生る(ある)(なる)」とする向きもありますが、
これは、本来、“神や天皇など神聖なものが〉生まれる。出現する”
という意味だそうです。
ので、敢えて「生まる」としました。
ご教授お願いいたします。
夏とんぼ未だ白河夜船かな
(なつとんぼいまだしらかわよふねかな)

「とんぼ」だけなら秋の季語。
ですので、不本意ながら「夏」をつけました。
ご教授お願いいたします。
夏とんぼ沈思黙考さながらに
(なつとんぼちんしもっこうさながらに)














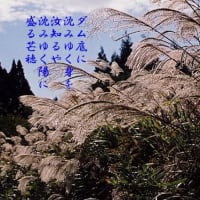



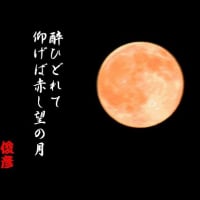


蜻蛉生まる。。。六文字ですね。
蜻蛉の子、子蜻蛉や、などでは駄目ですか?
二句目は夏蜻蛉でいいと思います。
まだ今年は、蜻蛉見てませんが、早いですね。
蜻蛉の赤ちゃん、大きな眼には この世はどう見えるんでしょうね。
平和な世の中であってほしいものです。
弟さん、手術のあと、元気になられるといいですね。
平癒、お祈りしております。
三句の内では、このお句が一番好きです♪
ユーモアが感じられますもの♪
お写真は、断然三枚目!こんなに近く鮮明に♪(驚
弟さんも、きっとそうなりますよ。
とんぼ生まるげに凄まじき人の世ぞ
夏とんぼ未だ白河夜船かな
夏とんぼ沈思黙考さながらに 鎌ちゃんさん
トンボは秋の季語ですか、少し変な気持ちですね。
この頃は蜻蛉も昔ほど見なく、年々少なくなっていそうです。
ほんと凄まじき人の世と似ていますね。
沈思黙考
一度に何十ヶ所も見られる眼には秘密がいっぱいですね。
>夏とんぼ未だ白河夜船かな
>夏とんぼ沈思黙考さながらに
私も「白河夜船」の句が好きですね。
「生る」は確かに本来の趣旨はその通りですが俳句界では
一般的に使われているようですね。巨匠虚子も
「蜘蛛に生れ網をかけねばならぬかな」など・・。
「蜻蛉」の季語は歳時記によって修正が進んでいます。
因みに「現代俳句歳時記」では夏の季語ですね。
私はあまり気にせずに詠んでいますが・・(笑)。
「生まる」この方がきっちりと伝わりますね。
字余りにならないよう使いたい時もありますが
言葉は大事にしたいですね。
夏とんぼ未だ白河夜船かな
白河夜船。。この形容はトンボにぴったりですね。
夏とんぼ沈思黙考さながらに
沈思黙考も言い得てます。
蜻蛉の網目までくっきりと撮られ
熟練のカメラワークですね。見入っています。
「夏とんぼ未だ白河夜船かな」
「夏とんぼ沈思黙考さながらに」
俳句の世界は未だ解らない事ばかりです。
読ませていただくことで少しは身につくかもなんて、甘いでしょうか?
こんなにキレイに写すことが出来るなんて、写真の方も難しいですね。
制限がありすぎも、世界が狭まるような気がしますが。
季語など、現実の季節の移ろいと差が大きいものも
あるのに何故?という気持ちがわきます。
…こんなこと言ったら、思い切り怒られてしまうかもしれませんが。
新しくうまれ出てきた命、この世は実に厳しい世界ではありますが
それでも祝福してあげたいですね。
じっと翅を休めながら何を思うトンボなのでしょう。
うまく詠み取られましたね。
大きな頭をグルグル廻しながら人間の仕草と同じです♪