蘭奢待(らんじゃたい)は正倉院に伝わる香木です。
この名前の中に「東大寺」がそれぞれ入っている事から、
付けられた名前のようです。
蘭の字の東、奢の字の大、待の寺ですね。
本当の名は、黄熟香で、熱帯アジア産のいわゆる沈香(じんこう)です。
ジンチョウゲ科の木の幹に樹脂や製油が付着したもので、
重くて水に沈んでしまうところからその名があり、
その高級品が伽羅(きゃら)です。
1996年、宮内庁正倉院事務所の科学調査で、
蘭奢待の香り成分が伽羅と一致することが確認されているとのことです。
蘭奢待は長さ156cm 重さ11.6kgで、
おそらくは9世紀に日本に渡来し、
宝物として正倉院に保管されて来ました。
特に、中世以降、日本では香道が盛んになりますが、
正倉院にある蘭奢待は幻の名香とでも憧れられたのかも知れません。
どのような香りなのか、試してみたいと思うのは人情でしょう。
時の権力者が少しずつ試してしまったようです。
現在、蘭奢待に切り取った証拠(付箋が貼ってあるそうですが)が
残っているのは、足利義政、織田信長、明治天皇の3人ですが、
足利義満、足利義教もどうやら試してみてしまったようです。
正倉院は勅封の倉庫で、
天皇の許可がなければその扉を開くことができません。
室町幕府の将軍たちは、おそらく許可を取ったのだと思いますが、
信長は東大寺に押しかけ無理矢理扉を開けさせたようです。
延暦寺の焼き討ち事件の後だけに、
東大寺もびびってしまったようで、扉を開け蘭奢待を見せます。
見ればそのままで済む訳はなく、二片切り取られたようです。
信長も、自分だけではきまりが悪かったのでしょう、
一片は正親町天皇に献上されたようです。
信長は、他にも自分を診てくれた、
医聖と呼ばれた名医曲直瀬道三にも下賜したとの話もあります。
既に1000年以上が経過した香木の香り、どのようなものなのでしょうか?
香道に興味見のない僕も好奇心が湧きます。
この名前の中に「東大寺」がそれぞれ入っている事から、
付けられた名前のようです。
蘭の字の東、奢の字の大、待の寺ですね。
本当の名は、黄熟香で、熱帯アジア産のいわゆる沈香(じんこう)です。
ジンチョウゲ科の木の幹に樹脂や製油が付着したもので、
重くて水に沈んでしまうところからその名があり、
その高級品が伽羅(きゃら)です。
1996年、宮内庁正倉院事務所の科学調査で、
蘭奢待の香り成分が伽羅と一致することが確認されているとのことです。
蘭奢待は長さ156cm 重さ11.6kgで、
おそらくは9世紀に日本に渡来し、
宝物として正倉院に保管されて来ました。
特に、中世以降、日本では香道が盛んになりますが、
正倉院にある蘭奢待は幻の名香とでも憧れられたのかも知れません。
どのような香りなのか、試してみたいと思うのは人情でしょう。
時の権力者が少しずつ試してしまったようです。
現在、蘭奢待に切り取った証拠(付箋が貼ってあるそうですが)が
残っているのは、足利義政、織田信長、明治天皇の3人ですが、
足利義満、足利義教もどうやら試してみてしまったようです。
正倉院は勅封の倉庫で、
天皇の許可がなければその扉を開くことができません。
室町幕府の将軍たちは、おそらく許可を取ったのだと思いますが、
信長は東大寺に押しかけ無理矢理扉を開けさせたようです。
延暦寺の焼き討ち事件の後だけに、
東大寺もびびってしまったようで、扉を開け蘭奢待を見せます。
見ればそのままで済む訳はなく、二片切り取られたようです。
信長も、自分だけではきまりが悪かったのでしょう、
一片は正親町天皇に献上されたようです。
信長は、他にも自分を診てくれた、
医聖と呼ばれた名医曲直瀬道三にも下賜したとの話もあります。
既に1000年以上が経過した香木の香り、どのようなものなのでしょうか?
香道に興味見のない僕も好奇心が湧きます。














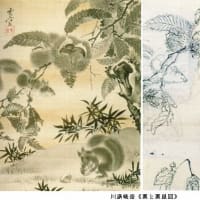







近代の日本では香水のたぐいはあまり用いられなかったようですが、香道が盛んだったこととどのような関係になるのか不思議ですね。
確かに、日本では香道でしたね。
良い香に魅かれるのは、
洋の東西を問わないのかも知れませんが、
その生活習慣などの違いもあるのでしょうね。