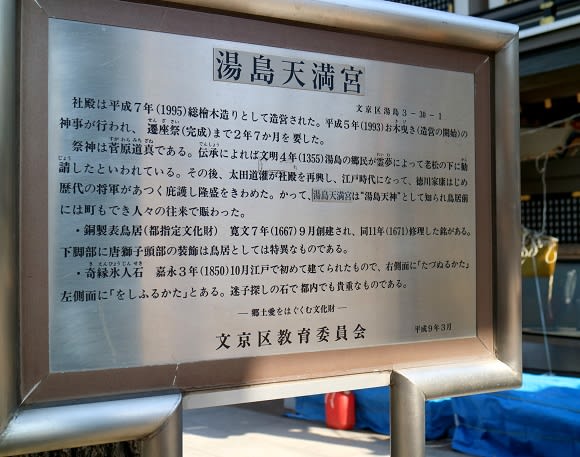図書館から借りていた 「遠野物語 remix」(角川学芸出版)を 読み切りました。
日本の民族学の先駆者とも呼ばれている柳田國男の「遠野物語」を 推理作家の京極夏彦が 原文の内容から 全く逸脱することなく 忠実に現代語訳した 分かり易く読みやすい作品です。
原文の「遠野物語」は 明治43年に発表された 岩手県遠野地方に伝わる民話、伝承を記述した説話集で 119の章からなる作品ということですが 本書「遠野物語 remix」は その119の章を順番ではなく バラバラに配置し ストーリーとして 繋がりやすくし 読みやすいように 再構成されています。
文語体の原文「遠野物語」を 読み解く根性は 有りませんが 「遠野物語」の入門書とも言える本書を見つけて 読んでみました。
実は 2013年7月に 「早池峰山」に登るため 盛岡からレンタカーで登山口まで行き 登り始めたのですが 前線の通過と重なり 暴風雨となってしまい 登頂を断念、途中から引き上げてきたことが有りました。
その際 時間に余裕が出来たため 遠野方面に ドライブ、遠野の一部だけですが 巡りました。
遠野といえば 民話の里、柳田國男の「遠野物語」とイメージを 持って帰ってきましたが、当時は まだ 読書する時間も意欲も無く 読むまでに至っていませんでしたが やっと 読むことが出来ました。
Contents
opening ・・「remix 序」で
著者の京極夏彦は 「この物語は すべて 成城の人柳田國男先生の著された書物遠野物語に記されて居るものなり。・・・・」
と 述べています。
A part ・・「序1」で
著者の柳田國男は 「これから語る話は すべて 遠野の人である 佐々木鏡石君より聞いたものである。・・・・明治42年
2月頃から 折々に聞いた・・・・彼の話を聞いた時 私(柳田)自身が感じたそのままを 一人でも多くの人に伝えたかったから
である」と 述べています。
B part ・・「序3」他
C part ・・「序4」他
早池峰山が語られる時 良く耳にする話が 出ています。

ending ・・遠野郷で古くから行われていた歌舞「獅子踊り」の歌詞が 書き留められています。